
tekowaです。
「土用の丑の日」といえば、うなぎを食べる日として有名ですが、そもそもどんな意味があるのか知っていますか?
実は、これは日本に古くからある「暦」と「五行説」に深く関わる日なのです。
「土用」とはなに?
「土用」とは、季節と季節の“変わり目”を指す言葉で、立春・立夏・立秋・立冬の前の約18日間をそれぞれ「土用」と呼びます。
特に「夏の土用」は、暑さのピークと重なるため、体調を崩しやすい時期とされ、古来より注意が必要な期間とされてきました。
「丑の日」ってどうやって決まるの?
「丑の日」は、十二支の“丑”にあたる日です。
つまり、土用の期間中に巡ってくる「丑の日」が「土用の丑の日」となります。
ちなみに土用期間に「丑の日」が2回ある年は、2回目を「二の丑」と呼びます。
なんでうなぎを食べるの?
「うなぎ」は夏バテ防止に良いとされる栄養豊富な食材。
江戸時代、平賀源内が「う」のつくものを食べると夏負けしないという風習をヒントに、「うなぎを食べよう」と広めたのがきっかけといわれています。
「五行説」との関係
五行説とは、万物を「木・火・土・金・水」の5つの気に分ける古代思想。
それぞれの気には季節や方角、臓器や色などが対応しています。
「土用」は「土」の気が強くなる期間で、「変化」「調整」「中庸」を象徴します。
季節の変わり目に体や気持ちを整える大切なタイミングでもあるのです。
ちなみに、「土」の気が乱れると、胃腸の不調やだるさとして表れやすいともいわれています。
どう過ごしたらいい?
- 胃腸をいたわる食事(温かいスープ、発酵食品など)
- 冷たいもの・生もののとりすぎを控える
- 睡眠・休息をしっかり取る
- 無理な予定を詰め込まず“中庸”を意識
うなぎ以外にも「う」のつく食べ物いろいろ
実は、うなぎに限らず「う」のつく食材を食べると良いと言われています。
例:うどん、梅干し、瓜、牛肉、うに、うし(牛乳)など。
自分に合った「う」のつく整えごはんで、土用のパワーを味方につけましょう!
まとめ
「土用の丑の日」は、ただの“うなぎの日”ではありません。
季節と体を整える大切な節目。
今年は、五行説や土の気を意識して、心と体を整えてみませんか?
土用を味方に、元気に夏を乗り越えましょう!
▶︎五行と土の気、季節の整え方について詳しく知りたい方は
👉【関連記事】「五行で整える!土用の過ごし方と食の知恵」 もどうぞ!

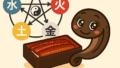
コメント