
11月1日の「計量記念日」は、家庭・学校・職場などで“数字を意識する日”。
この日に改めて考えたいのが、「食品ロス」です。
日本では、年間523万トン(※農林水産省2023年度推計)の食品がまだ食べられるのに廃棄されています。
これは一人あたり毎日茶碗1杯分のご飯を捨てている計算。
“もったいない”を減らすカギは、実は計量にあります。
今回は、整活の視点で「数字で防ぐ食品ロス」について解説します。
◆ 食品ロスの多くは“作りすぎ”から
家庭での食品ロスの約半分は「作りすぎ・買いすぎ」が原因。
“目分量”で作った結果、食べきれなかったという経験は誰にでもあるはずです。
整活では、「食材・分量・人数」を数値化することが第一歩。
たとえば、4人家族での味噌汁なら:
- 水 800ml
- だし 16g(2%)
- 味噌 大さじ4(72g)
このように「何人分=どれだけ作るか」を明確にするだけで、残菜量は大きく減ります。
“はかる”は、“捨てない”の基本です。
◆ “余らせない買い物”は重さから始まる
スーパーで野菜や肉を買うときも、重さの目安を知っているとムダが減ります。
・キャベツ1/2玉=約500g
・鶏むね肉1枚=約250g
・豆腐1丁=約300g
この数字を頭に入れておくだけで、必要量が瞬時にイメージできます。
整活では「買う前に、1回頭で秤にかける」を合言葉にしています。
重さを意識して買うと、余り物の管理もラクになります。
◆ “ちょっと余った”を生かす整活術
余りそうな食材を無駄にしないコツは、計量してリメイクすること。
・野菜は50〜100g単位でジップ袋冷凍。
・ご飯は120g(子ども)/150g(大人)でラップ冷凍。
・肉・魚は1回分ずつ下味冷凍しておく。
これを「数字」で仕分けるだけで、使いやすさが格段に上がります。
“計量して保存”は、“食材を整える”という行為そのもの。
冷蔵庫の中も整い、結果的にロスゼロに近づきます。
◆ “もったいない”の正体は「感覚」
多くの人は「このくらいあれば足りるだろう」と感覚で作ります。
しかし、感覚は日によってブレます。
疲れている日・空腹の日・お祝いの日──すべて感覚が違う。
だからこそ、“数字で固定化”することが安定のカギ。
「いつもはご飯150g、今日は少し減らして130g」
こうして数字で記録すれば、食欲や体調の変化も一目瞭然です。
整活では「数字で感覚を補う」ことを大切にしています。
◆ “食べきる家族”をつくる
整活家庭では、「作る量」と同じくらい「食べきる量」を意識します。
食卓で「もう少し食べられる?」「次に残したくない分量は?」など、
子どもにも“量の感覚”を教えることが食育につながります。
しばこさんの家庭のように、どんなに満腹でも“残さず食べきる”文化を育てると、
自然と食材の扱いにも責任感が芽生えます。
「残したくない」という意識が、家庭内ロスをゼロに導くのです。
◆ “期限を測る”も立派な計量
食品ロスの原因の一つが「賞味期限・消費期限の誤解」。
賞味期限は「おいしく食べられる期間」、消費期限は「安全に食べられる期限」。
ここを混同して廃棄してしまう人が多いのです。
整活では、賞味期限の管理も“数字で可視化”。
シールに「冷蔵○日/冷凍○日」と記入し、キッチンカレンダーで管理する方法がおすすめ。
期限を「数字で見える化」すれば、廃棄のタイミングも整います。
◆ 学校給食・施設でも生きる「計量のちから」
しばこさんのように栄養士や介護福祉士として現場を経験している方にとっても、
計量は「命を守る数字」です。
給食や介護食では、食べ残しを減らすために“1人前の適量”を正確に把握する必要があります。
また、施設では「1食あたり○g」のデータを蓄積しておくと、
食材発注の精度が上がり、無駄な仕入れが減ります。
これも“数字で整える食品ロス対策”。
数字は現場を救う共通言語なのです。
◆ “捨てない料理”はクリエイティブ
残り野菜やごはんをリメイクするのは、整活的には「再構築の美学」。
冷蔵庫の中の半端食材を計量して組み合わせれば、
栄養バランスも整い、新しい一品が生まれます。
・にんじん30g+玉ねぎ40g+ツナ小さじ1→洋風きんぴら
・ご飯120g+卵1個→焼きおにぎり風
・ブロッコリー茎40g+ベーコン1枚→スープ具材に再生
数字があれば、残り物も作品になります。
整活は「ムダを整える=創造する」文化です。
◆ “見えないロス”を意識する
食品ロスは「食べ残し」だけではありません。
・皮を厚くむきすぎる
・根を切りすぎる
・賞味期限を誤って捨てる
こうした“見えないロス”も、数字で意識すれば減らせます。
たとえば、にんじんの皮をピーラーで薄くむくと、廃棄率が5%→2%に減少。
1本あたり約5gの差でも、1年間で数kgの削減に。
数字は「もったいない」を見える化し、家庭の知恵を育てます。
◆ まとめ:“はかる”ことが“いのちをつなぐ”
食品ロスをなくすための第一歩は、スプーンやはかりを持つこと。
作りすぎず、買いすぎず、食べきる。
その積み重ねが、地球・家計・健康を整える行動になります。
整活では、ロス削減を“地球の整活”と呼びます。
計量記念日をきっかけに、「数字でやさしい暮らし」を始めましょう。
食材もお金も、時間も整う“もったいないゼロ”の生活へ。
次回ラスト⑩では、「計量の未来」──デジタル計量とAIの力で広がる“整う暮らし”を展望します。
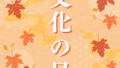
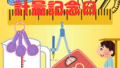
コメント