
11月1日の「計量記念日」は、実は環境にも深い関係があります。
私たちが日々行う「はかる」という行為は、ただの生活動作ではなく、地球資源を守る第一歩でもあるのです。
食材・水・電気・ガソリン・ゴミ──これらすべてが「量」で管理され、計量が正確だからこそ社会が成り立っています。
整活の視点から見れば、“はかる”とは「地球の呼吸を整える行為」。
今回は、SDGs(持続可能な開発目標)と結びつけながら、「はかる」ことで地球と共に生きる方法を考えていきましょう。
◆ “はかる”がつくる持続可能な暮らし
SDGsの中には「エネルギーをみんなに そしてクリーンに(目標7)」「つくる責任 つかう責任(目標12)」「気候変動に具体的な対策を(目標13)」など、資源の使い方に関する目標が並びます。
これらはすべて“量を意識する”ことから始まります。
電気の使用量、水の使用量、食品ロスの量。どれも「はかる」ことで初めて現状が見えるのです。
家庭での整活も同じ。
「電気をつけっぱなしにしない」「食材を無駄にしない」といった行動は、気持ちだけでは続きません。
実際に「どれくらい使っているか」を数字で知ることで、行動が変わります。
数字を“地球との約束”として捉えることが、これからの整う暮らしの形です。
◆ 食品ロスを“はかる”視点
日本の食品ロスは年間約523万トン(農林水産省2024年発表)。これは毎日お茶碗1杯分の食べ物が、日本中で捨てられている計算です。
原因の多くは“目分量の過信”や“買いすぎ”。
スーパーでのまとめ買いや、外食の大盛り注文など、「なんとなく」で決めてしまうことが多いのです。
整活の考えでは、「食を整える=買う量・作る量・残す量を整える」。
たとえば、調理前に1人分の食材を正確に量るだけで、廃棄を大幅に減らせます。
家庭の“はかる意識”が、地球全体の食料サイクルを整える第一歩です。
◆ 水を“はかる”ことで見えてくること
水道を5分間流しっぱなしにすると、約60Lの水が流れます。
これはペットボトル(2L)30本分。
洗顔時や歯磨きの際に水を止めるだけで、1日あたり約20Lの節水になります。
“はかる”ことで数字が見えると、行動が変わります。
「あと10秒流したら何リットル?」と家族で話すだけでも、子どもの環境意識が育ちます。
整活的に言えば、「数字で暮らしを整えることが、地球を整えること」に直結します。
◆ 電気を“はかる”整活
冷蔵庫・エアコン・照明などの電力も、「はかる」ことで意識が変わります。
電力会社のマイページで月間使用量をチェックするだけでも、家庭の“省エネ体質”が見えてきます。
「去年より減ってる!」「夜の電力が多いね」──そんな会話が生まれると、家族全員が主体的に参加できるようになります。
整活では、数字の“比較”をポジティブに活かすことが大切。減らすことを競うのではなく、「整ってきたね」と感じることが目的です。
◆ ゴミを“はかる”=暮らしのリズムを知る
ゴミの量を測るのも整活の一つです。
1日あたりの可燃ゴミの重さを量ってみると、「意外と多い」と驚く人も多いはず。
中には、未使用の食品や包装資材が含まれていることもあります。
「なぜ捨てることになったのか」を振り返ることで、買い物や調理の在り方が変わります。
数字は責めるためのものではなく、“改善への道しるべ”。
整活の基本は、批判ではなく観察です。
◆ 子どもとできる“環境をはかる遊び”
環境教育は「やりすぎない」がコツ。
遊びながら「もったいない」を感じる体験を通じて、地球への優しさを自然に学ばせましょう。
- ・お風呂に入るときに、水をメモリで測って入る
- ・冷蔵庫の扉を開けていた時間をストップウォッチで計る
- ・ゴミ袋の重さをはかって、昨日との違いを比べる
- ・ランチの残りご飯をスケールで測って「どれくらい残したか」確認
- ・ベランダ菜園で水やり量を決めて育てる
数字を通して“環境と遊ぶ”ことが、子どもにとって最高の環境教育。
「数字で見える=変化が分かる」ことは、モチベーションにもなります。
◆ 保育現場で広がる“はかる教育”
保育園でも、最近はSDGsの視点を取り入れた「エコ教育」が広がっています。
たとえば、給食で残ったおかずの重さを一緒に測って「今日は少なかったね!」と喜んだり、水道の使用量を視覚化するポスターを作ったり。
数字を通して環境問題を考えることは、難しい話ではなく「楽しい気づき」。
子どもたちが「もったいないね」と言えるようになることこそ、教育の成果なのです。
◆ 計量と“整活SDGs”の関係
整活の観点から見ると、計量は“バランスの哲学”。
自分の暮らしを整えることが、社会や地球の調和につながります。
家庭での小さな「はかる」が、地球規模の整いに変わる。
食べすぎを防ぐ、電気を節約する、水を無駄にしない──すべてが“地球の健康管理”です。
SDGsを難しく考える必要はありません。
今日使うお湯の量を半分にする。ゴミ袋を1つ減らす。それだけでも立派な整活。
“数字で整える”ことが、誰にでもできる持続可能な習慣なのです。
◆ まとめ:“はかる”は地球への思いやり
計量記念日は、「自分を整える」だけでなく「地球を整える」日。
はかることは、無駄を見つめ、バランスを取り戻す行為です。
エネルギー・食材・水──すべての資源を大切に使う意識を持つことで、整った暮らしと地球の健康が両立します。
整活の最終目的は、個人の健康と地球の健康をつなぐこと。
“はかる”という小さな行動が、未来の整った世界を作るのです。
次回⑥では、「調味料をはかる実験」を通して、家庭でできる味覚の整活を紹介します。
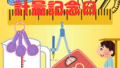
コメント