
「だいたいこのくらい」「適量でOK!」──料理番組やSNSでよく耳にする言葉です。けれど、栄養士の立場から言えば、その“目分量”が思わぬ健康トラブルを招くこともあります。
11月1日の「計量記念日」は、そんな“なんとなく”を見直し、正しく量ることの大切さを知るチャンスです。
整活の視点から見れば、計量とは「体の声を数字で整える」行為でもあります。
◆ なぜ正確に計ることが大事なのか
人の感覚は日によって変わります。体調・気温・湿度・気分によって、同じ「少し」でも加減が違ってくるもの。
たとえば、味噌汁の味噌を「大さじ1」と決めていれば毎回同じ塩分になりますが、目分量では1.5倍に増えることも。塩分過多は高血圧や腎臓疾患のリスクを高め、長期的な健康に影響します。
また、糖質や脂質も「少しぐらい」の積み重ねが体重の増加につながります。料理を整えるためには、まず“数字で整える”ことが基本。味のブレを防ぎ、家族全員の健康を守ることに繋がるのです。
◆ 栄養士が使う3種の“はかり”
料理を正確に整えるには、3つの計量ツールを上手に使い分けます。
- キッチンスケール(はかり)
グラム単位で食材を量る基本ツール。特に粉類・調味料・肉・魚の重さを確認するのに必須。 - 計量カップ
液体をml(ミリリットル)で量る器具。水・牛乳・だし汁・油などを正確に測れる。 - 計量スプーン
小さじ1=5ml、大さじ1=15mlが基準。調味料を入れる前に“すりきり”を意識することがポイント。
特に家庭では「小さじ・大さじ」が感覚的になりやすい部分。砂糖や塩は山盛りとすりきりで2倍以上の差が出るため、レシピ通りの分量を守るだけで料理の安定度がぐっと上がります。
◆ “はかる”は味覚教育の第一歩
保育園や家庭の食育でも、「はかる」は基本。
「味が濃い=おいしい」ではなく、「ほどよい味が一番落ち着く」と感じられる舌を育てることが、整活的な味覚教育です。
計量スプーンを持って子どもと一緒に「大さじ1ってこれくらい」「お砂糖とお塩は重さが違うね」と体験させるだけで、数字と感覚の両方が育ちます。
また、家庭で「今日は味噌をきっちり量ってみよう」と声をかけるだけでも、親子のコミュニケーションになります。数字で会話することは、子どもに“論理的思考”を自然に教える方法でもあるのです。
◆ 栄養計算の裏側にある“整活の思想”
栄養士の仕事では、1食の献立を設計する際、エネルギー・たんぱく質・脂質・炭水化物・塩分・カルシウム・鉄などを細かく計算します。
これを日常に落とし込むと、「毎日の食事を整えるための基準=整活式バランス」になります。
1食の目安として、成人女性では400〜600kcal、男性では500〜700kcalを意識。PFCバランスで見ると、
- P(たんぱく質):13〜20%
- F(脂質):20〜30%
- C(炭水化物):50〜65%
といった割合で整えることが理想です。
これもすべて“計量”から始まります。数字に落とすことで、栄養の偏りを視覚化でき、体の不調や疲れの原因を探しやすくなるのです。
◆ 「適量」ではなく「自分量」を知る
整活の考え方では、「標準量」よりも「自分量」を大切にします。
同じ大さじ1でも、体格・活動量・体質によって必要量は変わります。塩分控えめがいいとされても、汗をよくかく人やアスリートには不足することもあります。
だからこそ、“数字で把握してから調整する”ことが重要です。
たとえば、味噌汁を作るときにいつもより少なめの味噌を使ってみる。家族の反応を見ながら「この薄味でおいしい」と感じられるポイントを探す。これが整活式の“整える味”です。
◆ ダイエットと計量の関係
「ダイエット中だけはかる」という人も多いですが、本来、はかる習慣は一生モノ。
特に“たんぱく質量”を把握することは重要です。
たとえば、鶏むね肉100g=約22gのたんぱく質。1日50gを目標にするなら、肉や魚だけでなく、豆腐や卵を組み合わせてバランスを取ります。
感覚で食べていると、気づかないうちに不足することも。計量は、体の土台を整える行為なのです。
◆ 介護・高齢期の“はかる工夫”
高齢者の場合、計量スプーンやスケールを使うことが難しくなることもあります。
その際は、指や手のひらを目安にした「簡易計量」を取り入れます。
- 人差し指の第一関節=約小さじ1
- 手のひら1枚分の肉・魚=約80g
- 握りこぶし1個分のごはん=約150g
このように、体の一部を“ものさし”にする方法を伝えると、無理なく計量を続けられます。
また、嚥下機能に合わせて“とろみ剤”を正しく量ることも重要。粉末の0.5gの差が飲み込みやすさを左右することもあり、介護現場では緊張感を持って“はかる”習慣を守っています。
◆ 計量器具を整える=キッチンが整う
整活の原点は「道具を整える」こと。計量カップやスプーンを一式そろえるだけで、料理の流れがスムーズになり、キッチンの見た目もすっきり。
お気に入りのデザインや素材の器具を使うことで、毎日の“はかる”が楽しくなります。
計量は「義務」ではなく「暮らしのデザイン」。
整った空間は整った食を生み、整った体を作ります。
◆ まとめ:“はかる”は家庭の安心を作る行為
料理は感性と数字の両輪で成り立ちます。
目分量も大切ですが、それを支えるのは正しい計量。
「数字を信じることで味が安定し、体も心も整う」──これが整活式の食の考え方です。
計量記念日には、ぜひスプーンを手に取って、いつもの味を数値で見つめ直してみましょう。きっと“おいしさ”の理由が見えてくるはずです。
次回④では、「子どもと学ぶ“はかる遊び”」をテーマに、保育園・家庭・自由研究でできる楽しい体験を紹介します。
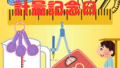
コメント