
tekowaです。
10月24日の国連デーは、国連憲章が発効した日。 平和と人権、そして「すべての人に教育を」という願いを実現するため、数多くの国連機関が活動しています。 その中でも教育・文化・科学を通じて人々をつなぐのが、ユネスコ(UNESCO)です。 世界遺産登録で知られるユネスコですが、その本来の使命は「教育を通じて平和を築く」こと。 この記事では、ユネスコの役割と教育支援の実際、そして日本との関わりを紹介します。
ユネスコとは?
ユネスコ(UNESCO:United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/国際連合教育科学文化機関)は、1945年に設立されました。 第2次世界大戦の悲劇を経て、「戦争は人の心の中で生まれるものである。ゆえに人の心の中に平和のとりでを築かなければならない」という理念を掲げています。
この理念のもと、ユネスコは教育・科学・文化・コミュニケーションの分野で国際協力を推進しています。 世界遺産登録で有名ですが、活動の中心は「教育支援」と「文化多様性の保護」にあります。
ユネスコの教育支援とは?
ユネスコの教育支援は、世界中の誰もが「学ぶ権利」を持つ社会を目指す取り組みです。 その根幹を支えるのが、以下の3つの柱です。
- 1. 教育の普及と質の向上
- 2. 教師の育成と教育政策支援
- 3. ジェンダー平等と包摂的教育
① 教育の普及と質の向上
ユネスコは、教育を「すべての人の基本的人権」と位置づけています。 特に、開発途上国ではまだ1億人以上の子どもが学校に通えていません。 識字教育プログラムを通じて、子どもから大人まで学ぶ機会を広げています。
代表的な取り組みとして、「EFA(Education for All)」や「SDG4:質の高い教育をみんなに」の推進があります。 これらは、初等教育の無償化や中等教育へのアクセス拡大を目標としています。
② 教師の育成と教育政策支援
ユネスコは、教師の不足や教育の質の格差を是正するため、各国政府と連携して教育制度の基盤整備を支援しています。 「教育の質は教師の質に比例する」という考えのもと、研修プログラムや教材開発、カリキュラム設計の支援を行っています。
また、ICT教育(デジタル学習)を推進し、オンライン教育や遠隔授業を通して教育機会を拡大。 新型コロナウイルスのパンデミック以降、この分野の重要性はますます高まっています。
③ ジェンダー平等と包摂的教育
ユネスコは「教育におけるジェンダー平等」を重要課題としています。 特に開発途上国では、家庭の貧困や早婚、文化的慣習により、女子が教育を受ける機会を奪われるケースが多くあります。 ユネスコは、女子教育支援プログラムを通じて、女性が自立し社会に参加できる力を育んでいます。
また、障がい児や少数民族の子どもなど、教育から取り残されやすい立場の人々にも焦点を当てています。 「誰一人取り残さない教育(Inclusive Education)」の実現を目指して活動を続けています。
世界遺産だけじゃない!ユネスコのもう一つの顔
ユネスコは、世界遺産だけでなく「無形文化遺産」や「世界の記憶」といった文化保護活動も行っています。 これらの活動は、教育と密接に関わっています。 なぜなら、文化や伝統を学ぶことが「自分のルーツを知る教育」につながるからです。
たとえば、日本の「和食」や「能楽」「和紙」などがユネスコ無形文化遺産に登録されています。 これらは単なる観光資源ではなく、次世代に伝えるための“生きた教材”でもあります。
ユネスコとSDGsの関係
ユネスコはSDGs(持続可能な開発目標)のうち、特に目標4「質の高い教育をみんなに」の実現を牽引しています。 さらに、教育を通じて以下の目標にも寄与しています。
- 目標5:ジェンダー平等を実現しよう
- 目標10:人や国の不平等をなくそう
- 目標16:平和と公正をすべての人に
つまりユネスコは、「教育を通じてSDGsすべてを支える」役割を担っているのです。
日本とユネスコの関わり
日本は1951年にユネスコに加盟し、長年にわたり積極的に貢献しています。 ユネスコの理念は「教育を通じて平和を築く」という点で、日本の戦後復興とも深く結びついていました。
日本発のユネスコ活動
- ユネスコスクール:平和・環境・人権などをテーマに学ぶ学校。全国で約1,300校が加盟。
- 世界寺子屋運動:読み書きできない大人に学ぶ機会を提供。アジア・アフリカで展開。
- 無形文化遺産の保護:「和食」「祭り」「和紙」など、日本の文化を後世に伝える活動。
特に「世界寺子屋運動」は、日本の“学び直し文化”が世界に広がった好例です。 一人の学びが地域を変え、地域の発展が平和につながるという理念を体現しています。
教育と平和はセットである
ユネスコの信念は、「教育なくして平和なし」。 戦争の記憶が薄れていく中で、教育を通じて他者を理解し、多様性を尊重する心を育むことこそが平和の基礎です。
また、教育は単なる知識習得ではなく、「自分で考え、選び、行動する力」を育てることでもあります。 これはまさに、子どもたちがこれからの時代を生き抜くための「生きる力」です。
私たちにできること
ユネスコの教育支援は、寄付や募金だけではなく、日常の中で参加できます。 たとえば、
- 地域のユネスコ協会に参加する
- ユネスコスクールの活動に関心を持つ
- 文化や伝統行事を子どもと一緒に学ぶ
- 国際教育やSDGs学習のイベントに参加する
- 家庭で“学びを楽しむ”文化を育てる
「教育を支援する」というと大きなことに聞こえますが、まずは家庭や地域から“学ぶ喜び”を伝えることが第一歩です。 その積み重ねが、世界平和への小さな灯になります。
まとめ
ユネスコの活動は、教室や教材を超えた「心の教育」を広げること。 戦争や貧困のない未来をつくるためには、知識よりも「理解と共感」が必要です。 教育はその扉を開く鍵です。 国連デーに改めて、学ぶことの尊さ、そして学び続けることの意味を考えてみませんか?
次回は「国連と気候変動対策(UNEP・UNFCCC)」について解説します。

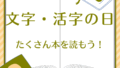
コメント