
tekowaです。
10月18日は「冷凍食品の日」です。
忙しい現代人の食生活を支える存在として、冷凍食品はすっかり私たちの暮らしに溶け込んでいます。
今回は、この記念日が制定された背景や意味、そして冷凍食品がどのように進化してきたのかを、栄養士の視点から紹介します。
冷凍食品の日の由来
「冷凍食品の日」は、1986年(昭和61年)に日本冷凍食品協会によって制定されました。
10月は“食欲の秋”として食への関心が高まる時期であり、18日は「冷凍(10=れいとう)」の語呂合わせから選ばれています。
また、冷凍食品の普及と品質向上を広く知ってもらうことを目的としています。
冷凍食品のはじまり
冷凍技術の歴史は古く、1920年代のアメリカで誕生した「フリージング技術」が原点といわれています。
日本では1950年代に家庭用冷凍庫の普及が進み、魚や野菜などの冷凍食品が一般家庭にも浸透しました。
当初は「味が落ちる」「冷凍臭がする」などのイメージがありましたが、技術の進歩により、現在では作りたてに近い品質を保つことが可能になっています。
なぜ冷凍食品が必要とされるのか
冷凍食品が私たちの生活に欠かせない理由は、単なる“便利さ”だけではありません。 保存性の高さ、安全性、そして栄養価の維持――これらの要素が揃っている点にあります。
- 保存がきく: 食材を長期保存でき、食品ロス削減にもつながる
- 衛生的: 冷凍状態で菌の繁殖が抑えられる
- 栄養を逃さない: 急速冷凍により、ビタミンなどの栄養素が保持されやすい
- 時短・簡便: 調理時間を短縮できるため、共働き世帯や高齢者にも人気
とくに、野菜の冷凍技術は年々向上しており、ブロッコリーやほうれん草などは収穫後すぐに急速冷凍することで、フレッシュな状態をキープしています。
冷凍食品が社会にもたらした変化
冷凍食品の普及は、単に家庭の時短を叶えただけではなく、社会全体にも大きな変化をもたらしました。
- 共働き世帯の食生活を支える
- 学校・病院・介護施設などで安定した食の提供を実現
- フードロスの削減と物流の効率化
- 災害時や緊急時の食料備蓄として活用
特に近年では、冷凍技術の進化によって「おいしさ」と「健康」を両立できる商品が増えています。 栄養バランスを考えた冷凍弁当や、電子レンジだけで完成する一汁三菜のセットなど、ライフスタイルに合わせた選択肢が広がっています。
栄養士の視点から見た冷凍食品の魅力
栄養士の立場から見ると、冷凍食品は「うまく使えば健康の味方」です。 野菜を下処理して冷凍しておくことで、忙しい日でもすぐに栄養バランスを整えられます。 また、旬の時期に冷凍された野菜や魚は、通年を通して安定した栄養価を保つことができます。
一方で、味付けが濃い・脂質が多い冷凍食品もあるため、選び方には注意が必要です。 ラベル表示を確認し、塩分やカロリーを意識して選ぶことで、冷凍食品をより健康的に活用できます。
まとめ
「冷凍食品の日」は、ただの語呂合わせの記念日ではなく、食文化や技術の進歩を祝う日でもあります。 冷凍食品は、時代のニーズに応える形で進化し、今では家庭・学校・介護施設・病院と、あらゆる現場で欠かせない存在です。 忙しい毎日の中でも、冷凍食品を上手に取り入れることで、栄養バランスの取れた食生活を無理なく続けることができます。

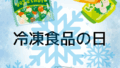
コメント