
tekowaです。
毎年10月10日は「目の愛護デー」とされています。 学校や眼科、地域イベントなどで「目を大切にしましょう」という啓発活動が行われるため、一度は耳にしたことがある方も多いでしょう。 しかし、この「目の愛護デー」がなぜ10月10日に制定されたのか、どんな歴史があるのかを詳しく知っている人は少ないかもしれません。 今回は、目の愛護デーの由来と歴史を掘り下げて解説します。
目の愛護デーの始まり
目の愛護デーは、1931年(昭和6年)に日本で制定されました。 当時は「視力保存デー」という名前で始まり、国民に視力保護の重要性を呼びかけるために設定されたものです。 その後、戦後の混乱期を経て1950年(昭和25年)に改称され、現在の「目の愛護デー」という名称が使われるようになりました。 つまり、90年以上の歴史を持つ記念日なのです。
なぜ10月10日なのか?
10月10日が選ばれた理由にはいくつかの説があります。 その中で最も有名なのが「10・10」と数字を横に並べると、人の目と眉の形に見える、というユニークな理由です。 「目を連想させる日付」として覚えやすいことから定着したと言われています。 また、秋は夏の強い紫外線や生活習慣による視力の疲労が表れやすい季節であり、この時期に目の健康を見直すことが重要とされた背景もあります。
制定当時の背景
昭和初期の日本では、産業の発展とともに近代的な労働環境が整備されつつありました。 工場労働や事務作業に従事する人々が増え、視力の低下や眼病が社会問題となっていたのです。 また、子どもたちの近視や眼疾患も増加しており、国全体で「視力を守る」取り組みが必要とされていました。 そうした時代背景の中で「視力保存デー」として始まり、戦後には「目の愛護デー」として引き継がれたのです。
戦後から現代への発展
戦後の日本は復興期にあり、国民の健康意識が高まりました。 1950年に「目の愛護デー」として再スタートを切ると、全国で視力検査や眼病予防の啓発活動が行われるようになりました。 特に学校や職場での視力検査が普及したのも、この頃の流れと関連しています。 現在では、眼科医会や地域の保健機関が主体となり、視力低下の予防や早期発見の重要性を呼びかけています。
国際的な広がりとの関係
実は、世界的にも「目の健康を守る日」が設定されています。 例えば、世界保健機関(WHO)や国際失明予防機関(IAPB)は、10月の第2木曜日を「世界視力デー(World Sight Day)」と定めています。 日本の「目の愛護デー」と近い時期に行われるため、国内外で目の健康を啓発する大きな流れが生まれているのです。
現代社会における目の愛護デーの意義
現代はスマホやパソコンの普及により、目を酷使する時代です。 特に子どもの近視の増加や、働き世代の眼精疲労、さらには高齢者の白内障や緑内障など、世代ごとに異なる目のトラブルが問題視されています。 そうした中で「目の愛護デー」は、国民全体が目の健康を意識するきっかけとなっています。 眼科検診や生活習慣の見直しを促す点で、今なお重要な役割を果たしているのです。
まとめ
目の愛護デーは1931年に「視力保存デー」として始まり、戦後の1950年に「目の愛護デー」と改称されました。 10月10日という日付には「10・10」で目と眉を連想できるユニークな由来があります。 制定当時の背景には近代化による視力低下問題があり、現代ではデジタル機器や高齢化に伴う目の健康課題に対応する啓発活動へと発展しています。 今年の10月10日には、ぜひ自分や家族の目の健康について改めて考えてみてください。
次回は「目の愛護デーの目的と意義」について解説します。
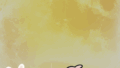
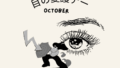
コメント