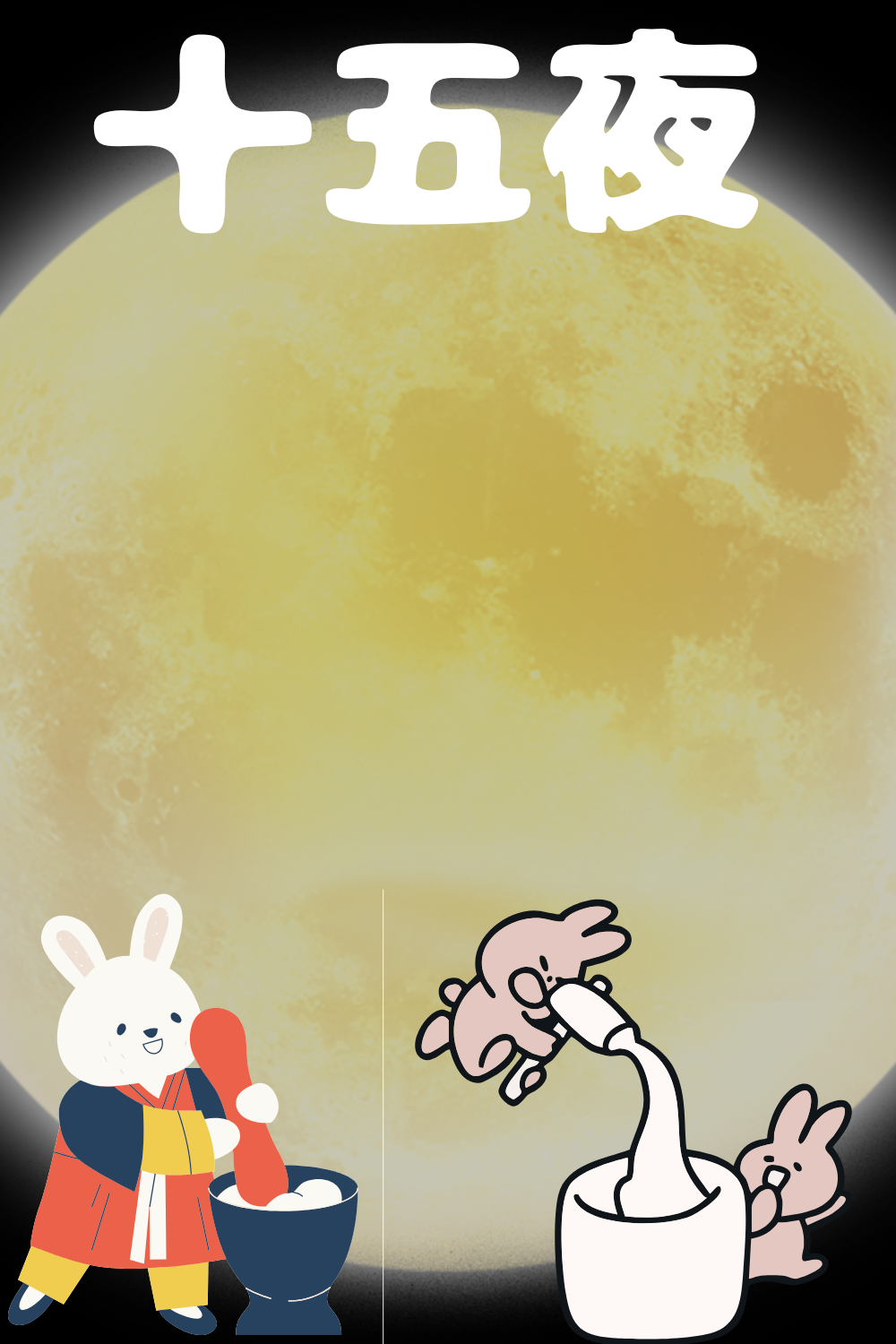
tekowaです。
秋の夜空を彩る「お月見」といえば十五夜が有名ですが、実は日本には「十三夜」や「十日夜(とおかんや)」といった関連行事もあります。これらを合わせて「お月見三大行事」と呼ぶ地域もあり、十五夜だけでは語りきれない日本独自の月見文化が息づいています。本記事では、十五夜と十三夜・十日夜の違いや意味をわかりやすく解説します。
十五夜(中秋の名月)とは?
十五夜は旧暦8月15日に行われる月見行事で、「中秋の名月」として親しまれています。稲刈りの時期にあたるため、収穫感謝の意味も込められています。丸い月を眺め、団子や里芋、ススキを供えて自然の恵みに感謝するのが特徴です。十五夜は一年で最も月が美しいとされ、日本の月見文化の中心的存在です。
十三夜とは?
十三夜は旧暦9月13日にあたる月見行事です。十五夜に次いで美しい月とされ、日本独自の風習として広がりました。中国にはない日本ならではの文化であり、「後の月見」と呼ばれることもあります。 また「十五夜と十三夜の両方を月見しないと片見月(かたみづき)になり縁起が悪い」と言われる地域もあり、両方を楽しむのが良いとされました。
十三夜には栗や枝豆を供える風習があるため「栗名月」「豆名月」とも呼ばれます。秋の実りを再び感謝する意味合いが強く、十五夜と並んで親しまれています。
十日夜(とおかんや)とは?
十日夜は旧暦10月10日前後に行われる行事です。十五夜・十三夜が月見中心であるのに対し、十日夜は農耕儀礼としての性格が強いのが特徴です。特に稲刈りが終わる時期であるため、「収穫を終えたことを感謝する行事」として位置づけられてきました。
地域によっては、子どもたちが藁で作った神馬(かみうま)を立てて田んぼを回り、収穫を感謝し来年の豊作を祈る風習もあります。関東を中心に伝わる文化で、十五夜や十三夜と組み合わせて秋の収穫行事として大切にされてきました。
お月見三大行事のつながり
十五夜・十三夜・十日夜は、それぞれ時期も意味も異なりますが、共通して「収穫感謝」と「月を愛でる」ことが根底にあります。十五夜で豊作を祈り、十三夜で再び感謝を捧げ、十日夜で収穫の終わりを祝い感謝する。この流れは、自然と共生してきた日本人の暮らしを象徴しています。
現代に生きる月見文化
現代では十五夜だけを楽しむ家庭が多いですが、地域によっては十三夜や十日夜の風習が受け継がれています。スーパーや和菓子店でも「栗名月」「豆名月」と銘打った商品が並ぶことがあり、伝統が現代の生活に溶け込んでいることがわかります。
まとめ
十五夜は「中秋の名月」として月を愛で、十三夜は「栗名月・豆名月」として再び収穫に感謝し、十日夜は「収穫の締めくくり」として行われる行事です。三つを合わせてお月見三大行事とすることで、日本人が自然と共に歩んできた文化の豊かさが見えてきます。今年は十五夜だけでなく、十三夜や十日夜にも目を向けてみてはいかがでしょうか。
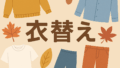
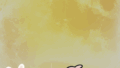
コメント