
tekowaです。
秋分の日は「昼と夜の長さが等しくなる日」であり、同時に「祖先をうやまい、亡くなった人々をしのぶ日」として国民の祝日に定められています。 この文化的な背景は、高齢者施設における行事やレクリエーション活動とも深く結びついています。 施設で生活する高齢者の方々にとって、秋分の日は家族や地域社会とのつながりを感じ、心を豊かにする大切な機会です。 この記事では、秋分の日に高齢者施設で行われる行事や、その意義について紹介します。
高齢者施設における秋分の日の意義
高齢者施設では、季節の行事を通じて生活にリズムや潤いを与えることが大切にされています。 秋分の日は「お彼岸の中日」にあたるため、先祖供養や自然への感謝をテーマにした活動がよく取り入れられます。 また、秋の味覚や伝統文化を楽しむことで、入居者の方々が懐かしい記憶を呼び起こし、心身の健康にも良い影響を与えるのです。
秋分の日に行われる主な行事
高齢者施設で実施される秋分の日の行事には、以下のようなものがあります。
- お彼岸法要や慰霊祭:僧侶を招いて読経を行い、先祖や亡くなった方をしのぶ
- お墓参り代行やオンライン参拝:外出が難しい方に代わり、施設職員が供花を行ったり、リモートで参拝を中継する
- 季節の食事提供:おはぎや栗ご飯、秋の果物を使ったメニューで季節感を楽しむ
- 音楽や工作のレクリエーション:秋の歌を合唱したり、紅葉の壁飾りを作ったりする
- 家族交流会:秋分の日を機に家族が面会に訪れ、一緒に食事や行事を楽しむ
食事で感じる秋分の日
食事は季節を感じる最も身近な手段です。 秋分の日には「おはぎ」が欠かせません。 小豆の赤い色には邪気を払う意味があり、昔から供養の食べ物とされてきました。 また、栗ご飯、さつまいも、きのこ、秋刀魚など旬の食材を取り入れた献立は、高齢者にとって栄養価が高く、食欲を引き出す工夫にもなります。
レクリエーション活動の工夫
高齢者施設では、秋分の日に合わせたレクリエーションを行うことで、入居者が季節を感じられるようにしています。 例としては以下のようなものがあります。
- 紅葉やすすきをモチーフにした貼り絵・塗り絵
- 秋の歌(「もみじ」「赤とんぼ」など)を歌う音楽療法
- 俳句や短歌づくりで季節を表現する
- お彼岸にまつわる話を聞き、思い出を語り合う回想法
これらの活動は脳の活性化や情緒の安定につながり、認知症予防にも役立つとされています。
秋分の日と家族とのつながり
施設で過ごす高齢者にとって、家族との交流は大きな楽しみの一つです。 秋分の日には家族を招いて「交流会」や「合同食事会」が開かれることもあります。 お彼岸の時期に合わせて家族が集まりやすい環境を整えることは、入居者の安心感や幸福感につながります。
まとめ|秋分の日は心をつなぐ行事
秋分の日は、高齢者施設において「先祖を敬い、自然に感謝する日」として重要な役割を果たしています。 法要や食事、レクリエーションを通じて入居者が季節を感じ、心豊かに過ごすことができます。 また、家族や地域社会とのつながりを深めるきっかけにもなるため、秋分の日はまさに「心をつなぐ日」といえるでしょう。 2025年の秋分の日には、施設でも家庭でも、ぜひ感謝と絆を再確認する時間を持ってみてください。
次の記事では、「秋分の日の旅行・おでかけスポット」についてご紹介します。

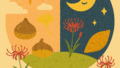
コメント