
tekowaです。
子どもの成長にとって「噛む力=歯ぢから」は欠かせない要素です。特に幼児期は顎や歯、そして口周りの筋肉が発達する大切な時期。この時期に噛む習慣がしっかりと身についているかどうかは、将来の歯並びや発音、さらには集中力や学習力にまで影響を及ぼします。今回は保育士補助や幼児食マイスターとしての視点も交えながら、幼児期に大切な噛む習慣の作り方について解説します。
なぜ幼児期に噛む習慣が大切なのか
幼児期は、乳歯から永久歯への移行や顎の成長が進む時期です。この時期に噛む経験が不足すると、以下のような問題が起こりやすくなります。
- 顎の発達不足で歯並びが乱れる。
- 発音が不明瞭になる。
- 集中力が持続しにくい。
- 消化不良や偏食につながる。
幼児期に噛む習慣を作るポイント
① 離乳食からの工夫
離乳食を与えるとき、やわらかすぎるペーストに頼りすぎず、月齢に応じて「舌でつぶせる硬さ」や「歯ぐきで噛める硬さ」に段階的に進めることが重要です。偏食や丸のみを防ぐためにも、いろいろな食感を体験させましょう。
② 噛みごたえのある食材を取り入れる
毎日の食事に、自然に噛む習慣を育てる食材を取り入れましょう。例としては、にんじんスティック、きゅうり、れんこんチップス、とうもろこしなど。噛む楽しさを感じられる食材を選ぶことがポイントです。
③ 遊びを通じたトレーニング
幼児は遊びの中で力をつけていきます。噛む習慣も同じで、口周りの筋肉を鍛える遊びを取り入れるのがおすすめです。
- シャボン玉遊び:息を吹くことで口の筋肉を強化。
- 風船ふくらまし:顎や口の周りを鍛える。
- 歌や手遊び歌:口を大きく開けて歌うことで発声・咀嚼筋のトレーニングになる。
④ 食事環境の工夫
幼児期は食事環境も大切です。一人で食べさせるより、家族や保育園の友だちと一緒に食べることで自然と噛む回数が増えます。保育士補助としても、食事の時間に「よく噛んでね」と声掛けすることは習慣作りに有効です。
実体験から見る噛む力の違い
例えば、わが家の下の子(2歳9か月)は小魚やぬか漬けきゅうりなど噛みごたえのあるものも喜んで食べ、自然と顎が鍛えられています。一方で上の子(5歳9か月)は離乳食期に偏食があり、噛む経験が不足したため顎がやや弱め。食べるものは増えましたが、噛むことを忘れてしまうことがあり、声掛けが欠かせません。
このように、幼児期の食習慣や声掛けの工夫がその後の噛む力の差につながっていきます。
親や保育者ができる工夫
- 姿勢を正す: 足が床につく高さの椅子で、背筋を伸ばして食べる。
- 食材の切り方を工夫: 小さく切りすぎず、噛む必要がある大きさにする。
- おやつ選び: 柔らかいゼリーやスナックだけでなく、歯ごたえのあるおやつも取り入れる。
- 楽しい雰囲気で: 食事中に「よく噛んでね」と笑顔で声掛けする。
まとめ:幼児期の噛む習慣は一生の宝
幼児期は噛む習慣を作るゴールデンタイムです。この時期にしっかりと歯ぢからを育てることで、将来の歯並びや健康、集中力に良い影響を与えます。保育や家庭でできる小さな工夫を積み重ね、楽しみながら噛む習慣を育てましょう。歯ぢから探究月間をきっかけに、今日から意識して取り入れてみてください。

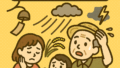
コメント