
tekowaです。
夏祭りや花火大会で手にする「うちわ」や「扇子」。どちらも風を送るための道具ですが、形やたたみ方、用途が違うことに気づいたことはありますか?
今回は、この2つの“和の風アイテム”の違いを、歴史・構造・文化の視点からじっくり解説します。日本の夏に欠かせない、奥深い「風の道具」の世界へようこそ。
うちわと扇子、基本の違いをチェック
| 道具 | 特徴 | 代表的な使用場面 |
|---|---|---|
| うちわ | 丸型・固定式・広い面で風を送る | お祭り・広告・台所・火起こし |
| 扇子 | 折りたたみ式・持ち運びやすい・細かな風 | 茶道・舞踊・礼儀作法・フォーマルな場 |
見た目も用途も意外と違いますよね。
うちわのルーツは中国→火の道具から進化
うちわの原型は、古代中国から伝わった「団扇(だんせん)」。火を起こすために使われていたとされ、日本でも奈良時代には記録が残っています。
平安時代以降は、貴族の顔を隠す道具(儀礼用)としても使われ、やがて庶民の涼をとる道具へと変化しました。
特に江戸時代には、職人による手作りの「丸うちわ」「渋うちわ」「竹骨うちわ」などが登場。現在では広告やノベルティなどにも多用されています。
扇子の登場と“たためる文化”の誕生
扇子は、日本で独自に発展した「たためる道具」です。平安時代にはすでに存在し、当初は木簡(もっかん=文字を書く木の板)を折り重ねた「檜扇(ひおうぎ)」が使われていました。
その後、紙と竹を組み合わせた“今の形”に近い扇子が生まれ、やがて舞踊・能・茶道など、礼儀作法の中に取り入れられていきます。
「閉じて運べる」という構造は、海外でも高く評価され、西洋の折りたたみ式扇子のルーツになったとも言われています。
使い方で広がる“和の知恵”
うちわは広い面で風を送るのに向いており、キッチンでの火起こしや虫よけ、団扇絵としての芸術表現にも活用されてきました。
一方、扇子は狭い空間でも控えめに風を送れるため、茶席や劇場、着物姿に合わせての「気遣いの道具」として使われます。
現代のうちわ・扇子事情
- ・ポリエステル製のクールタイプうちわ
- ・カバンに入るコンパクト扇子
- ・インテリアとしての飾り扇子
最近では、アニメやアイドルの応援グッズとしての“ジャンボうちわ”や、夏のギフトとしての“高級扇子”も人気です。
ちょこっと観察ヒント💡
家にあるうちわと扇子をくらべてみよう。風量・材質・音・使いやすさなどを記録すると、自分なりの「涼しさマップ」が作れます。紙や竹の違いも要チェック!
まとめ|風を仰ぐその道具にも、日本の美意識が宿る
うちわと扇子――どちらもただの涼む道具ではありません。それぞれに長い歴史があり、使い方や場面によって意味を持ち、そこには“日本らしさ”が詰まっています。
祭りの日に配られたうちわ、浴衣に差した扇子、贈答品としての飾り扇――。手にしたその瞬間、風だけでなく「文化」も仰いでいるのかもしれませんね。
次回は「線香花火が落ちるまでの時間」──静かな美しさに潜む実験的な観察の旅へ🔥

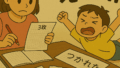
コメント