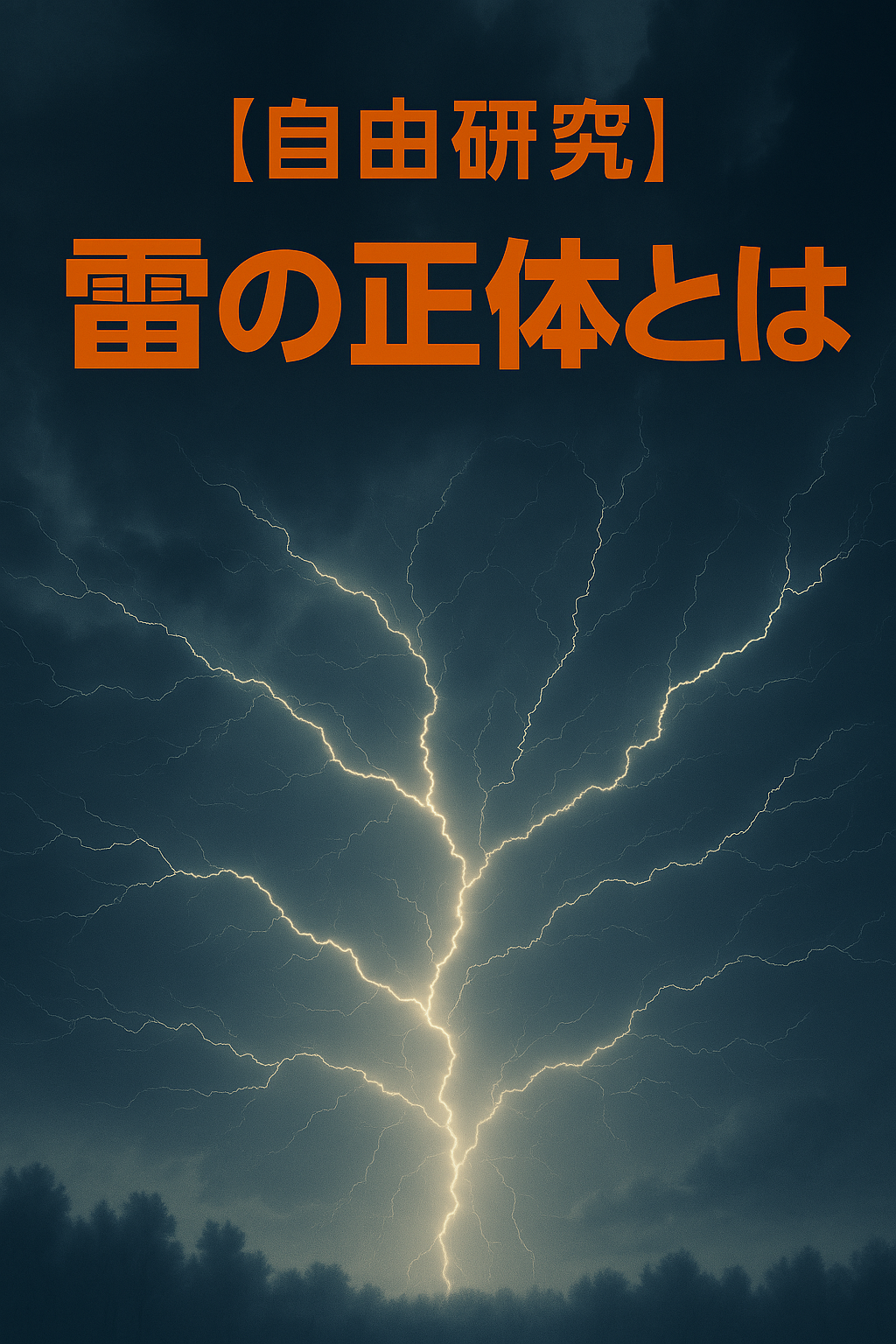
雷のひみつ(前編)〜空からのドカーンの正体をさぐろう〜
tekowaです。
夏の午後、空がにわかに暗くなり、ゴロゴロ……と音がしてきたかと思うと、ピカッと光ってドーンと大きな音が響く。「雷(かみなり)」です。
この音と光に、びっくりしたことがある人も多いかもしれません。でも、雷はただ「こわい」だけじゃないんです。実は、自然の力がつくり出す、ふしぎがいっぱいの現象なんですよ。
今回は、そんな雷について、小学生にもわかりやすく「前編」として基本のしくみを紹介します。おうちや学校でできる自由研究にもピッタリですよ♪
雷って、なにが起こってるの?
雷は「雲の中」や「雲と地面のあいだ」に電気が走ることで起こります。とつぜん空に光が走るのは、この電気のスパークなんです。
空にある「入道雲(にゅうどうぐも)」は、夏の暑い日にできやすいもくもくした大きな雲。正式には「積乱雲(せきらんうん)」といいます。雷はこの雲の中で起こることが多いんです。
どうやって電気ができるの?
積乱雲の中では、氷のつぶ(氷晶やあられ)が上へ下へとぶつかり合っています。このぶつかり合いの中で、電気がたまっていき、やがて一気に流れ出す瞬間――それが「雷」なんです。
電気がいきなり流れるとき、空気が一気に加熱されて、光(ピカッ)と音(ゴロゴロ)になります。
雷が光ってから音がするのはなぜ?
「ピカッ!」と光ってから、ちょっとして「ゴロゴロ」と聞こえるのは不思議ですよね。これは、光と音の速さがちがうからなんです。
- 光の速さはとても速くて、ほぼすぐに届きます。
- 音の速さは1秒間に約340メートル。だから、遠くの雷だと聞こえるまでに時間がかかるんです。
この時間差を使えば、雷までの距離を計算することもできるんですよ!
かんたん計算方法
- 光ったら、心の中で「1、2、3…」と数えます。
- ゴロゴロが聞こえたら、その数を3倍します。
たとえば「6」まで数えてから音がしたなら、6×340=約2,040メートル、つまり約2kmくらい離れた場所で雷が落ちたとわかるんです!
雷が落ちると、なにが起こる?
雷が地面に落ちることを「落雷(らくらい)」といいます。とても強い電気なので、木がこげたり、電線が切れたりすることもあります。
人や建物に当たると危険なので、雷が近くに来たときは安全な場所に避難することがとても大切です。
雷はどうやってできるの?もう一度まとめよう!
- あつい日に積乱雲ができる
- 雲の中で氷がぶつかって電気がたまる
- 電気が流れると光(ピカッ)と音(ゴロゴロ)になる
- 光と音の時間差で雷の距離がわかる
雷の観察ってどうやるの?
雷が近づいてきたら、安全な屋内から観察してみましょう。
観察するときのポイント
- 光ってから音が聞こえるまでの時間を数える
- 雷の数や、どの方向で光ったかをメモする
- 雷の前後で、雲の様子や風、温度に変化があったか記録する
記録したことをノートにまとめると、自由研究の立派な観察記録になります♪
雷の種類もいろいろ?
雷には、いくつかの種類があります。ちょっとだけ紹介しますね。
- 雲の中の雷…雲の中だけで光る
- 地面に落ちる雷…落雷とよばれます
- 水平に走る雷…空を横にビカッと走る
雷の形や音に注目して観察すると、いろんな違いが見つかっておもしろいですよ。
次回の「後編」では…?
後編では、雷がどうして発生するのか、空気のしくみや静電気との関係について、もっと深く学んでいきます。
さらに、安全に「雷のミニ実験」をするアイデアや、雷と昔話、ことわざなどの文化面も紹介します。
「なんで空は光るの?」「どうして金属に雷が落ちやすいの?」そんなギモンも解決していくよ!
まとめ
- 雷は、雲の中で電気がたまって流れたときに起こる
- 光と音の速さのちがいで、雷の距離がわかる
- 雷は自然の力を教えてくれる先生のような存在
ちょっぴりこわいけど、とてもふしぎで面白い「雷の世界」。
次の「後編」もお楽しみにね!
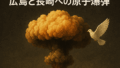
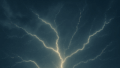
コメント