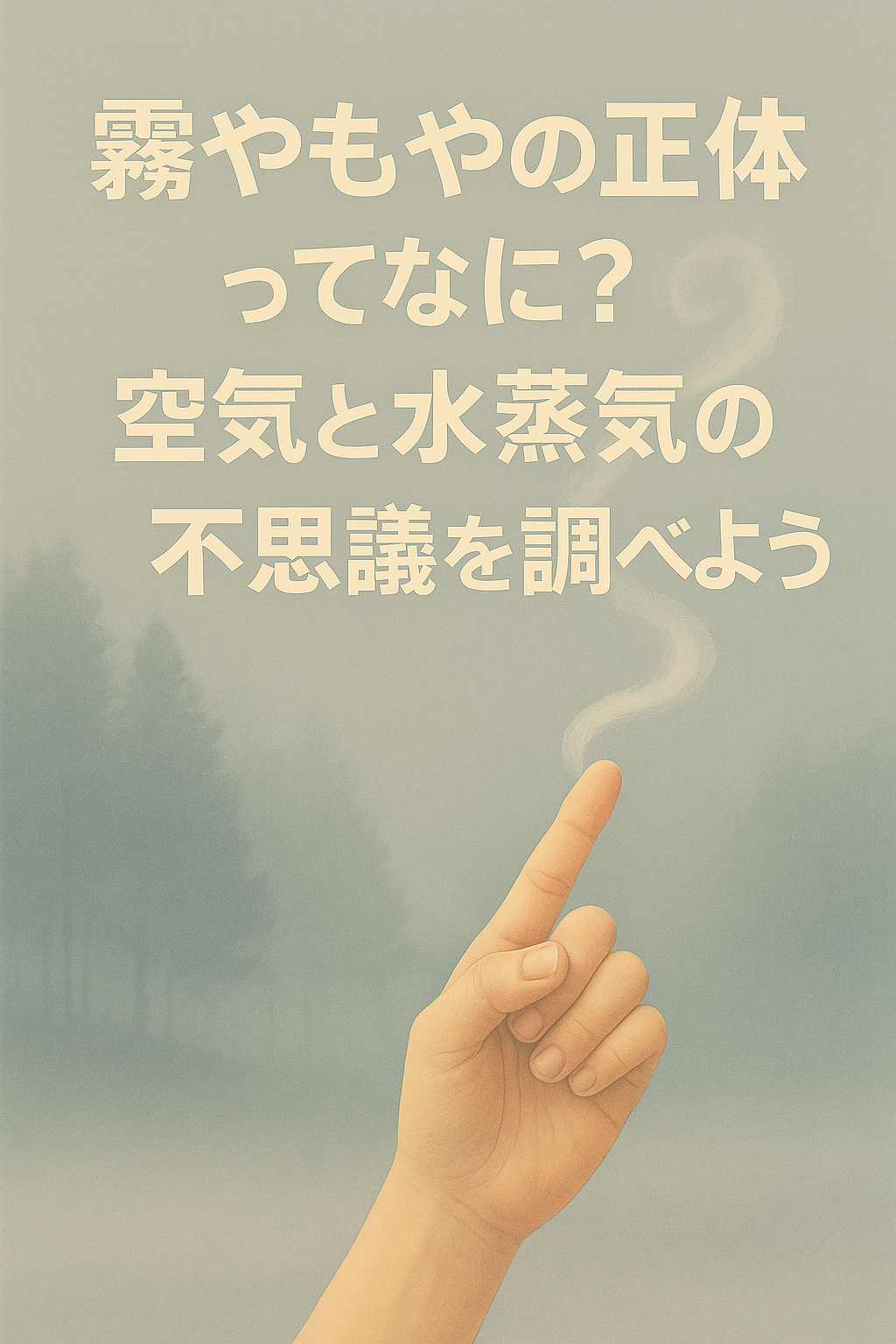
tekowaです。
前編では、ペットボトルの中に霧をつくる実験を通して、空気中の水蒸気が冷えると「水」になって白く見えることを学びました。
後編では、外の自然や室内での観察を通して、気温や湿度、環境のちがいによって霧・もや・雲がどう見えるかを探っていきます。
実験2:自然の中で霧を観察してみよう
毎朝、同じ時間に外に出て、以下のような場所で霧やもやが見えるかを観察して記録します。
- 畑や草の多い場所
- 川・池・水辺のまわり
- 山の上・高原・坂の多いところ
- 建物のすきまやアスファルトの上
観察するポイント:
- 白くかすんで見えるか?
- 近くのものははっきり見えるか?
- 太陽が出るとすぐ消える?
観察記録の例
| 日付 | 場所 | 気温 | 湿度 | 霧・もやのようす |
|---|---|---|---|---|
| 7月28日 | 川のちかく | 22℃ | 90% | 白く広がる霧があり、太陽が出てすぐ消えた |
| 7月29日 | 校庭 | 28℃ | 60% | くもりだったが霧はなし |
どうして朝に霧が出やすいの?
夜のあいだに地面が冷え、朝になるとその冷たい空気にふれた水蒸気が「水」になって霧になります。
とくに、晴れた朝、風がない、前日に雨がふったなどの条件がそろうと霧が出やすいです。
雲と霧のちがいって?
- 雲:空の高いところで水蒸気が水になったもの
- 霧:地面にちかいところで水蒸気が水になったもの
どちらも「見える空気(=水のつぶ)」ですが、高さのちがいがポイント!
気象とくらしの関係
霧やもやが出ると、交通が止まったり見通しが悪くなったりします。
「濃霧注意報」などが出ると、車のライトをつけたり、学校の登校時間が変わることもあります。
自由研究としてのまとめ方
- 人工の霧と自然の霧のちがいを表にまとめる
- 気象との関係を図で整理
- 自分なりの「霧が出るしくみ」を絵や図で説明する
感想やふり返り
- 毎日観察して、自然の変化がおもしろく感じた
- 霧を「さわってみた」気分になって不思議だった
- 天気予報や気象に興味が出てきた
参考にした本・サイト
- 国立天文台の気象図鑑
- 気象庁の公式ページ
- 科学館の展示資料
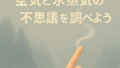
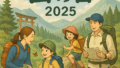
コメント