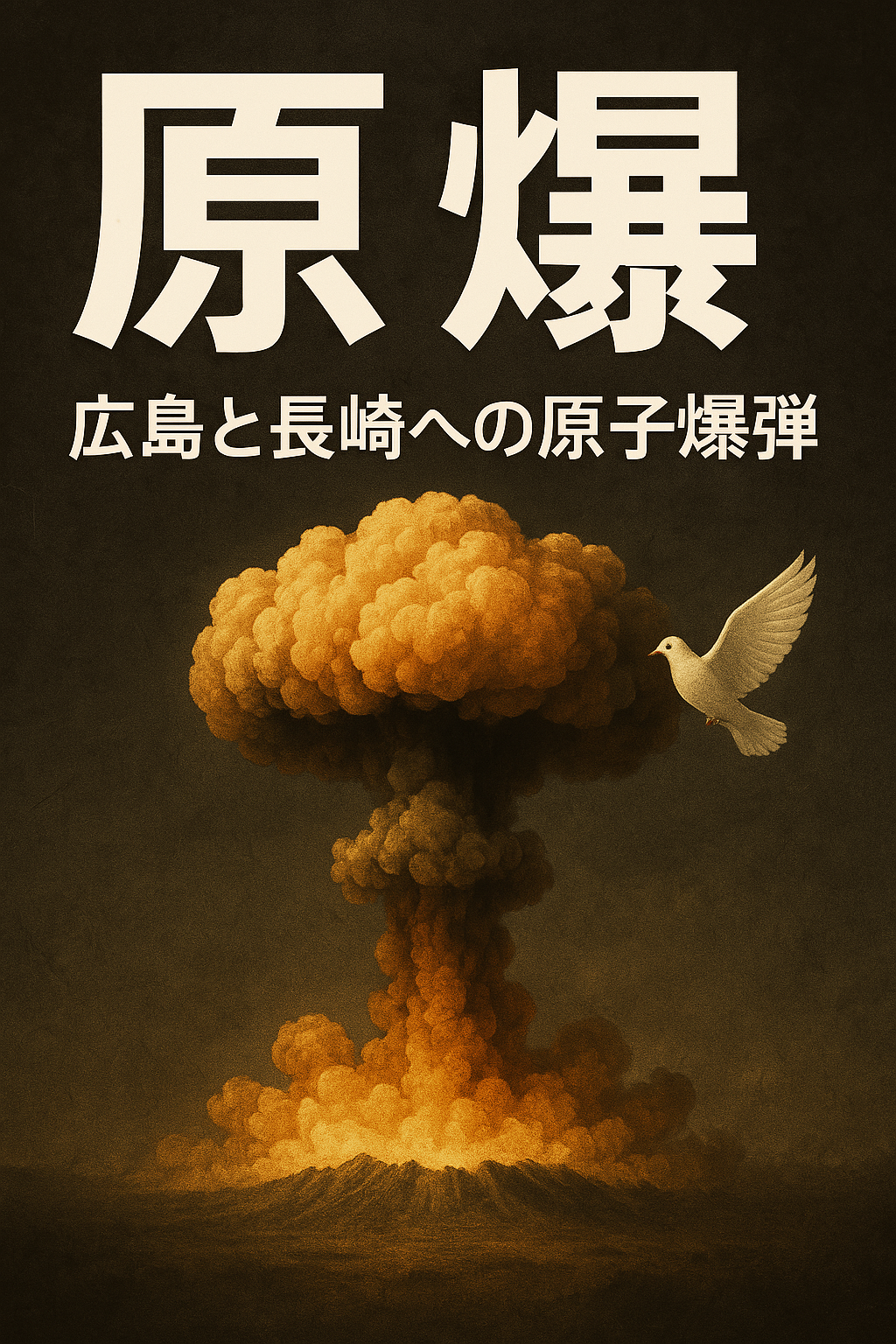
tekowaです。
戦争中、日本では食べ物がとても少なくなっていました。お米や野菜、お肉などが自由に買えなくなり、「配給(はいきゅう)」という制度で生活していたのです。
今回は、戦時中の食事と配給制度について、やさしく紹介します。
1. なぜ食べ物が足りなかったの?
戦争が続くと、食べ物を作る田んぼや畑がこわれたり、農家の人たちが兵隊に行ってしまったりして、食料が少なくなりました。
また、外国から食べ物を運ぶ船も攻撃されてしまい、輸入(ゆにゅう)もできなくなったのです。
2. 配給制度ってなに?
配給制度とは、国が「食べ物を少しずつ分ける」仕組みです。
たとえば、お米が1人につき1日200グラムまでと決められていて、それ以上はもらえませんでした。
もらえる量もだんだん少なくなり、「麦」や「イモ」、「すいとん」などが主食になっていきました。
3. ごはんはどんなものだったの?
白いごはんを食べることはとてもめずらしく、雑炊(ぞうすい)やすいとん、イモがゆなどでおなかを満たしていました。
おかずも少なく、たくあんやみそを少しだけ。ぜいたくは禁止されていたため、お菓子などはほとんどありませんでした。
4. お母さんたちの工夫
少ない材料でおいしく作るために、お母さんたちはたくさん工夫をしていました。
・大根の葉っぱまで使う
・イモの皮もゆでて食べる
・すいとんに野菜を入れてボリュームアップ
「もったいない精神」が大切にされていました。
5. 食べることの大切さ
戦争中は「食べること」がとても大変で、空腹で倒れてしまう人もいました。
だからこそ、今のように毎日食事ができることが、どれほどありがたいかを知るきっかけになります。
6. 今の給食とはちがう?
戦後すぐに学校給食が始まりましたが、戦時中はもちろんありませんでした。
家からおにぎりを持って行ったり、食べずに帰る日もあったそうです。
7. まとめ|食事は命をつなぐ力
戦時中の人々は、少ない食料の中でも知恵と努力で生き抜きました。
毎日のごはんに感謝し、食べ物をたいせつにする心を忘れないようにしましょう。
🕊 このシリーズの他の記事も読んでみよう!
→ 第20弾「戦時中の暮らしを伝えるモノや場所とは?」へつづく
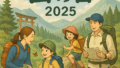
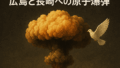
コメント