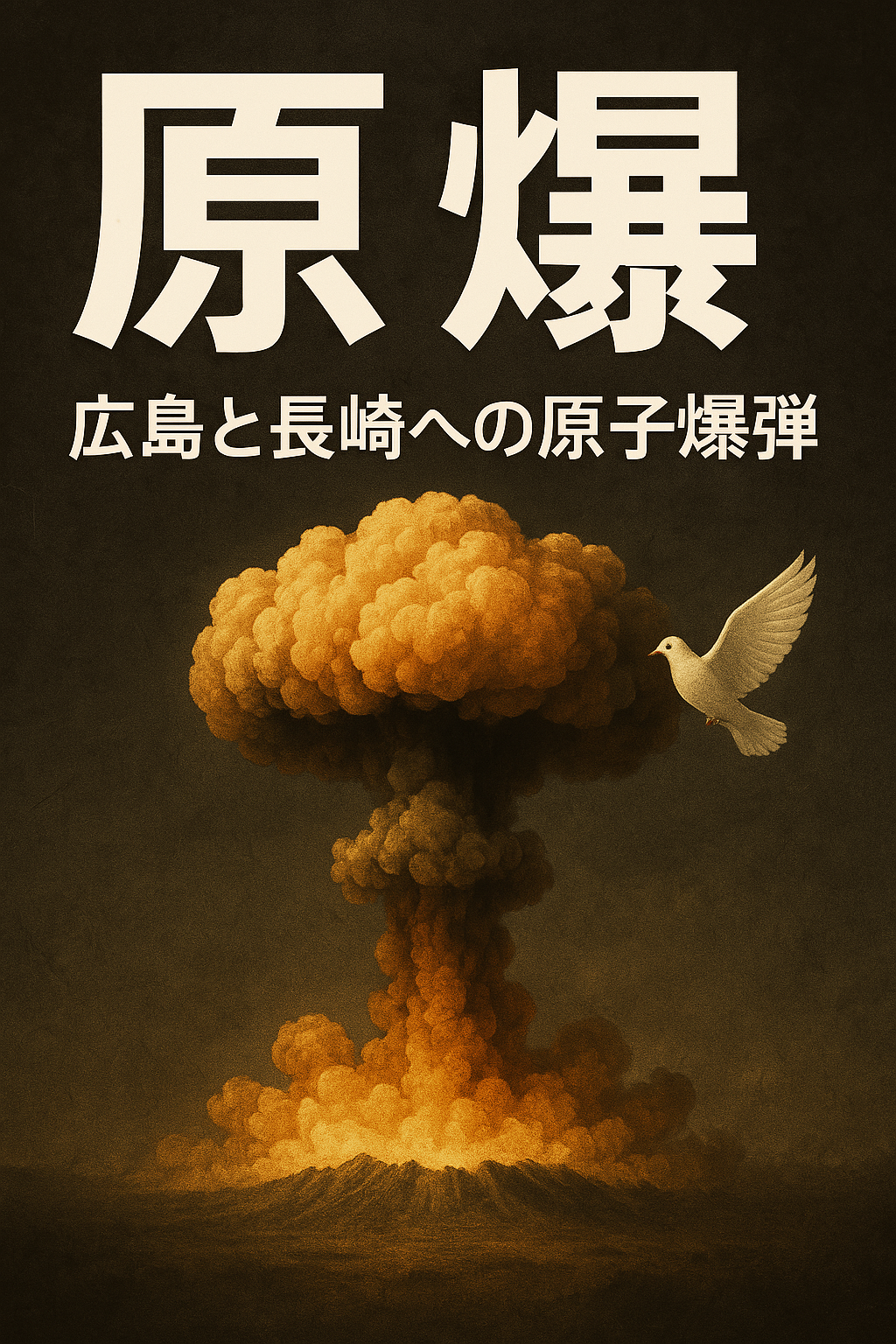
tekowaです。
戦時中の食事とは?代用食・配給制度・工夫された食べものをわかりやすく解説
今ではコンビニやスーパーでかんたんにごはんが手に入りますが、戦争中の日本では、食べものがとても少なくなり、毎日のごはんも大変なものでした。今回は、戦時中の「食事」についてやさしく紹介します。
1. 戦時中は食べものが足りなかった
戦争がつづくと、海外から食べものを運んでくる船が沈められたり、農家の人が戦地に行ってしまったりして、作物も少なくなりました。食料(しょくりょう)がたりなくなったため、人びとはとても苦労しました。
2. 配給制度ってなに?
食べものが少なくなったことで、「配給制度(はいきゅうせいど)」が始まりました。これは、国が人びとに食べものを決められた量だけ分けるしくみです。
お米やパン、さとう、しょうゆなど、決められたものを「もらいに行く」か「引きかえに行く」生活が続きました。
3. 代用食(だいようしょく)って?
配給で足りない分は、「代用食(だいようしょく)」でまかなっていました。代用食とは、本物の食材のかわりになるものです。
- 米のかわりに:大根・さつまいも・くず米
- 砂糖のかわりに:甘いイモやシロップ
- しょうゆのかわりに:うすめたみそ汁
- お肉のかわりに:大豆や豆腐
「ごはん」といっても、ほとんどが野菜だったり、味も薄くてボソボソしていたりと、おいしいものではなかったそうです。
4. 料理の工夫とアイデア
お母さんや給食のおばさんたちは、少ない材料でもおなかをふくらませる工夫をたくさんしました。
- くず野菜でスープをつくる
- カボチャや豆を使って甘みを出す
- おからやふすま(小麦の皮)を使ってパンを作る
戦争中は「ぜいたくは敵だ」という言葉もあり、楽しい食事より「生きのびるためのごはん」が大事にされていました。
5. 子どものごはんはどうだった?
学校では「戦時中の給食」がありましたが、それも食べられない日がありました。多くの子どもたちは、自分のお弁当箱にわずかなおにぎりやイモだけを入れて通っていたそうです。
ある日は、にんじんの葉っぱ入りおにぎり。ある日は、大根の切れっぱしの味噌汁。そんな日々が続いていました。
6. 食べることのありがたさ
今、私たちはいろいろな食べものをすきなだけ選ぶことができます。でも、戦時中の人びとは「食べること」じたいが大変だったのです。
そのつらい体験があるからこそ、今の「食べられるありがたさ」を感じることができます。
7. まとめ|食事から平和を考える
食べものは、命をつなぐ大切なものです。戦争で食べられない日がある、家族に分けられない、そんな時代があったことを知ることで、今の平和な食卓がどれほど貴重かがわかります。
「いただきます」「ごちそうさま」は、そうした思いもこめて言いたいですね。
🕊 このシリーズの他の記事も読んでみよう!
→ 第8弾「原爆ドームとは?世界遺産が語る平和の願い」へつづく
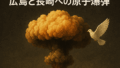
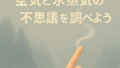
コメント