
tekowaです。
毎年8月11日は「山の日」。2016年から新たに加わった国民の祝日です。しかし、「山の日って何をする日?」「なぜ8月11日なの?」と思う人も多いのではないでしょうか。 この記事では、山の日が制定された背景や由来、その意味や狙いをわかりやすく解説します。
山の日の目的とは?
「山の日」は、国民の祝日に関する法律(祝日法)によって次のように定められています。
「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」
つまり、山の自然に触れ、山から得られる恵みに感謝しようという日なのです。これまで海の日はありましたが、「山の日」がなかったため、山岳関係者や地方自治体などが中心となって制定運動が進められました。
山の日はいつから始まった?
山の日は、2014年(平成26年)5月に法律が可決され、2016年(平成28年)から施行されました。初めての「山の日」は2016年8月11日です。
なぜ8月11日かというと、以下のような理由があります:
- お盆休みに近く、山に出かけやすい
- 「八(やま)」と「十一(木が立っているように見える)」という語呂合わせ
- 長野県など山岳観光地の希望も反映
実は当初、「6月第1週」や「海の日の翌日」なども候補に挙がっていましたが、結果的に8月11日に落ち着きました。
山の日ができた背景
山の日が誕生した背景には、次のような動きがあります:
- 2002年:日本山岳会が「山の日」制定を提案
- 2010年:全国山の日協議会が設立
- 2013年:日本山岳会などのロビー活動が活発化
- 2014年:祝日法改正が国会で可決
特に「全国山の日協議会」には、全国の自治体や観光団体、登山団体などが参加し、山文化の普及や自然教育の観点から祝日の意義を訴え続けてきました。
他の祝日とどう違うの?
例えば「海の日」は「海の恩恵に感謝し、海洋国家日本の繁栄を願う」日です。同じく「山の日」も自然への感謝を目的としていますが、より「親しむ」「触れる」ことが重視されています。
登山やハイキング、山菜採り、森林浴など、実際に自然に足を運ぶことが推奨されているのも特徴です。また、地元の山に感謝を伝えるイベントも各地で行われています。
日本人にとって「山」とは?
日本は国土の約7割が山地。古来より山は「神が宿る場所」「自然と人間の境界」とされ、信仰や文化の中に溶け込んできました。
たとえば:
- 修験道の修行場(熊野・大峰山など)
- 富士山や白山など、霊峰としての信仰
- 山の幸を供える秋の収穫祭
「山の日」は、こうした山にまつわる文化や自然の大切さを再確認する機会でもあるのです。
世界にも「山の日」はある?
世界的には、国連が定めた「国際山岳デー(International Mountain Day)」が12月11日にあります。これは持続可能な山岳開発や自然保護を促進する国際デーで、2003年にスタートしました。
日本の山の日とは趣旨が少し異なりますが、「山に意識を向けよう」という点では共通しています。
まとめ:山の日をもっと楽しもう!
「山の日」は単なる祝日ではなく、私たちの暮らしと深く関わってきた「山」に目を向ける大切な日です。
- 自然の恵みに感謝する
- 山の文化や歴史を知る
- 登山やハイキングで自然に触れる
そんな1日にしてみてはいかがでしょうか? お子さんと一緒に近くの里山へ出かけてみるのもおすすめですよ。
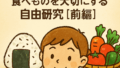
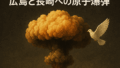
コメント