
🌟どうして夏になると浴衣や甚平を着るの?
tekowaです。
夏まつり、花火大会、七夕、盆踊り…
「夏」と聞いて思い浮かぶ風景の中には、浴衣や甚平を着ている人の姿がありますよね。
でも、ふと疑問に思いませんか?
「なんで夏だけ浴衣や甚平を着るの?」
「どうして昔から着続けられているの?」
この自由研究では、そんな“夏のふく”の不思議な定番の理由を、歴史・文化・生活の知恵から調べていきます!
🏯浴衣のはじまりは“お風呂用”だった!?
今では「おしゃれな夏の着物」になっている浴衣。
そのルーツは、なんと平安時代の貴族が蒸し風呂に入るときに着ていた「湯帷子(ゆかたびら)」です。
- 「帷子(かたびら)」=裏地のない薄い着物
- 「湯帷子」=湯(蒸し風呂)に入る時の服
つまり、浴衣は最初「お風呂専用の肌着」のようなものでした。
🧺江戸時代、庶民のあいだに広がった「木綿の浴衣」
江戸時代になると、木綿の普及とともに浴衣は庶民にも広がりました。
湯上がりに着るだけでなく、花火や盆踊りといった夏の行事にも着られるようになったのです。
- 動きやすくて乾きやすい → 夏の普段着に!
- 涼しい素材&派手な柄 → 夏の“おしゃれ勝負服”に!
🉐浴衣の名前の由来は?
浴衣という言葉は「浴びる衣(きもの)」と書きますが、元の言葉は「湯帷子(ゆかたびら)」です。
これが略されて「ゆかた」と呼ばれるようになり、漢字だけが「浴衣」に変化したと考えられています。
つまり、読み方は昔のままで、字だけが現代的に変化した“あて字”なんですね。
👘甚平のはじまりは「作務衣」だった!
甚平のルーツは、お寺の作業着である「作務衣(さむえ)」。
それをもっと軽くて涼しく、動きやすいように改良したのが、今の甚平です。
特に子ども向けには、上下セパレートでトイレも行きやすく、動き回る夏にぴったりな服として人気があります。
🧵甚平の名前の由来は?
「甚平」という名前の由来には諸説ありますが、有名なのは「ある仕立て職人の“甚平さん”が考案したから」という説。
もともとは「甚平さんの服」と呼ばれていたものが、そのまま名前になったのでは?と言われています。
はっきりした記録はありませんが、和の名前としても親しみやすく、広く使われるようになったと考えられています。
🎆なぜ夏に着るの?「行事」とのつながり
浴衣や甚平は、次のような「夏限定」の行事と相性バツグンなんです。
- 🎋七夕:夜の行事。風通しの良い服が快適
- 🎆花火大会:軽くて涼しい浴衣が人気
- 🪭盆踊り:踊りやすい甚平で参加!
- 👦保育園・学校行事:子どもは甚平、大人は浴衣が定番
📝まとめ:浴衣と甚平が“夏のふく”になった理由
| 要因 | 内容 |
|---|---|
| 🏛️ 歴史 | 貴族の湯帷子 → 江戸の庶民 → 現代の行事着へ |
| 🌬️ 機能性 | 通気性・速乾性バツグンの綿や麻が主素材 |
| 🎋 文化 | 七夕・花火・盆踊りなど“夏限定イベント”と結びついて普及 |
🔗続きはこちら!
- ✅【第2回】浴衣と甚平はどうして涼しい?素材と形に隠れた夏の工夫とは?
- ✅【第3回】浴衣vsTシャツどっちが涼しい?実験でくらべてみた!
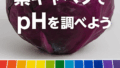
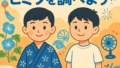
コメント