
11月1日の「計量記念日」は、大人だけでなく子どもにとっても大切な学びの日です。
「はかる」という行為には、数字を知ること・比べること・順序を考えることなど、子どもの発達に欠かせない要素がたくさん詰まっています。
整活の視点から見ても、“はかる”は心と体と暮らしを整える基礎。今回は、家庭や保育園でできる「はかる遊び」を通して、子どもの“数字の力”を育てる方法を紹介します。
◆ 「はかる」はすべての学びの原点
子どもたちが最初に出会う“数”は、「1つ、2つ、3つ…」という数唱。でもその先には「どちらが重い?」「どっちが長い?」「どれだけ多い?」という“量”の感覚が広がっています。
この“量感”を育てるのが、計量遊び。実際に手を動かして、触って、比べて、感じることで、数字が生きたものになります。
単なる算数ではなく、五感で覚える“整う感覚”。これが、のちの論理的思考や自己調整力へと繋がっていくのです。
◆ 1. スプーンで砂糖・塩をすくう実験
透明なコップに砂糖と塩を用意し、スプーンですくって別の容器に移すだけの簡単な遊び。
「同じスプーン1杯なのに、どっちが重い?」と聞いてあげると、子どもは目と手で違いを感じ取ります。
重さを感じたあとに「じゃあ、どうして違うんだろう?」と考えさせると、自然に科学的思考が芽生えます。
保育園ではこの体験を通じて、「同じ量でも種類によって重さが違う」ことを学び、のちに“密度”の概念へと繋げていきます。
◆ 2. 水のメモリ遊び
計量カップやペットボトルを使って、「100mlまで入れてみよう」「200mlと300ml、どっちが多い?」とクイズ形式で遊ぶのもおすすめ。
メモリを目で追うことで、数字と量の対応関係を自然に覚えます。
さらに、食紅を使って水に色をつけると視覚的にわかりやすく、飽きずに続けられます。
これも整活的に言えば“視覚から整える遊び”。目で見て、心で感じることで、数字が感覚として定着していくのです。
◆ 3. 「重さくらべ」ゲーム
同じ形のカップに異なる素材を入れて重さを比べる遊び。例えば、ビー玉・お米・綿・お菓子などを同じ量ずつカップに入れて、「どれが重い?」「なぜ?」と考えます。
重さの違いを体感するうちに、「形や大きさが同じでも重さは違う」という感覚を掴みます。
これは、後の理科や算数の基礎となる重要な感覚。体験の積み重ねが「わかる子ども」を育てます。
◆ 4. 体を使った“はかる”あそび
はかるのは道具だけではありません。
「廊下の長さは何歩?」「積み木10個分の長さはどれくらい?」など、体を使った計測遊びも人気です。
体の動きを通じて“長さ・距離・リズム”を感じ取ることは、運動神経と同時に空間認知能力を育てます。
また、みんなで「10歩歩いたら止まる」などのルールを作ると、社会性や協調性の学びにも繋がります。
◆ 5. おままごとで“はかる”を日常化
おままごとは、最も自然な“はかる遊び”の場です。
「スプーン3杯の砂糖」「カップ半分のミルク」などの言葉を使うことで、遊びながら数字に触れます。
保育園では、この遊びの中に“食育”を組み込みます。たとえば、「お味噌はしょっぱいから、少しだけ」「お砂糖は甘いけど入れすぎると虫歯になる」と話しながら量の調整を学ばせます。
こうした体験は、後に“自分で味を整える力=整食力”に変わっていくのです。
◆ 「はかる=整う」子どもの心の変化
計量遊びは、数字だけでなく“気持ち”を整える効果もあります。
たとえば、順番にスプーンを使う・メモリをきちんと見る・こぼさないように注ぐ——これらの動作は、集中力や自己調整力を育てます。
「丁寧にやると上手くいく」「落ち着くと失敗しない」という成功体験が、子どもの心を穏やかに整えてくれるのです。
◆ 家庭でできる整活式“はかる体験”5選
- ① ごはん茶碗の重さを測ってみる(空の状態と盛った状態の違い)
- ② ペットボトルの水を家族で飲んで「誰がどれだけ飲んだか」予想→実測
- ③ おやつのグラムを測って1日分の目安を作る
- ④ お風呂の水位を見て「今日はどこまで入ってる?」と観察
- ⑤ お米を炊くとき、計量カップで正確に1合を量って炊き比べ
どれも「特別な準備なし」でできる遊びです。
“正確に量る”という行為を遊びに変えることで、親も子も楽しく学べます。
◆ 整活設計士の視点から
整活式の食育では、「感覚×数字×心の整え」を一体として捉えます。
子どもが「はかる」を通して得るのは、単なる知識ではなく、
- 正確に見る力
- 自分で調整する力
- 相手を思いやる力
この3つ。数字を扱うことは、思いやりのトレーニングでもあります。
「みんなで同じ量を分ける」「少しずつ注ぐ」といった行動には、相手を尊重する心が自然に育つのです。
◆ 保育園・学校・家庭がつながる「はかる文化」
保育園での経験が家庭に、家庭での経験が学校に繋がっていく。
この“教育の連鎖”の中心にあるのが「はかる文化」です。
たとえば、保育園でメモリを読めるようになった子が、小学校で算数にスムーズに入っていく。
また、家庭で料理を手伝う経験があれば、家庭科や理科でも“理解が速い子”になります。
整活的にはこれを「暮らしの中のSTEM教育」と呼びます。
◆ まとめ:はかる子は、考える子に育つ
“はかる”という行為は、子どもにとって「考える力を育てる遊び」。
数値を比べ、手で感じ、目で確かめ、心で納得する。
それは整活そのものです。
数字を通して世界を理解できるようになると、自己肯定感や達成感も自然と高まります。
「できた!」という小さな成功を積み重ねることが、将来の学びの土台を作るのです。
次回⑤では、「“はかる”を通して知る環境とSDGs」をテーマに、資源・水・電気など、地球を“整える”ための計量の視点を紹介します。
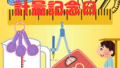
コメント