
毎年11月1日は「計量記念日」。この日は、1959年(昭和34年)に新しい計量法が施行されたことを記念して、当時の通商産業省(現在の経済産業省)が制定しました。意外と知られていませんが、私たちの生活の中には「はかる」ことがあふれています。食べ物、体の状態、時間、お金、エネルギー——どれも“正確に測る”ことで初めて安心して暮らせるのです。
◆ 計量法ってなに?
「計量法」は、社会全体で共通の“ものさし”を持つためのルールです。もし、1メートルや1キログラムの基準が人や地域によって違ったらどうなるでしょうか。お店で買う100gの肉が実際は80gしかなかったり、病院の点滴量がずれてしまったり。そんな世界では安心して暮らせません。だからこそ、日本では「国家標準」を定め、計量器(はかり・温度計・メーターなど)が正しく使われるように管理されています。
◆ “はかる”は信頼の基礎
計量とは、単なる数字の操作ではなく「信頼を形にすること」。お店とお客さん、医療者と患者、料理を作る人と食べる人——すべての間に「正確に量る」ことで生まれる安心があります。たとえばお米屋さんが1合きっちり量って渡すのも、調剤薬局が処方量を慎重に計るのも、すべてその信頼を守るためです。
◆ 栄養士から見た“はかる”の重要性
栄養士として働くと、「はかる」という行為がどれほど人の健康を左右するかを痛感します。たとえば、スプーン1杯の塩——目分量で振るのと、きっちり量って入れるのでは、1食で1〜2gの差が出ることも。1日3食、1年間続けば、塩分摂取量は1000g以上変わります。つまり、計量とは健康寿命を延ばす小さな習慣なのです。
また、糖尿病患者の食事指導では「1単位=80kcal」を基本に食品をグループ分けして管理します。これも“はかる文化”の一部。整活式献立づくりでも、PFCバランスを整える際に欠かせないのが正確な計量です。
◆ 保育園の現場では?
保育園では「はかる」ことを通して子どもたちが数や量の感覚を育てます。たとえばおままごと遊びの中で「スプーン3杯でジュースいっぱい!」「お砂糖をひとさじ!」というやりとりが生まれます。これが初めての“計量体験”。
遊びながら感覚を磨き、やがて「はかる=正確に伝える」という社会的スキルに繋がっていきます。
給食室でも同じです。調味料を量る、切る大きさをそろえる、盛り付けの量を統一する——これらはすべて“安全でおいしい給食”を作るための計量文化。保育の世界では、数字の裏に“愛情と責任”があります。
◆ 介護の現場では“はかる”が命を守る
介護福祉士としての現場では、体重・血圧・体温・食事量・尿量などを日々測定します。これを怠ると、体調変化を見逃す危険があるため、計量は命を守る行為です。
たとえば、前日より体重が2kg増えていれば心不全のサイン、食事量が半分に減っていれば誤嚥の前兆かもしれません。1g・1mL単位の記録が、健康管理の基盤になります。
◆ 世界でも「はかる」は平和の象徴
毎年5月20日は「世界計量記念日(World Metrology Day)」ですが、日本の11月1日はそれに呼応する形。世界共通の単位を使うことで、国際取引や研究がスムーズに行われます。つまり、正確に“はかる”という行為は、国境を越えた平和の約束でもあるのです。
◆ 家庭でも“はかる整活”を
家庭でもできる「整活式はかる習慣」はとてもシンプルです。
- 毎朝、体重・体脂肪・水分量を測る
- 料理は目分量ではなく、一度スケールで確認してみる
- 塩分計や糖度計を使って味を数値化してみる
- 子どもと一緒におやつを作りながら「何グラムかな?」と話す
これらの行動を通じて、“感覚”だけに頼らない暮らしが身につきます。特に女性はホルモン周期やライフステージによって体調が変化するため、定期的な測定で自分を整えることが大切です。
◆ 「感覚」も「数字」も、両方大事
とはいえ、数字に縛られすぎるとストレスになります。計量記念日は、「数字を味方にする」ための日。数値を眺めて反省するのではなく、「あ、少し疲れてたんだな」「塩分が多かったな」と気づくきっかけにすればいいのです。
◆ 子どもに伝えたい“はかる心”
「はかる」という行為は、相手を思いやる気持ちにも繋がります。たとえば「おかずを均等に分ける」「お友達と半分こする」も一種の計量。そこには“公正”と“共有”の心が育ちます。
子どもたちが将来、数字を通じて思いやりを持てる大人になるよう、保育現場でも“はかる文化”を大切にしたいものです。
◆ 整活設計士の視点から
「整える暮らし」とは、感覚と数字のバランスをとること。
食事も健康も、感情だけでは続かず、数字だけでも満たされません。
計量記念日は、そんな“整活の軸”を思い出す日。今日だけでも、キッチンのスケールを出してみたり、体重計のホコリを拭いてみたり。
数字と少し仲良くなるだけで、暮らしがぐっと整っていきます。
◆ まとめ:「はかる」は、未来を信じる行為
計量は、過去・現在・未来をつなぐ橋です。正確に測ることで、食の安全を守り、健康を維持し、経済を支え、教育や介護の現場に信頼をもたらします。
そして、誰かのために“はかる”とき、そこには必ず優しさがあります。計量記念日をきっかけに、「はかる」という言葉の奥にある“信頼”と“整活”を見直してみませんか?
次回は②「健康を守る“はかる習慣”」として、体重・血圧・食事量など、日々の整活チェックポイントを紹介します。
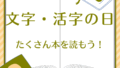
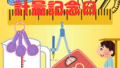
コメント