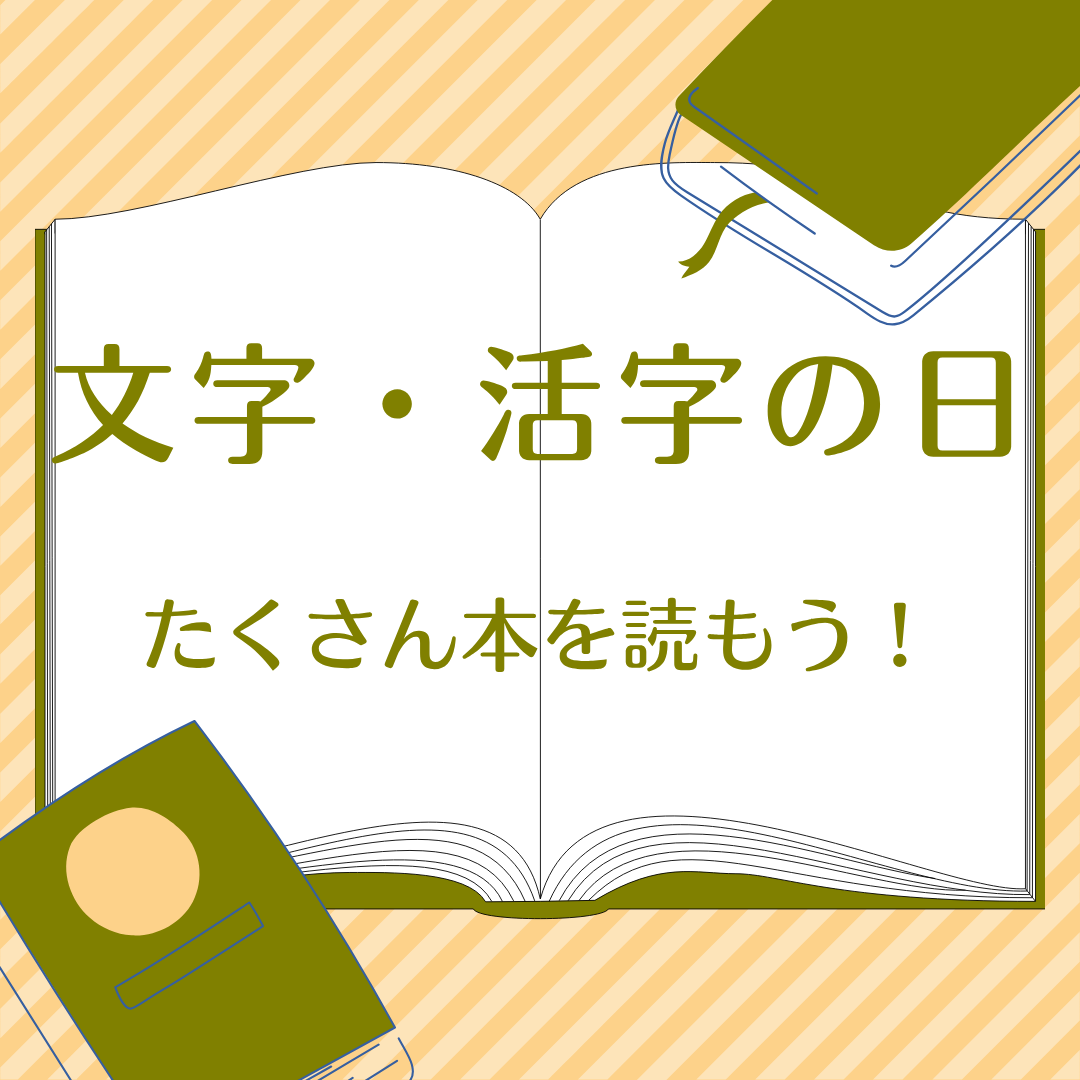
tekowaです。
10月27日は「文字・活字文化の日」。 本を読む時間が減っている今だからこそ、改めて「読む力」と「書く力」の関係を見直すことが大切です。 言葉は、私たちが考え、感じ、伝えるための基本的な道具。 その力を育てるために欠かせないのが、“読む習慣”なのです。
このテーマは、保育・教育・栄養・福祉など、どの分野でも共通しています。 読む力が育つと、考える力、伝える力、表現する力――つまり“書く力”が自然と整っていくのです。
1. 読む力が「思考の素材」を増やす
人は、頭の中にある「言葉のストック」で考えます。 たとえば、“楽しい”“きれい”“悲しい”といった言葉しか知らなければ、 感情を表す幅もその範囲にとどまってしまいます。 しかし、読書を通して多様な表現に触れると、心の中の辞書がどんどん豊かになります。
この「言葉の貯金」が、思考の深さを決めるのです。 文章を書くときに「どう表現しようかな」と悩む人は、 まだ“材料”が少ないだけ。 読むことで材料が増え、自然と書けるようになります。
つまり、「読む力」は“思考のインプット”。 「書く力」は“アウトプット”。 両者は一方通行ではなく、呼吸のようにセットで育ちます。
2. 読書が「構成力」を育てる
良い文章には、必ず「流れ」と「リズム」があります。 それを身につける最も自然な方法が、「読むこと」。 本を読むとき、私たちは無意識のうちに構成を学んでいます。
たとえば、物語の起承転結。 説明文の「結論→理由→具体例」の順番。 対話文の間の取り方。 これらはすべて、読む経験を通じて体に染み込んでいきます。
文章をうまく書けない子どもに「もっと考えて」と言うよりも、 良い文章を“読む機会”を増やすほうが効果的。 読むうちに、無意識に“書き方の型”が身につくのです。
3. 読む力が「感情表現の幅」を広げる
物語の登場人物の気持ちを想像したり、詩の一節に共感したり―― 読書は、他人の感情を自分の中に取り込む経験でもあります。 その体験が、文章を書くときの“表現の深さ”につながります。
「楽しい」だけでなく、「胸がふくらむようにうれしい」 「悲しい」だけでなく、「息が詰まるような切なさ」 言葉のバリエーションを知ることで、気持ちをより繊細に描けるようになります。
特に子どもにとって、感情の語彙を増やすことは自己表現の第一歩。 読書で言葉を知ることが、結果的に“自分を伝える力”を育てます。
4. 書く力を育てる読書の実践法
読むだけで終わらせず、「読んだあとどう感じたか」を言葉にする習慣が大切です。 ここでは、家庭でできる3つの簡単な実践方法を紹介します。
① 読んだ本の一文を書き写す
気になった一節をノートに書く。 それだけで、語彙や構成の感覚が自然に身につきます。 子どもなら「好きなセリフを選んで書こう!」でもOK。
② 感想を一言でまとめる
「どんな気持ちになった?」を一言で表現する練習。 書く量よりも、「どう言葉を選ぶか」が大事です。 短い感想でも、自分の感情を表す言葉を探すことが目的。
③ 家族で“感想の共有時間”を作る
お風呂上がりや寝る前に、「今日は何読んだ?」と聞くだけでもOK。 聞かれることで思考が整理され、話す→書くへの流れができていきます。
5. 読むことは「思考の筋トレ」になる
文章を書く力は、思考の深さに比例します。 読むことで「考える力」を鍛えることが、 最終的に“自分の言葉で書ける人”になる近道です。
保育や教育の現場でも、読書量と作文力の関係は明らかです。 たくさん読んでいる子は、文のつながりが自然で、 自分の考えを筋道立てて書くのが上手。 それは、読書によって「文の流れ」や「思考の順番」を体得しているからです。
書くことが苦手な子に必要なのは、才能ではなく“読む時間”。 読むことが、言葉の基礎体力を作ります。
6. 読む×書くは“自己理解”につながる
読んで書くことは、他人の世界を通して自分を知る作業でもあります。 本の中の登場人物に自分を重ねたり、感想を書くことで気づいたり。 「私はこう感じるんだ」と知ることが、心の整理につながります。
福祉の現場でも、文章を書くことで気持ちが整う例は多くあります。 “書く療法”と呼ばれるように、言葉にすることは感情のセルフケアです。 そのベースになるのが「読む習慣」。 読むことで、感情に名前をつける力が育ちます。
7. 読む力が未来をつくる
AIが文章を自動生成する時代になっても、 「読む力」と「書く力」は人間の本質的なスキルとして残ります。 AIが“書く”世界だからこそ、 人間は“読む”ことで、内容を理解し、意味を見つけ、考える必要があるのです。
つまり、読む力は“判断力”。 書く力は“表現力”。 どちらも、社会を生きるための基本的な“生きる力”です。
家庭で読書の時間を作ることは、 ただの学習習慣ではなく、“生き方の教育”でもあります。
8. まとめ|読む力で整う、書く力で広がる
読むことは、心を整え、思考を育てる行為。 書くことは、それを外に広げる行為。 読む×書くを繰り返すうちに、 言葉が整い、自分の世界が少しずつ広がっていきます。
読書量が減っている今こそ、 家庭や教育現場で「読む時間」を取り戻すことが、 次の世代の“書く力”を守る第一歩。 1日10分でもいい、本を開いてみましょう。 その10分が、未来のあなたや子どもの言葉の力を育ててくれます。
読む力は、書く力の土台。 そして、書く力は、人を動かす力。 文字・活字文化の日に、改めて“読む”という行為を丁寧に見つめてみませんか。
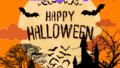
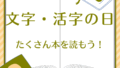
コメント