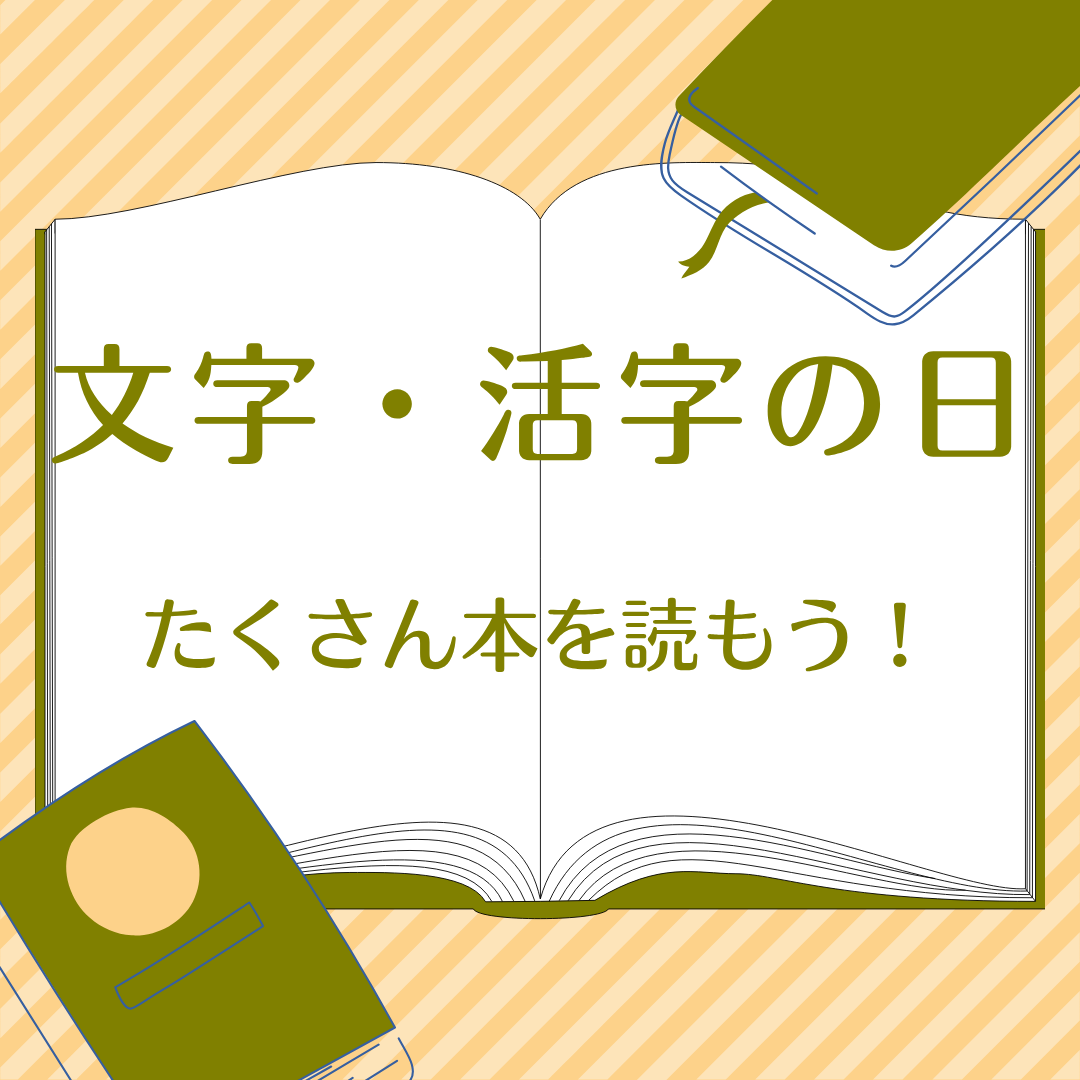
tekowaです。
10月27日は「文字・活字文化の日」。 この日をきっかけに、今回は“高齢者と活字文化”について考えてみたいと思います。 デジタル化が進む現代でも、紙の本や新聞、手書きの文字には特別な力があります。 読むこと、書くこと、声に出すこと――そのすべてが、高齢者の心と脳を穏やかに整えてくれるのです。
私は介護福祉士として、また栄養士として高齢者と関わる中で、 「活字」が生活の質を高める場面を数多く見てきました。 活字は、単なる情報の媒体ではなく、心を動かす“命の刺激”でもあります。
1. 活字を読むことで得られる「心の安定」
活字を読む行為には、心を落ち着かせる効果があります。 新聞や小説、俳句集などをゆっくり読むことで、 日々の孤独感や不安感が和らぎ、穏やかな時間が流れます。
特に高齢者にとって大切なのは、「リズム」です。 活字を追うリズムは、呼吸を整え、集中を促します。 これは“整活”的”に言えば「心の呼吸法」。 短時間でも、毎日同じ時間に読む習慣を持つことで、生活リズム全体が整っていきます。
また、読書中は記憶や感情を呼び起こすことが多く、 「昔の自分」に再会できる貴重な時間にもなります。 読むという行為が、“回想”と“癒やし”を同時に生み出すのです。
2. 読む力が「脳の活性化」につながる
活字を読むことは、認知症予防にも効果があるといわれています。 文章を理解するために、脳は視覚・言語・記憶・思考を同時に働かせます。 そのため、日常的な読書は“脳の総合運動”なのです。
実際、新聞を音読する習慣を持つ高齢者は、 そうでない人に比べて認知機能が保たれやすいという研究もあります。 「音読」は、文字を読み、声に出し、耳で聞き、意味を理解する―― この一連の動作が脳の活性化に非常に効果的なのです。
整活的にいえば、これは“脳の体操”。 ウォーキングが体を整えるように、音読は脳を整える行為なのです。
3. “書く整活”で心と手をつなぐ
読むことに加えて、「書くこと」も高齢者にとって重要な整活です。 手紙を書く、日記を書く、俳句や川柳を綴る―― これらの行為は、脳の運動と心の整理を同時に行うリハビリになります。
特におすすめなのが「回想ノート」。 昔の思い出を文字にすることで、記憶が整理され、前向きな感情が引き出されます。 「小学校の頃の遠足」「初めての就職」「子育ての思い出」など、 テーマを決めて書くと、自然と笑顔が増える方も多いです。
書く行為は、“心の再確認”。 「自分はこれまでよく頑張ってきた」と思えることが、 生きる意欲の回復につながります。
4. 食卓にも“活字の力”を取り入れる
栄養士として感じるのは、「食と文字」は意外と深く結びついているということ。 たとえば、食卓で新聞やレシピを読むことも立派な“活字整活”です。
・新聞の料理欄を見ながら「これ作ってみたいね」と会話が生まれる ・昔の給食メニューを見て「懐かしい」と笑顔がこぼれる ・食材の産地や旬の記事を読むことで、季節を感じる こうした小さな活字体験が、食卓をより豊かにしてくれます。
読むことをきっかけに人と話す。 その“交流”が、栄養と同じくらい心の健康を支えるのです。
5. 家族や介護者ができるサポート
高齢者に活字文化を楽しんでもらうためには、 “無理のないサポート”が大切です。 ここでは、家庭や施設で取り入れやすい工夫を紹介します。
① 大きな文字の本や新聞を選ぶ
視力の低下に合わせて、文字のサイズを調整することが第一歩。 最近は“シニア向け大活字本”も増えており、 好きな作家の作品を読み直す方も多いです。
② 一緒に音読する
家族やスタッフが隣でゆっくり読み上げると、 安心感が生まれます。 短い俳句や童話など、“聴く読書”から始めても十分です。
③ 書くスペースを作る
机の上にメモ帳と筆記具を置いておくだけで、 「ちょっと書いてみようかな」と思えるものです。 日付入りのノートに「今日の一言」を書くのもおすすめ。
6. 福祉現場での活字整活の実践例
私が介護施設で働いていた頃、 新聞の読み合わせを毎朝行っていました。 1人が見出しを読み上げ、皆で内容を話す。 わずか10分の活動でも、笑顔と会話が増え、 「今日も楽しかった」という言葉をよく聞きました。
また、俳句クラブや朗読会も人気があります。 自分の言葉で季節を詠むことや、他人の詩を声に出して読むことが、 “自己表現”と“共感”の両方を生み出します。
このような活動を通して感じるのは、 活字文化は“世代をつなぐ橋”になるということ。 子どもから高齢者まで、共通の話題で語り合えるのが文字の魅力です。
7. 活字整活がもたらす“生きがい”
「毎日新聞を読むのが楽しみ」「俳句を書くのが日課」 そんな習慣を持っている方は、表情が生き生きしています。 活字との関わりが、日常にリズムと目標を生み出すからです。
読む・書く・話す――この三拍子を生活の中に取り戻すことは、 加齢による衰えを“緩やかに整える”力を持っています。 それは医療や介護だけでは補えない、文化的リハビリです。
8. まとめ|活字は、心の筋肉を鍛える
高齢期にこそ、文字と活字の力が生きてきます。 読むことで心が落ち着き、書くことで感情が整い、 話すことで社会とのつながりが保たれる。 そのすべてが“整活”の一部です。
活字を読む手が少し震えても、 文字を追う目がゆっくりでも構いません。 1ページ読むたびに、心と脳は確実に動いています。
10月27日「文字・活字文化の日」。 高齢者の方々にとっても、 そして支える家族にとっても、 この日は“言葉で生きる力”を見直すチャンスです。 今日、新聞を1面だけでも読んでみましょう。 その5分が、心の健康をやさしく整えてくれます。
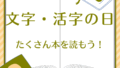
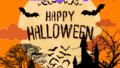
コメント