
tekowaです。
10月の街を歩くと、オレンジや紫、黒の彩りが目を引きます。スーパーにはかぼちゃを使ったスイーツや総菜が並び、保育園や学校では子どもたちが仮装を楽しむ光景も見られます。けれども、私たちが親しんでいる「ハロウィン」という行事の本当の起源や、日本でここまで浸透した背景を知る機会はあまりありません。今回は、古代ヨーロッパから現代日本への文化の流れをたどりながら、“食”との関わりを見つめていきましょう。
ハロウィンのはじまり ― 古代ケルトの「サウィン祭」
ハロウィンの原点は、約2000年以上前のケルト民族の祭り「サウィン(Samhain)」にあります。ケルトの暦では10月31日が一年の終わりであり、冬の始まりでもありました。この夜、人々は収穫を終えて豊穣を感謝し、同時に祖先の霊や精霊がこの世に戻ってくると信じていました。精霊を迎えるために火を焚き、仮面をかぶり、悪霊から身を守るための儀式を行っていたのです。
つまりハロウィンは本来、“命の循環”や“自然の恵み”を感じる行事でした。日本でいえばお盆や秋祭りのような位置づけに近く、「亡くなった人を思い、自然と共に生きる感覚」を大切にする日だったのです。
キリスト教と融合し、アメリカへ渡ったハロウィン
ケルトの風習はやがてキリスト教に取り入れられ、「万聖節(All Hallows)」という聖人の日が11月1日に定められました。その前夜である10月31日が「All Hallows’ Eve(オール・ハロウズ・イヴ)」と呼ばれるようになり、これが「Halloween(ハロウィン)」の語源です。
19世紀、アイルランドやスコットランドの移民がアメリカへ渡ると、この風習も一緒に伝わりました。アメリカでは宗教的意味合いが薄れ、子どもが主役の「トリック・オア・トリート」文化へと変化していきます。お菓子を配り歩く習慣が生まれたのは、貧しい人々が家々を回って祈りを捧げた古い風習「ソウリング」がもとになったといわれています。
ここで重要なのは、ハロウィンが単なる仮装イベントではなく、“分かち合い”や“地域のつながり”を生む社会的行事でもあるという点です。これは現代の日本社会における地域イベントの形にも通じる考え方です。
日本でハロウィンが広まった理由
日本でハロウィンが広く知られるようになったのは1990年代後半。東京ディズニーランドが1997年に開催した「ディズニー・ハロウィーン」がきっかけのひとつです。その後、テーマパークや商業施設が次々とイベントを展開し、SNSの普及も相まって急速に定着しました。
とくに特徴的なのは「仮装文化」と「食の融合」です。日本では宗教色よりも「季節を感じる楽しみ方」として受け入れられ、スーパーやコンビニではハロウィン限定のスイーツや総菜が並ぶようになりました。かぼちゃ、紫いも、チョコレートなど、彩り豊かな秋の食材を使ったメニューが毎年話題になります。
保育園や介護施設などでもハロウィンメニューを取り入れる場が増えています。保育現場では行事食を通じて「季節を感じる心」や「食への興味」を育て、高齢者施設では「見た目の楽しさ」で食欲を引き出す効果が期待されています。
かぼちゃが象徴になった理由と栄養価
ハロウィンといえば「ジャック・オー・ランタン」。オレンジ色のかぼちゃをくり抜いて灯りをともすこの飾りには、もともと悪霊を遠ざける意味がありました。アイルランドでは当初カブが使われていましたが、アメリカでは豊富に収穫できるかぼちゃに置き換えられ、現在の形になったといわれます。
栄養士の立場から見ると、かぼちゃはβカロテンやビタミンEが豊富で、抗酸化作用に優れています。冷え込みが増す秋にぴったりの食材であり、免疫力アップや肌の保湿にも効果的。ハロウィンが流行したことで、かぼちゃを家庭料理で取り入れるきっかけが増えたのは大きなメリットといえます。
保育・介護・家庭それぞれでの楽しみ方
保育園では、かぼちゃのマッシュで作るおばけマッシュポテトや、野菜を型抜きしておばけの顔を作るなど、子どもたちの創造力を育むメニューが人気です。食育の一環として「食べるイベント」としてのハロウィンは、五感を刺激する良い機会になります。
介護施設では、咀嚼や嚥下に配慮したムース食でもハロウィンを楽しむ工夫が見られます。かぼちゃや紫いも、にんじんなどで自然な色味を出し、見た目から季節を感じられるようにすることがポイント。栄養バランスを崩さずに“行事を味わう”ことが、心のリハビリにもつながります。
家庭では、ハロウィンを通じて親子の会話が増えたり、子どもが料理に興味を持つきっかけにもなります。お菓子や装飾だけでなく、家族で「秋の味覚を楽しむ日」として取り入れることが、整った食生活=整活の一部になるのです。
文化が「食」でつながるということ
ハロウィンは、もともと宗教的な行事でしたが、今や食を通じて人と人を結ぶ季節の文化へと変化しました。保育・介護・家庭、どの現場でも「食卓に季節を感じる工夫」があることで、人の心は温かくなります。
行事を形だけで終わらせず、「旬の食材を味わう」「色や香りを楽しむ」ことを意識する。それこそが、私たち日本人の“食文化の成熟”につながるのではないでしょうか。
おわりに
ハロウィンの起源を知ると、ただのイベントではなく「収穫を感謝し、命をつなぐ行事」であることが見えてきます。日本でもその本質を忘れずに、季節を感じながら心と体を整えるきっかけとして取り入れていきたいですね。
次回は、2025年のハロウィントレンドを紹介します。

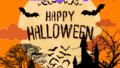
コメント