
tekowaです。
10月24日の国連デー。 世界の平和や人権、持続可能な社会の実現に向けて、多くの国連機関が活動しています。 その中でも、私たちの「食」と深く関わるのが、WFP(国連世界食糧計画)です。 この記事では、WFPの設立背景や活動内容、飢餓の現状、そして私たちができる支援の形について、栄養士の視点も交えて解説します。
WFPとは?
WFP(World Food Programme/国連世界食糧計画)は、1961年に設立された国連の食料支援機関です。 世界中で飢餓に苦しむ人々に食料を届け、「命をつなぐ活動」と「自立を支える活動」の両輪で取り組んでいます。
本部はイタリア・ローマにあり、約2万人の職員が80カ国以上で活動しています。 2020年にはノーベル平和賞を受賞し、飢餓と紛争の悪循環を断ち切る努力が国際的に高く評価されました。
WFPの使命|“Zero Hunger” 飢餓をゼロに
WFPの最大の使命は、「Zero Hunger(飢餓ゼロ)」です。 これはSDGs(持続可能な開発目標)第2目標に掲げられており、WFPはその実現の中心的存在です。
飢餓は単に「食べ物が足りない」という問題ではありません。 貧困、紛争、気候変動、経済格差、ジェンダー不平等など、複数の要因が重なり合って発生します。 WFPは、こうした複雑な背景を理解したうえで、地域の状況に合わせた支援を行っています。
飢餓の現状
国連の2024年報告によると、世界で約7億3,500万人が十分な食料を得られずに暮らしています。 これは世界人口の約9人に1人の割合にあたります。
特に深刻なのはアフリカ地域で、サハラ以南の国々では子どもの約3人に1人が慢性的な栄養不足(低身長)に苦しんでいます。 また、ウクライナ紛争や気候変動による干ばつ・洪水が食料生産に影響し、食料価格の高騰も問題を深刻化させています。
さらに、飢餓の影響は「体」だけでなく「心」にも及びます。 十分に食べられないストレスや不安は、教育・就労意欲の低下、家庭内暴力など、社会的問題へとつながっていくのです。
WFPの主な活動
WFPの活動は大きく2つに分かれます。
- 1. 緊急支援(Emergency Relief):紛争や災害などで食料を失った人々に、すぐに食料を届ける活動。
- 2. 開発支援(Development Support):地域の自立を支援し、飢餓の連鎖を断ち切る活動。
① 緊急支援
自然災害や戦争が発生した際、WFPは現地に食料や栄養補助食を届けます。 例として、ウクライナ危機、シリア内戦、ガザ地区、アフリカ東部の干ばつなどが挙げられます。 緊急時には、ヘリコプターやドローン、さらには「空中投下」などの手段で命をつなぐ物資を運ぶこともあります。
② 開発支援
緊急支援の後は、地域の人々が自立できるように支援が続きます。 たとえば、
- 学校給食の提供(子どもが学校に通う動機づけに)
- 農業支援(種や道具の提供・栽培技術の教育)
- 道路整備(食料輸送ルートの確保)
- 女性の就労支援(食料配布や給食調理の仕事創出)
特に学校給食プログラムは、教育と栄養の両面を支えるWFPの代表的な活動で、世界約60カ国で実施されています。
日本とWFPの関係
日本はWFPの主要な支援国の一つです。 政府からの拠出金のほか、民間企業や個人による寄付も活発です。
日本では「国連WFP協会」が活動しており、募金やキャンペーン、企業とのタイアップなどを通して飢餓ゼロ運動を広めています。 また、緊急時には日本米や非常食が被災地に送られることもあります。
日本発の取り組み例
- 「レッドカップキャンペーン」:学校給食支援のための募金活動。
- 「おにぎりアクション」:おにぎりの写真を投稿すると5食分の給食が寄付される。
- 「食品ロス削減×WFP」:賞味期限間近の食品を活用して支援につなげる。
これらの活動は、日本ならではの「食の思いやり文化」が国際貢献につながっている例でもあります。
WFPとSDGs
WFPの活動はSDGsの複数の目標に直結しています。
- 目標1:貧困をなくそう
- 目標2:飢餓をゼロに
- 目標3:すべての人に健康と福祉を
- 目標4:質の高い教育をみんなに
- 目標5:ジェンダー平等を実現しよう
WFPは「食」を中心に、教育・健康・平等といった他分野にも波及効果をもたらしています。 食べることは、生きることの基盤。 だからこそ「飢餓の解決」は、すべての目標を支える柱と言えます。
テクノロジーを活用した食料支援
近年のWFPは、テクノロジーを活用して効率的な支援を実現しています。 たとえば、
- ブロックチェーンによる現金給付(難民がスマホで支援を受け取れる)
- AIを用いた食料需要の予測
- ドローンを使った災害時の食料輸送
これらの技術は「人道支援×デジタル化」という新しい形の国際協力として注目されています。
私たちにできる支援
WFPの活動は、私たち一人ひとりの行動からも支えられています。 特別なことをしなくても、日常の中でできる支援があります。
- おにぎりアクションに参加する
- 食品ロスを減らす(買いすぎ・作りすぎを見直す)
- WFPの寄付プログラムを知る
- フェアトレード商品を選ぶ
- 子どもと一緒に「世界の食の不平等」を話す
例えば、おにぎり1枚の写真投稿で5食分の給食が届く。 たったそれだけでも、誰かの未来が変わるのです。
まとめ
WFPの活動は、「食」を通じて命をつなぎ、未来を育むものです。 飢餓は遠い国の問題ではなく、地球全体の課題です。 国連デーをきっかけに、食べることのありがたさ、そして誰もが「満たされる世界」を目指すWFPの思いを感じてみませんか?
次回は「国連と教育支援(ユネスコの活動)」についてお届けします。
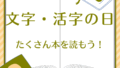

コメント