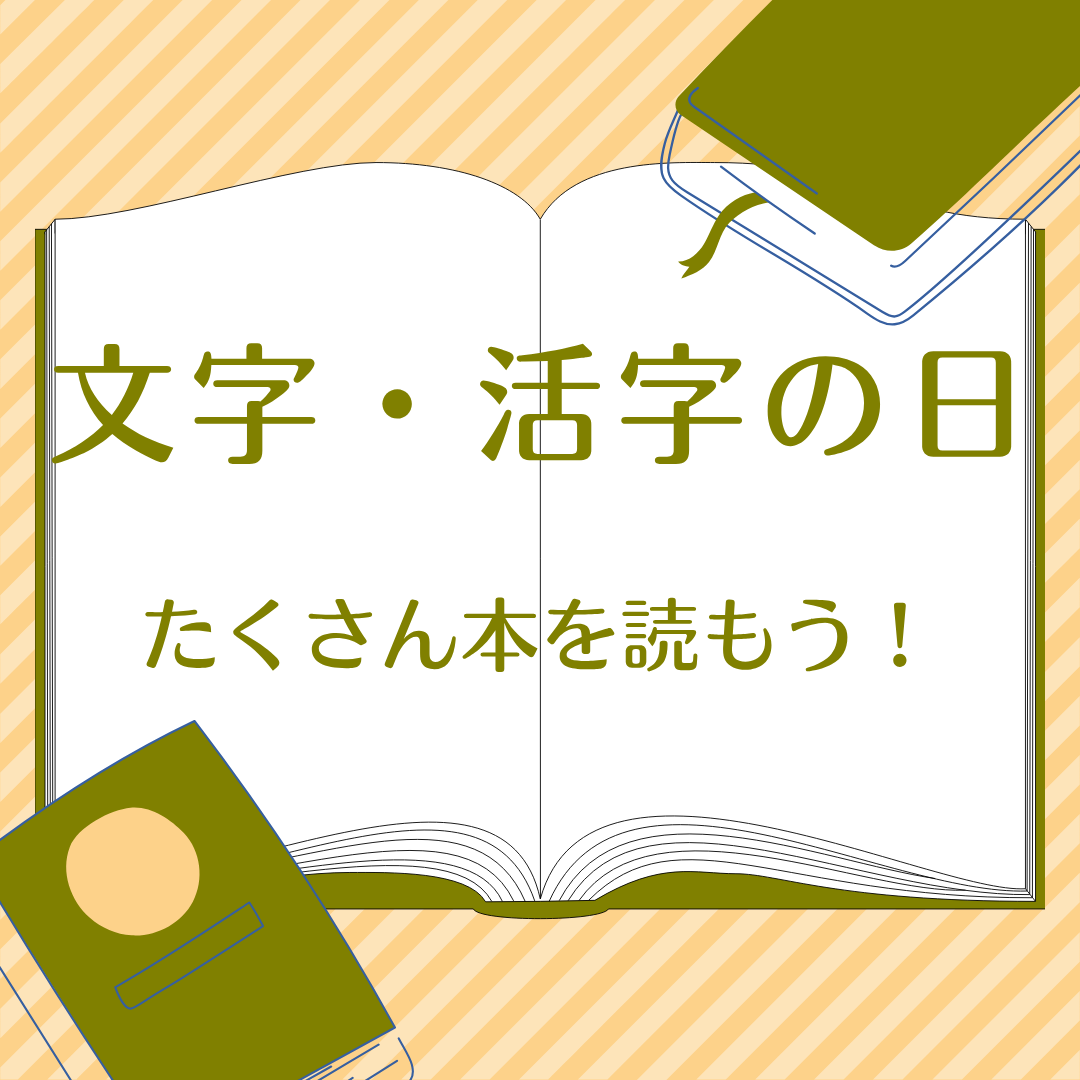
tekowaです。
10月27日の「文字・活字文化の日」シリーズも、いよいよ最終章です。 ここまで“読む力”を中心にお伝えしてきましたが、 今回は「読む」「書く」「話す」という3つの言葉の動きを “整活(=心と生活を整える活動)”の視点からまとめていきます。
人は言葉によって思考し、行動し、心を整理します。 つまり、言葉は“心の設計図”でもあるのです。 この3つをバランスよく使うことで、 人間関係・感情・思考・体調まで自然と整っていきます。
1. 「読む」は、心を満たす栄養補給
読むことは、情報を取り入れるだけでなく、 自分の中に“静かな時間”を生み出す行為です。 活字に触れることで、外の世界の喧騒を一度離れ、 心の中を整えることができます。
整活的に言えば、「読む=心の栄養補給」。 偏った情報ではなく、自分に必要な“栄養のある言葉”を選ぶことで、 考え方や感情のバランスが取れていきます。
たとえば、落ち込んだときはエッセイや詩集、 焦っているときは自然や食に関する本など、 心の状態に合わせて“読むジャンル”を選ぶのも整活の一種です。
2. 「書く」は、心を整理するセルフケア
書くことは、自分と向き合う時間です。 ノートやメモに感情を書き出すだけで、 心の中のモヤモヤを整理し、冷静さを取り戻すことができます。
私はよく「書く整活」として、次の3ステップをおすすめしています。
- 今日あったことを3行で書く
- そのとき感じた気持ちを1語で書く(例:安心・焦り・感謝など)
- 最後に「明日はこうしよう」と1行書く
これだけで、頭と心の整理が自然に進みます。 人は“書く”ことで思考を外に出し、“読む”ことでそれを受け取る。 この往復が、心の交通整理になるのです。
また、書くことは「言葉の筋トレ」。 感情を言葉で表現する力が高まるほど、 ストレスを抱えにくくなります。 これは保育・福祉の現場でも感じることで、 言葉を持つ人ほど感情表現が穏やかで、衝突が少ない傾向にあります。
3. 「話す」は、言葉を循環させるコミュニケーション
話すことは、読む・書くで育てた言葉を“外に出す”行為です。 発した言葉は耳から再び自分に返ってきて、 自己理解を深める働きをします。
たとえば、日常会話でも次のような整活的工夫ができます。
- 否定から入らず「そうなんだね」と受け止める
- 相手の話を最後まで聞いてから返す
- 「ありがとう」「大丈夫?」などの声かけを意識的に使う
これらはすべて“言葉の整活”。 人との会話は、心のバランスを整える大切な手段です。 話すことが減ると、心が閉じていく一方、 言葉を交わすことでエネルギーが循環し、心が軽くなります。
介護の現場では、短い会話がその人の一日を変えることもあります。 「おいしかったね」「いい天気ですね」 そんな一言が、人の心をほぐす薬になるのです。
4. 「読む・書く・話す」をつなぐ整活サイクル
3つの言葉の動きをつなぐと、次のような“整活サイクル”が生まれます。
読む → 書く → 話す → また読む。
読むことで知識と気づきを得て、 書くことで自分の考えを整理し、 話すことで他者と共有して深める。 そしてまた、誰かの言葉を読むことで新しい学びが生まれる―― この循環こそが「言葉の整活」です。
このサイクルが回り始めると、 心が安定し、自己肯定感も高まります。 “自分の言葉で考え、自分の声で伝える”という習慣が、 AI時代にも揺るがない人間力を育てます。
5. 整活的・言葉との付き合い方ヒント
- スマホを閉じて紙の文字に触れる時間を作る
- 寝る前に「今日一番心に残った言葉」を書く
- 朝の挨拶を丁寧に言葉に出す
- 感謝のメッセージを週1回誰かに送る
- お気に入りの言葉ノートを作る
こうした小さな積み重ねが、 「言葉を大切にする人」を作ります。 言葉を整えることは、心を整えること。 そしてそれが、栄養・睡眠・人間関係すべてを穏やかにする基盤になります。
6. まとめ|言葉の整活は“生き方”を美しくする
読む・書く・話す――。 この3つの言葉の力を意識するだけで、 人との関わり方や自分の捉え方がやわらぎ、 生き方そのものが整っていきます。
10月27日、文字・活字文化の日。 この日をきっかけに、あなた自身の「言葉の整活」を始めてみませんか? 読むことで心を満たし、書くことで感情を整え、話すことで人とつながる。 その積み重ねが、未来のあなたをやさしく照らしてくれます。
“言葉で整う暮らし”を、今日から少しずつ。 整活は、静かな一行から始まります。
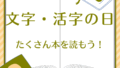

コメント