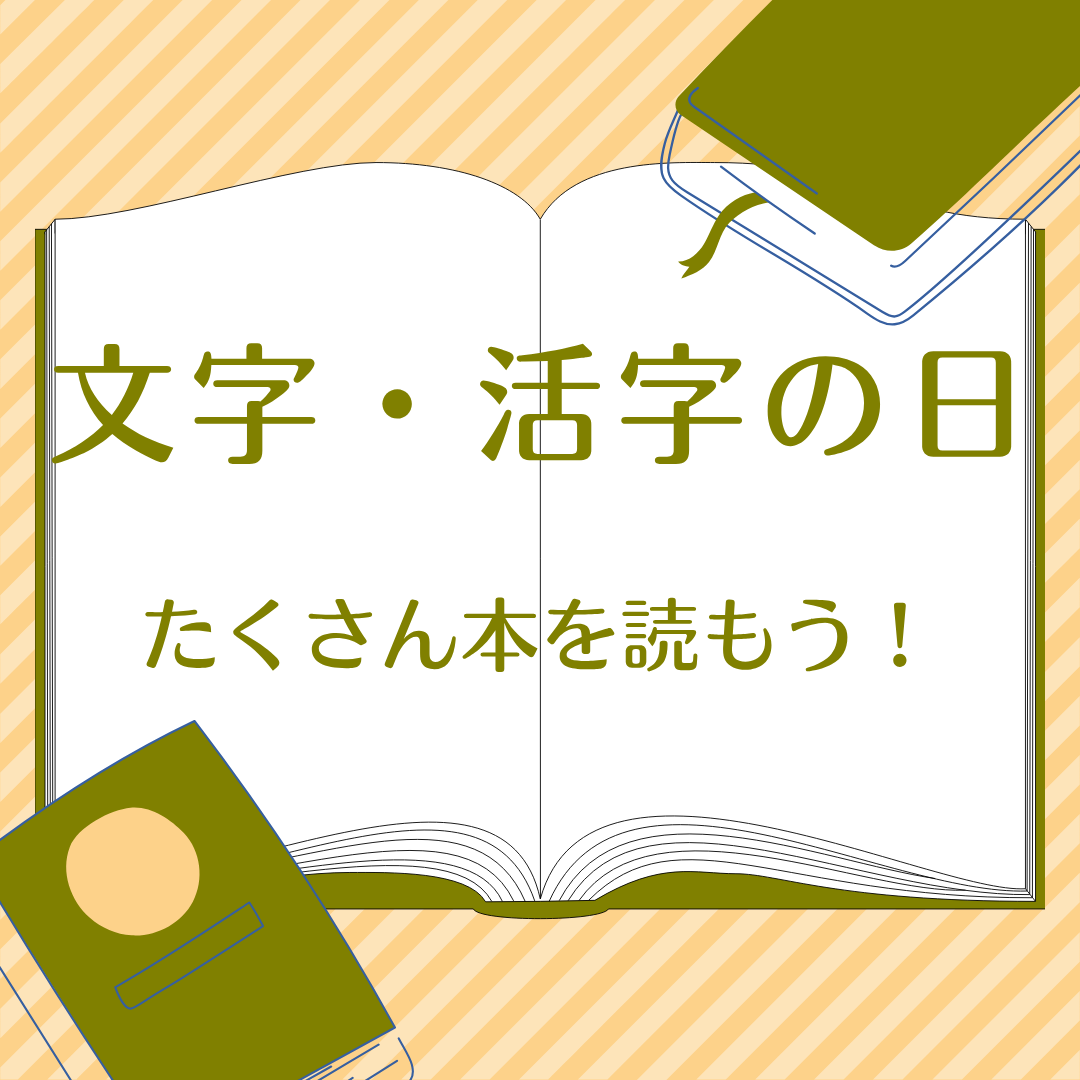
tekowaです。
10月27日は「文字・活字文化の日」。 いま、スマホ1つで世界とつながる時代に、 あえて“活字”に目を向ける意味を考えたことはありますか? SNSが日常の一部になった現代だからこそ、 私たちには「言葉を整える力=活字のチカラ」が求められています。
1. SNSの便利さの裏にある“言葉の軽さ”
SNSでは、短い言葉・感情的な発言・反射的な反応が目立ちます。 もちろんリアルタイムで思いを伝えるのは魅力的なこと。 しかしその一方で、「考える前に発信してしまう」ことで、 誤解・炎上・分断が生まれるケースも少なくありません。
活字には“間”があります。 本や文章を読むとき、私たちは一度立ち止まり、 「なにを伝えたいのか」「どう感じたのか」を考える時間を持てます。 その“間”こそが、思考を深め、人との違いを受け止める力になるのです。
2. 活字が育てる3つのチカラ
活字文化を大切にすることは、単なる読書推奨ではありません。 それは「人としての土台を整える行為」です。 ここでは、活字が育てる3つの力を紹介します。
① 思考力
文章を読むということは、頭の中で情報を整理すること。 主語と述語、因果関係、比喩表現などを無意識に処理するため、 論理的思考力が自然と鍛えられます。 SNSで一瞬の感情を吐き出すのとは異なり、 「言葉の背景を読み取る力」が育ちます。
② 想像力
活字は映像のない世界。 読者は自分の中で登場人物の表情や場面を想像します。 この「想像する力」は、人を思いやる心=共感力の源です。 保育や介護の現場でも、想像力がある人ほど他者への気づきが早い。 それはまさに“読む力”が“優しさ”を育てている証拠です。
③ 表現力
読書を通じて多様な語彙に触れると、 自分の感情を丁寧に表現できるようになります。 「うれしい」「悲しい」だけではなく、 「じんわり」「切ない」「くすぐったい」といった微妙な言葉が増えると、 感情を適切に伝えることができるようになります。 これは人間関係のトラブルを減らす“心の整活”でもあります。
3. SNS時代の“読む整活・書く整活”
現代の整活では、食事や運動だけでなく、 “情報との付き合い方”を整えることも重要です。 SNSやニュースなどの情報を取捨選択するためには、 「読む力」「考える力」「言葉を選ぶ力」が欠かせません。
たとえば、1日の終わりにスマホを閉じて、 紙の本や新聞を10分読むだけで思考の質が変わります。 活字を読むことで、脳は「情報の整理」を始めます。 混乱した気持ちや焦りが落ち着き、 “自分の軸”が戻ってくる感覚があるはずです。
4. 子どもたちに伝えたい“言葉の整え方”
子どもにとっても、言葉の扱い方を学ぶことは非常に大切です。 SNSが早期化する今、「文字でのやり取り」を誤解なく行うためには、 活字の基本=“文章を読む・書く”体験が必要です。
たとえば家庭では、次のような“活字整活”がおすすめです:
- 一緒に日記を書く(その日の気持ちを言葉に)
- 感想文の「好きな場面」を一緒に話す
- 絵本を読んだあと、「どんな気持ちになった?」と尋ねる
- お手紙やメッセージカードを書いて気持ちを伝える
これらはすべて「言葉の筋トレ」。 自分の感情を正確に言葉にできるようになると、 トラブルの回避力や対話力が高まります。
5. 大人こそ“言葉を整える時間”を
SNSやメールのやり取りで、つい言葉がきつくなったり、 誤解を招いた経験はありませんか? 大人もまた、情報に追われる日々の中で「言葉を整える時間」を持つことが必要です。
おすすめは、“書く瞑想”のようにペンを動かす時間を取ること。 今日あったことを3行でもいいのでノートに書き出すと、 心の中のモヤモヤが整っていきます。 書くことは“自分と対話する行為”であり、 内省(リフレクション)の習慣にもつながります。
6. 保育・介護・栄養の現場に共通する“言葉の大切さ”
私の経験からも感じるのは、「言葉が人を整える」ということ。 保育の現場では、言葉かけ一つで子どもの表情が変わります。 介護の現場では、優しい言葉が安心や笑顔を生みます。 栄養指導では、言葉選び一つで「やってみよう」と思える力が引き出せます。
つまり、言葉は“心の栄養”なのです。 活字文化を大切にすることは、 人と人をつなぐ“見えない栄養素”を補う行為とも言えます。
7. まとめ|活字のチカラで心を整える
SNSの速い流れの中で、言葉が軽く扱われがちな今。 だからこそ、私たちは一度立ち止まり、 “言葉を整える”時間を意識的に作る必要があります。
活字は、思考を深め、心を静かにし、人との距離を整えてくれます。 1日10分でもいい。 スマホを閉じ、本を開く――それだけで世界の見え方が変わります。
10月27日、文字・活字文化の日。 読むこと、書くこと、伝えること。 その一つひとつが、整った暮らしの礎になります。 活字のチカラを、もう一度生活の中に取り戻していきましょう。
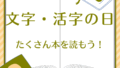

コメント