
tekowaです。
10月18日は「冷凍食品の日」。 近年は“時短”や“便利”というイメージに加えて、健康志向の冷凍食品も多く登場しています。 冷凍食品は上手に使えば、栄養バランスの整った食生活を続ける大きな味方になります。 今回は、栄養士の立場から、冷凍食品を健康的に取り入れるためのコツを詳しく紹介します。
冷凍食品を健康的に使う基本の考え方
冷凍食品は、「上手に選び・組み合わせ・使いこなす」ことで、健康を支える食材になります。 大切なのは、“冷凍=加工食品だから不健康”という思い込みを手放すこと。 むしろ、急速冷凍によって栄養が保たれた優れた食品も数多くあります。
冷凍技術の発達により、ビタミンやミネラルが壊れにくく、旬の食材を長期保存できるようになりました。 たとえば冷凍ほうれん草や冷凍ブロッコリーは、下茹で不要で手軽に野菜をプラスでき、 忙しい人ほど健康的な食事を維持しやすくなっています。
栄養士がすすめる冷凍食品の選び方
健康的に冷凍食品を取り入れるには、次の3つのポイントを意識しましょう。
- ① 栄養バランスで選ぶ: 主食・主菜・副菜のバランスを意識。野菜入りやたんぱく質を含むメニューを選ぶ。
- ② 成分表示を確認: 塩分・脂質・糖質をチェック。特に「1食あたりの塩分量3g以下」が目安。
- ③ 加工度を見極める: 衣が厚すぎる揚げ物や、ソースが濃い製品は控えめに。
また、電子レンジ調理に対応した製品を活用すれば、油を使わずに調理でき、余分なカロリーを抑えられます。
冷凍食品と組み合わせたい“整う副菜”
冷凍食品を中心に使うときは、汁物や副菜で栄養を補うのがポイントです。 以下のような組み合わせを意識してみてください。
- 冷凍パスタ+野菜スープ(冷凍ミックスベジタブルを使用)
- 冷凍チャーハン+冷凍枝豆+冷奴
- 冷凍うどん+温泉卵+小松菜のお浸し
- 冷凍からあげ+冷凍かぼちゃ煮+具沢山味噌汁
冷凍食品を主菜に据え、野菜や汁物でビタミン・ミネラルを補うことで、 冷凍中心でもバランスの取れた食卓になります。
“塩分・脂質過多”にならない工夫
冷凍食品は味付けがしっかりしているものが多いため、調味料を足さないことが大切です。 また、同系統の味(例えば唐揚げ+チャーハンなど)を組み合わせると、塩分が重なりやすくなります。 一方の味付けを控えめにしたり、野菜や汁物で薄味のバランスを取ることで、健康的な食事になります。
家庭で作る“自家製冷凍食品”もおすすめ
健康志向の方には、自家製冷凍もおすすめです。 一度に多めに作って小分け冷凍しておけば、添加物を気にせず時短が叶います。
- 鶏むね肉の下味冷凍(塩麹・味噌・ヨーグルトなど)
- ひじき煮・切り干し大根の煮物
- 野菜スープやミネストローネ
- 豆腐ハンバーグやつくね
自家製冷凍は、手作りの安心感と栄養の両立ができ、食費の節約にもつながります。
冷凍食品を「整う食生活」に活かす
冷凍食品を上手に使うことは、食生活の“整え”にもつながります。 「作る」から「整える」へ――冷凍庫を活用すれば、無理なくバランスが取れる生活が実現します。
たとえば、冷凍野菜で“彩りを整える”、冷凍ごはんで“量を整える”、冷凍魚で“たんぱく質を整える”など、 整活的な発想で使えば、心身のリズムも整いやすくなります。
まとめ
冷凍食品は、忙しい現代の食生活に欠かせない存在です。 健康的に取り入れるためには、「選び方」「組み合わせ」「食べ方」の3つがカギ。 冷凍食品を賢く活用すれば、時短・節約・健康の三拍子がそろった“整う食生活”が叶います。 10月18日の「冷凍食品の日」を機に、あなたの冷凍庫を“整活のパートナー”にしてみませんか?
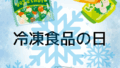

コメント