
tekowaです。
10月16日の「世界食料の日」は、世界的な飢餓やフードロスだけでなく、各国の食料自給率や農業のあり方を考えるきっかけにもなります。特に日本は食料自給率が先進国の中でも低く、今後の食料安全保障に課題を抱えています。本記事では、日本の自給率の現状、持続可能な農業の方向性、そして私たちができることを解説します。
日本の食料自給率の現状
農林水産省の統計によると、日本の食料自給率(カロリーベース)は38%前後にとどまっています。これは、私たちが食べているカロリーの約6割を輸入に依存していることを意味します。特に小麦・大豆・油脂などは輸入依存度が非常に高く、もし国際的な物流が止まった場合には食卓に大きな影響が及びます。
一方、生産額ベースの食料自給率は65%前後とされています。これは日本国内で生産された食材の金額割合を示すもので、米や野菜、魚介類などは国内産が多いことを反映しています。しかし、主食や飼料作物の輸入依存度を考えると、安心できる数字とは言えません。
食料自給率が低いことのリスク
食料自給率の低さは、単なる統計上の数字ではなく、国の安全保障にも直結します。
- 国際情勢の不安定化で輸入が滞るリスク
- 円安や価格高騰による食料費の増大
- 農業人口の減少による国内供給力の低下
- 気候変動で収穫が不安定になり、輸入依存国からの調達も難しくなるリスク
こうした問題を背景に、国内農業をどう守り、育てていくかが急務となっています。
持続可能な農業とは?
「持続可能な農業」とは、環境・経済・社会の3つの側面から持続可能性を追求する農業の形を指します。環境への負担を減らしつつ、農家が経済的に成り立ち、次世代に農業が継承されていく仕組みを作ることが求められています。
① 環境に配慮した農法
農薬や化学肥料の使用を減らす有機農業、地元で循環する資源を活用する農法、脱炭素化に向けたエネルギー利用などが進められています。環境に優しい農業は、気候変動対策にもつながります。
② 農業のデジタル化(スマート農業)
ドローンによる農薬散布やAIを活用した収穫予測、ロボットによる作業自動化など、デジタル技術を導入することで農業の効率化と人手不足の解消が図られています。
③ 地域との連携
農産物の地産地消や、学校給食での地元野菜の活用は、地域の農業を支え、子どもたちの食育にもつながります。都市と農村をつなぐ「CSA(地域支援型農業)」も広がりつつあります。
私たちにできること
食料自給率を高める、持続可能な農業を応援するために、消費者である私たちにもできることがあります。
- 地元産の野菜や米を選ぶ ― 地産地消を意識する
- 旬の食材を取り入れる ― 輸入依存を減らす一歩に
- フードロスを減らす ― 廃棄を減らせば農産物の有効活用に
- 農業体験やボランティアに参加する ― 農業への理解と応援につながる
未来の食を守るために
「持続可能な農業」は、農家だけでなく、消費者や企業、行政が一体となって取り組むべき課題です。私たち一人ひとりが地元の農産物を選び、食品ロスを減らす行動をすることで、国内の農業を支える力になります。
まとめ
日本の食料自給率は低い水準にありますが、持続可能な農業を支え、地産地消やフードロス削減を進めることは、未来の食を守る大きな力になります。世界食料の日をきっかけに、私たちも「食の選び方」を見直し、次世代につながる持続可能な食卓をつくっていきましょう。
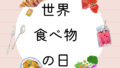

コメント