
tekowaです。
「よく噛んで食べなさい」と昔から言われてきましたが、その背景には単なる消化の問題だけでなく、脳の働きにまで影響があることが分かっています。近年の研究では、噛むこと=咀嚼が集中力や学力に深く関わっていることが明らかになってきました。栄養士としての視点や、保育士補助として子どもを見てきた経験を踏まえながら、噛む力と集中力・学力の関係について解説していきます。
噛むことが脳に与える影響
咀嚼の動作は単なる食事の一部ではなく、脳への刺激をもたらす重要な行為です。
- 脳血流を増やす: 噛むことで顎の筋肉が動き、脳への血流が促進される。
- 海馬を活性化: 記憶を司る海馬が刺激され、記憶力や学習能力が高まる。
- 集中力の持続: 脳が活性化することで学習や作業への集中が長続きする。
噛む力不足が招く学習面の問題
噛む力が不足すると、顎や歯の問題だけでなく学習面にも影響が出ます。
- 集中が途切れやすく、学習効率が下がる。
- 姿勢が崩れやすく、書く・読むなどの作業に支障が出る。
- 偏食や早食い習慣が集中力低下につながる。
保育園や小学校で「落ち着きがない」と言われる子どもたちの中には、噛む習慣が少ないことが関係しているケースもあります。
子どもの実例から見る噛む力と集中力
例えば、わが家の子どもたちの噛む力の差にも集中力の違いが現れています。下の子(2歳9か月)は小魚やぬか漬けきゅうりを好んで噛み砕くため、食事中の集中も長続きします。一方で上の子(5歳9か月)は噛む習慣が少なかったため、食べるのに時間がかかり、噛むことを忘れることもしばしば。声掛けをして意識させると集中が持続するので、やはり噛む力と集中力には密接な関係があると実感しています。
学習効率を高めるための「噛む工夫」
家庭や学校で簡単に取り入れられる「噛む工夫」を紹介します。
- おやつに噛む食材を: ガムや小魚、ナッツなど咀嚼を促すものを取り入れる。
- 朝食に噛みごたえを: ご飯と野菜味噌汁など、噛む習慣をつけやすいメニューにする。
- 学習前の噛む習慣: ガムを噛んだ後に勉強すると集中が続きやすい。
- 保育・学校現場での意識付け: 食育活動で「よく噛む」ことを伝える。
噛むこととストレス軽減の関係
噛む行為は集中力だけでなく、ストレス軽減にも役立ちます。緊張しているときにガムを噛むとリラックスできるのは、脳内のセロトニン分泌が促されるためです。子どもにとっても、大事なテスト前や緊張する場面で「噛む」習慣は心を落ち着ける効果を発揮します。
まとめ:噛む力は学力を支える土台
噛む力は食べるためだけでなく、集中力や学習力を支える重要な基盤です。噛むことで脳が活性化し、集中力が持続し、記憶力も高まります。子どもの成長にとって「よく噛む習慣」はまさに一生の宝。歯ぢから探究月間をきっかけに、家庭や学校で噛む工夫を取り入れ、学力向上にもつなげていきましょう。

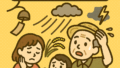
コメント