
tekowaです。
介護の現場では「噛む力=歯ぢから」を維持・回復するために、さまざまな取り組みが行われています。高齢者にとって噛む力の低下は、誤嚥や低栄養、生活の質の低下に直結する大きな課題です。そこで実践されているのが「咀嚼リハビリ」。これは単に食事を工夫するだけでなく、口腔機能全体を意識した包括的なケアです。今回は介護福祉士としての視点から、現場で実践されている咀嚼リハビリの具体的な方法と効果を解説します。
咀嚼リハビリとは?
咀嚼リハビリとは、噛む力や飲み込む力を維持・回復するために行う訓練や生活支援のことです。対象は主に高齢者や病気後の方ですが、実は誰にとっても有効な取り組みです。食事の楽しみを守り、誤嚥を防ぎ、栄養をしっかり摂取するための重要な手段です。
介護現場で取り入れられている咀嚼リハビリの方法
① 口腔体操
食事前に行う口腔体操は、咀嚼リハビリの基本です。具体的には以下のような運動があります。
- 「あいうべ体操」:口を大きく開けて「あ・い・う・べ」と発音。
- 舌回し運動:舌を上下左右に動かして筋肉をほぐす。
- 頬の膨らまし運動:口の中で空気をためて頬を膨らませる。
これらは口周りの筋肉を柔らかくし、咀嚼や嚥下をスムーズにする効果があります。
② 食事形態の工夫
介護食=柔らかい食べ物、というイメージが強いですが、噛む力を完全に奪ってしまうと逆に衰えます。そのため現場では「無理のない噛みごたえを残す」工夫がされます。
- 煮物は柔らかくしつつも形を残す。
- 魚は骨を取り除き、身を少し厚めに切る。
- おかゆだけでなく、雑炊や柔らかめのご飯も取り入れる。
③ 咀嚼トレーニング
食事以外の時間でも、咀嚼筋を動かすトレーニングが行われます。
- ガムやグミを使った噛む練習。
- 「噛むおもちゃ」を利用する(特に口腔機能訓練用)。
- 発声や歌唱を通して口周りを動かす。
④ 姿勢や環境の工夫
正しい姿勢は咀嚼や嚥下を助けます。椅子に深く座り、背筋を伸ばし、頭を少し前傾させる姿勢が理想的です。また、落ち着いた環境でゆっくり食事することも誤嚥防止につながります。
⑤ 多職種連携
介護現場では介護福祉士だけでなく、歯科医師、歯科衛生士、管理栄養士、言語聴覚士などが連携して咀嚼リハビリを支えています。それぞれの専門性を活かし、食事の工夫や口腔ケア、嚥下訓練を総合的に行います。
咀嚼リハビリの効果
継続的に咀嚼リハビリを行うことで、以下のような効果が期待できます。
- 噛む力の維持・回復。
- 誤嚥や窒息の予防。
- 栄養状態の改善。
- 食べる楽しみの維持による生活の質向上。
- 会話や表情が豊かになり、社会参加意欲が高まる。
まとめ:咀嚼リハビリは「生きる力」を守る
介護現場で行われる咀嚼リハビリは、単なる訓練ではなく「生きる力」を支える取り組みです。噛む力を維持することは栄養や免疫、脳の健康に直結し、高齢者の生活を豊かにします。歯ぢから探究月間をきっかけに、家庭でもできる口腔体操や食事の工夫を取り入れ、高齢者の健康寿命を一緒に支えていきましょう。

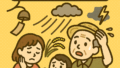
コメント