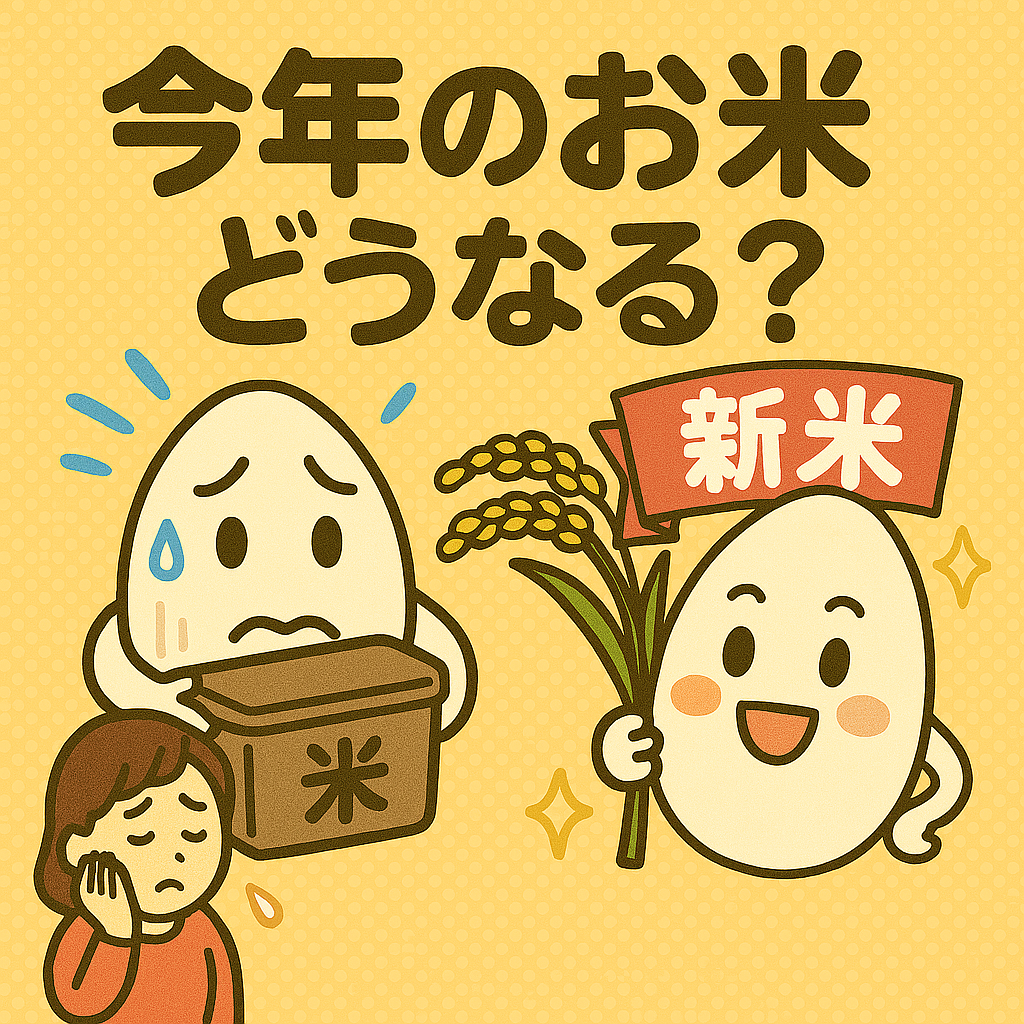
tekowaです。
「平成の米騒動」を覚えていますか。1993年、日本は記録的な冷夏に見舞われ、全国の作況指数は74まで落ち込み、店頭からコメが消える事態に。2024〜25年に見られる“令和の米不足感”と何が同じで、何が違うのか。この記事では、原因・制度・輸入・価格・消費行動の5視点で徹底比較します。
1. 原因:単一の冷夏(1993) vs 複合要因(2024〜25)
1993年は、冷夏・日照不足が決定的な単一要因でした。全国作況指数は戦後最悪の74。学術的にも、当時の異常気象はピナトゥボ火山の噴火後の気候影響やエルニーニョの関与が指摘されています。結果として収穫量は大幅減、政府は海外から緊急輸入を実施する異例の対応に踏み切りました。11
2024〜25年は、猛暑と豪雨の繰り返しによる品質・歩留まりの揺らぎに加え、生産調整・高齢化・在庫と流通のタイムラグ、需要の回復や季節的偏りなど、複数要因が同時に絡む“複合型”です。局地的に店頭が薄く見える一方で、統計上は一定の輸入・在庫が存在するという“体感”と“需給”のズレが起きやすいのが令和の特徴です。12
2. 制度と輸入:緊急輸入(1993)と恒常的TRQ(令和)
1993年は“特例”としての緊急輸入が注目されました。これを機に、UR合意などの通商枠組みの下でミニマムアクセス(MA)米が制度化。現在はWTOのTRQ:精米換算で約68万2千トン/年が恒常運用され、OMA(通常入札)とSBS(同時売買)で調達・配分されています。2024/25年度も約70万トン規模の輸入見込みが示され、制度的には毎年の安全弁がある状態です。13
3. 価格の出方:一気に跳ねた平成、じわ高の令和
1993年は作況が歴史的に悪く、家庭の緊急需要と報道の相乗効果で短期的な店頭不足が顕在化し、価格が急騰しました。対して令和の局面は、品質ミックスの悪化・仕入れコスト・為替・心理などの合併症でじわじわ高止まりしていく傾向。2025年には5kg=4,000円台という報道や、相対取引で60kg=2万6千円台の水準が示されるなど、消費・外食双方に影響が波及しています。14
4. 消費者行動:買い占めの連鎖(平成)と分散的なローリング(令和)
平成の米騒動では「棚から消える」映像が大量に流れ、一斉の買い急ぎが連鎖。令和の局面でも一部地域で似た事象は起きましたが、TRQや備蓄制度が定着し、月を跨いだ出回りや業務用・家庭用の切替で市場が徐々に落ち着くパターンが見られます。消費者側もローリングストックや代替主食の併用で、波をいなす家計防衛が広がっています。15
5. 小売・外食への影響:仕入れとメニュー設計の工夫
外食では銘柄・等級を柔軟に見直しつつ、提供量や価格、ランチ・テイクアウトの設計で吸収を図る動きが出ています。給食は長期契約が多いものの、素材価格上昇が献立に及ぶため、米粉・雑穀・麺などで調整するケースも。家庭ではパックご飯やアルファ米の活用、もち麦・雑穀のブレンド、冷凍ご飯の品質確保(粗熱取り→急冷→ラップ二重)などが定番化しています。
6. データで押さえる要点
- 1993年作況指数=74:戦後最悪(冷夏)—制度整備の転機に。16
- TRQ=約682千トン/年:恒常的に輸入される安全弁。17
- 2025年価格指標:店頭5kgで4千円台報道/相対26,000円台。18
- 24/25年輸入見通し:約70万トン規模で推移の公的レポート。19
7. まとめ:違いを知れば、慌てず備えられる
平成は「一撃の冷夏」が引き起こした短期の大混乱。令和は、猛暑・豪雨という極端現象の頻度増に、制度・流通・心理が絡む複合型の不安定です。TRQや備蓄は機能しており、物理的な“欠配”に直結しない局面でも、タイミングのズレや品質ミックスで家計の体感物価が上がるのが現代の難しさ。だからこそ、ローリングストック・保存・炊飯の最適化で波をいなし、出回りの節目(新米の流通、本決算の在庫見直し、学期替わりの業務需要)を冷静に見極めることが、最短ルートの家計防衛です。20


コメント