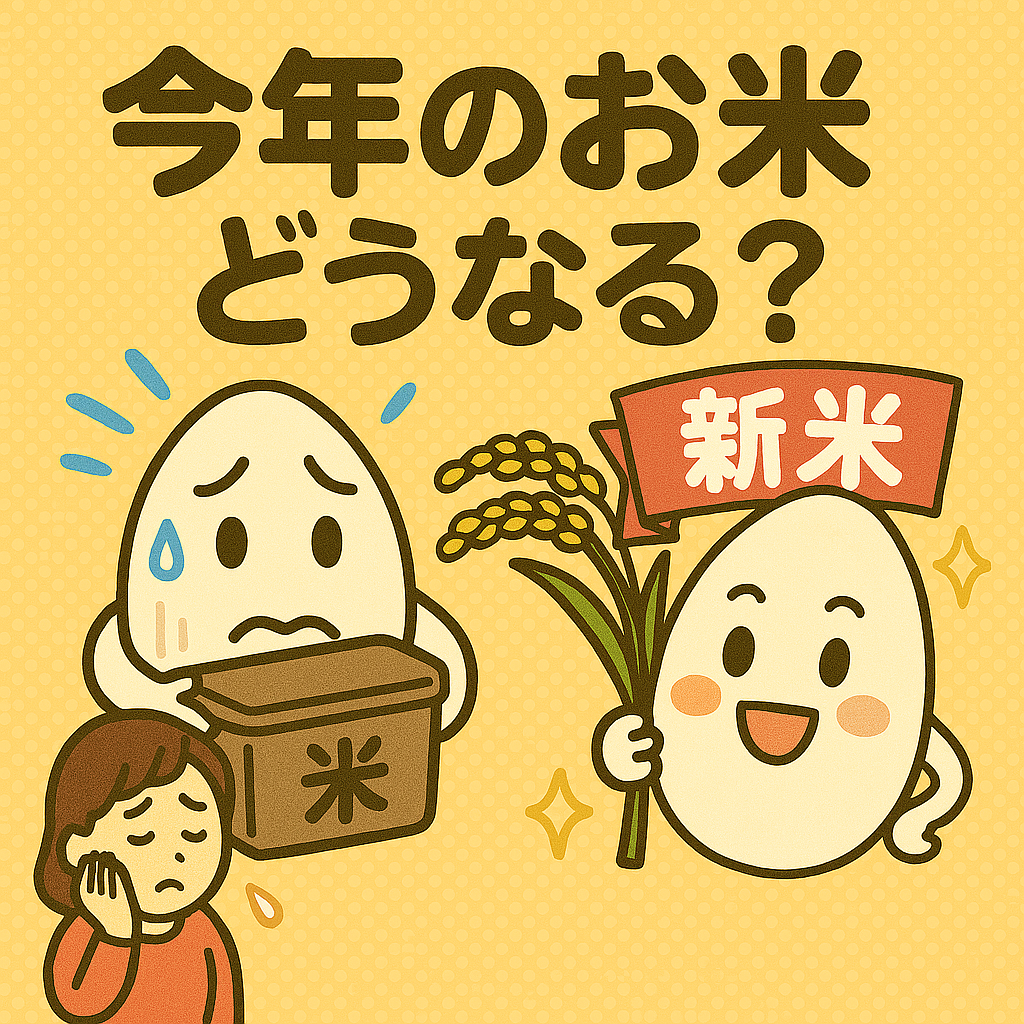
tekowaです。
「お米が高い」「スーパーで在庫が薄い」。2025年の夏から秋にかけて、日本の食卓は“米不足”という不安と向き合っています。本記事では、2025年の米不足の背景を、天候不順・災害、需給と在庫・輸入制度、価格動向の3つの軸で整理。1993年の平成の米騒動とは違う、令和ならではの構造も踏まえて、暮らしの実践策まで解説します。
1. 2024〜2025年にかけて何が起きたのか
直近の需給の崩れは、前年度の天候要因の影響が翌年に長く尾を引くところにあります。2024年は猛暑や局地的豪雨で品質・歩留まりの低下が懸念され、2024年産米の一部が高値・品薄を招きました。2024年夏には店頭在庫の薄さが話題になり、消費者心理が先行して買いだめが波及した地域もあります。こうした前年の不安定さが、2025年の新米シーズン入り直前まで価格・在庫感に影響を残しました。0
一方で、政策・統計面では米の輸入・在庫の制度が安定装置として機能しています。日本はWTOの取り決めに基づくミニマムアクセス(TRQ)として、約68万2千トン(精米換算)を毎年輸入しています。2024/25年度もこの水準を維持ないし増加見通しとされ、構造的に「物理量が全くない」という事態ではありません。ただし、入札スケジュールや流通の目詰まり次第で、店頭在庫の薄さが一時的に顕在化することはあります。1
2. 天候不順と災害が米に与えるダメージ
米は高温・少雨・多雨のいずれにも敏感で、猛暑は白未熟粒の増加や品質低下を、長雨・豪雨は登熟不良や倒伏、病害の誘発につながります。台風の通過が続くと、収穫直前の圃場で倒伏が広がり、刈り取り効率と品質に影響します。2024年の猛暑・豪雨リズムの影響は、2025年の価格形成にも波及しました。足元の価格は2025年夏時点で高止まりが指摘され、5kgで4千円台という報道も見られます。2
もっとも、2025年作の作柄自体には「回復寄り」とする見方もあり、耕地面積の戻りや天候次第では品薄感の緩和が見込まれる、との国内報道も出ています。したがって「不足=絶対量がない」というより、タイミング・品質ミックス・流通の偏りが家計に“足元の高さ”として映っていると理解すると良いでしょう。3
3. 令和の米不足が「平成」と違う点
1993年の米不足は記録的冷夏が直接引き金で、全国作況指数は74という戦後最悪レベルでした。一方、令和の局面は猛暑や豪雨など極端現象の頻度増に加え、生産調整や高齢化、需要の季節偏在、在庫と流通のタイムラグなど、複数要因が絡む“複合型”。結果として、物流や入札のタイミングで局所的に“棚が薄い”現象が起こりやすいのが特徴です。比較の詳細は次記事②でも扱いますが、構造面の違いが2025年の体感を左右しています。4
4. 価格はなぜここまで上がるのか
価格を押し上げるのは、①作柄・品質の不確実性(上位等級比率の変動)、②小売の仕入れコストの上昇、③為替やエネルギー・包材コスト、④期待・心理の先行—の相乗効果です。2025年夏時点の店頭・相対価格は高止まりの報が相次ぎ、相場的にも60kgあたり2万6千円台といった高水準が示されています(市況レポート)。5
ただし、国のTRQ輸入(約68万トン)や民間の在庫、年度後半の新米出回りが進めば、需給は徐々に均衡に近づく公算です。過度な買いだめは逆効果で、価格のボラティリティを高めかねません。6
5. 政策と輸入:安全弁としてのTRQとSBS
日本のコメは「国家貿易」の枠組みで、WTOのTRQ:約68万トンをMAFF(農水省)が調達。OMA(通常入札)とSBS(同時売買)の二本立てで運用され、テーブルライス用途のSBS枠、業務・加工向けのOMA枠などに配分されます。2025年の年央レポートでも、24/25年度輸入見込みは約70万トン規模との見通しが示されました。必要に応じ備蓄米の放出や枠拡大の議論が行われることもあります。7
6. 家計と食卓を守る実践策(すぐできる対処)
- 買い方: まとめ買いよりもローリングストック。普段使いの銘柄を2袋体制にして、古い方から消費→補充。
- 保存: 高温期は冷蔵保存(野菜室)か密閉+冷暗所。長期は小分け冷凍の選択肢も。8
- 炊き方: 等級ミックス時は吸水短め+水量やや少なめで粒感を確保。古米ブレンドは浸水を長めに。
- かさ増し: もち麦・雑穀・押し麦・切り干し大根戻し汁などで食感と栄養を底上げ。
- 品薄時の代替: パックご飯・アルファ米・米粉パン・うどん等を一時的に併用(非常食も兼ねる)。
7. 先読みの視点:2025年産の見通し
足元では、2025年産の作付け面積回復観測や天候次第で品薄感が緩む可能性も指摘されています。もっとも、台風・豪雨の頻度やコースは年ごとに異なり、局地的な被害が出れば地域差は残ります。市場は新米の出回り・等級比率・業務筋の引き合いで敏感に反応するため、一時的な価格波乱は想定内として備えるのが現実的です。9
8. まとめ
2025年の米不足感は、前年度の猛暑・豪雨の尾を引く品質・在庫面の不確実性、流通のタイミング、心理の先行が重なった“複合型”。輸入(TRQ)や備蓄は安全弁ですが、短期的な店頭の薄さや価格の振れは避けがたい局面があります。消費者としてはローリングストックと保存・炊飯の工夫で賢く乗り切りつつ、新米の出回り状況を見極めていきましょう。10
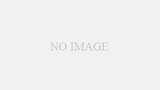

コメント