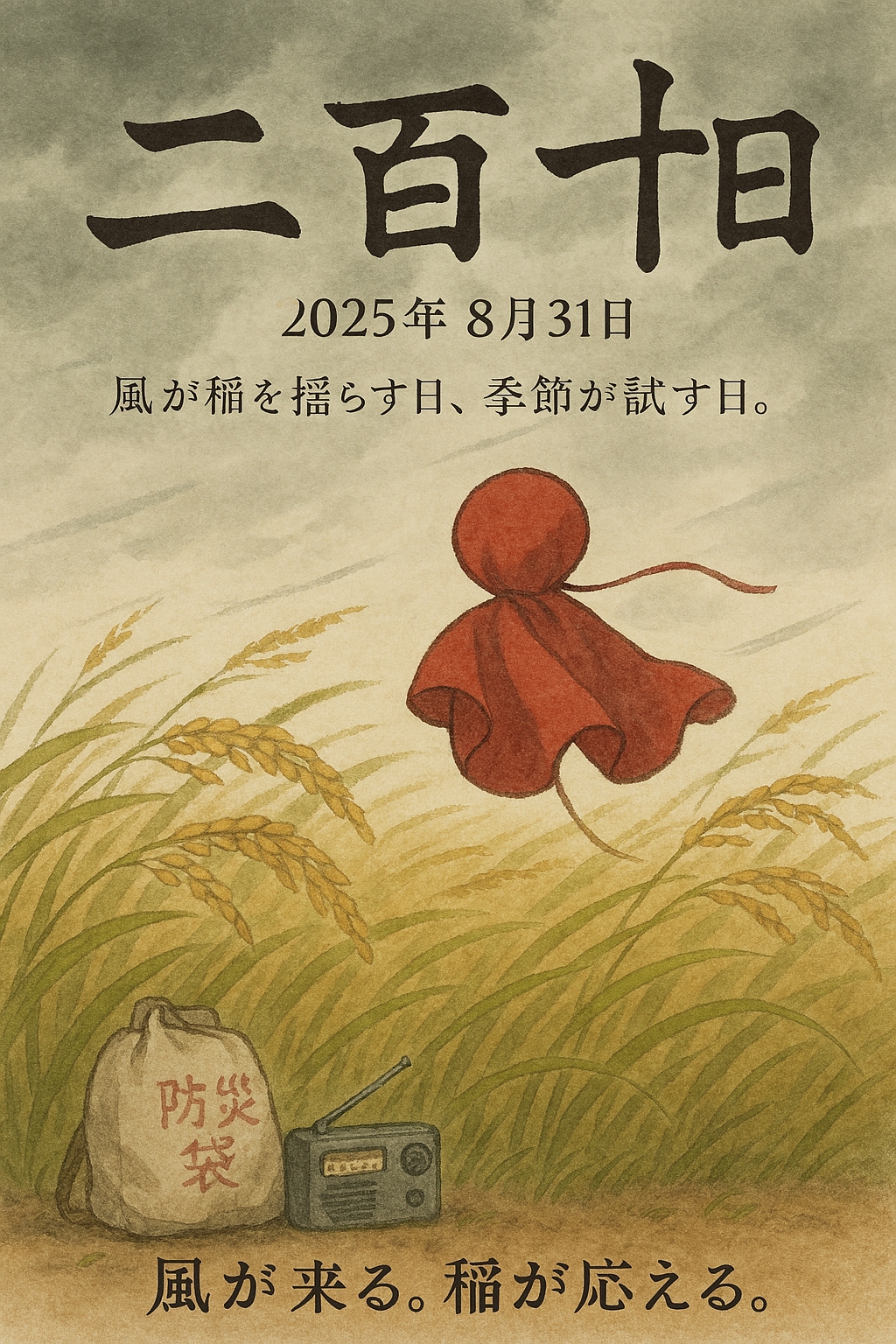
tekowaです。
二百十日(にひゃくとおか)は、昔から「台風の厄日」として農家に警戒されてきました。 では、本当に二百十日前後は台風が多いのでしょうか?
この記事では、昔の経験則と現代の気象学を比較しながら、その理由を解き明かします。
二百十日と台風の関係
二百十日は立春から210日目、おおよそ9月1日前後にあたります。 この時期は、日本列島周辺で台風の接近数が年間で最も多い時期です。
昔の経験則
江戸時代や明治時代、気象予報がなかった頃、人々は長年の経験から「この時期は風が荒れる」と覚えていました。 稲の穂が実る時期に暴風雨が来ると収穫が大打撃を受けるため、農家はこの日を厄日として恐れたのです。
現代の統計で見る台風ピーク
気象庁の統計によると、日本への台風接近数は8月後半〜9月前半がピークです。 特に9月1日前後は、過去数十年の平均でも接近数が多く、昔の経験則は科学的にも裏付けられています。
気象学的な理由
- 太平洋高気圧の勢力が弱まり、台風の進路が日本列島に向かいやすくなる
- 海面水温が高く、台風が発達しやすい時期
- 偏西風の位置が南下し、台風を本州付近に引き寄せる
二百十日と二百二十日
二百十日の約10日後にあたる二百二十日も、台風注意日とされています。 これは台風の発生・接近が続くためで、農村では両方をセットで警戒しました。
農作物への影響
稲作においては、台風による倒伏(稲が倒れること)や、塩害・冠水などの被害が深刻です。 このため二百十日は、単なる暦上の節目ではなく、実際の農業リスクの高い時期なのです。
まとめ
二百十日が台風の厄日とされるのは、昔の迷信ではなく、気象学的な根拠があることがわかります。 2025年は8月31日が二百十日にあたり、この前後は台風への備えを万全にしておきましょう。


コメント