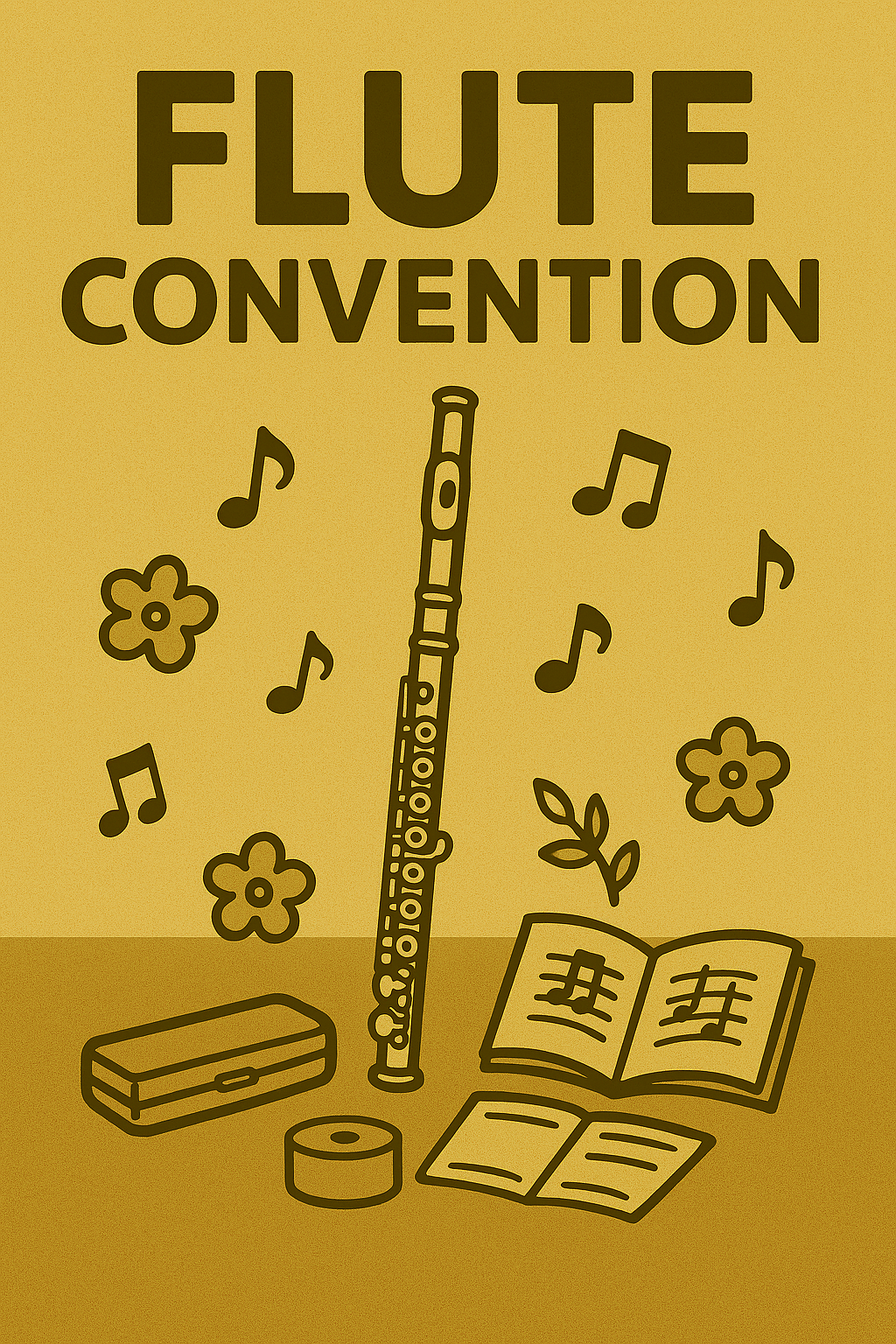
tekowaです。
私たちが耳で聴いている「音」は、実は空気の震え(振動)です。 フルートや他の楽器も、この空気の振動をコントロールして音楽を作ります。
この記事では、音の正体や振動の仕組み、波の性質などを、フルートを例にわかりやすく解説します。
1. 音の正体
音は、物体が振動し、その振動が空気を伝わって耳に届く現象です。 フルートの場合は、息が歌口に当たって発生する振動が管内の空気を揺らし、その揺れが耳に届きます。
2. 振動と波
空気の振動は「波」として進みます。音の場合は縦波と呼ばれ、空気の粒が進む方向に沿って押し縮められたり広がったりします。
3. 周波数と音の高さ
- 振動が速い(高周波数)=高い音
- 振動が遅い(低周波数)=低い音
フルートは、管の長さを変えることで空気の振動の速さを調整し、音の高さを変えています。
4. 振幅と音の大きさ
空気の振動の幅(振幅)が大きいほど、音は大きくなります。 強く吹けば振幅が大きくなり、弱く吹けば小さくなります。
5. 実験で確かめよう
- ゴムひもを弾いて振動の速さと音の高さを比較
- コップに水を入れ、スプーンで軽くたたいて音の高さの違いを調べる
- ペットボトルに息を吹き込み、水の量で音の高さが変わる様子を観察
6. フルートでの応用
フルートの演奏では、息の速さ・角度・量を変えることで振動の特性をコントロールします。 また、音孔を開閉することで管の有効長を変え、振動の速度と波の形を変化させます。
7. 音の響きと倍音
楽器の音色には倍音と呼ばれる複数の周波数成分が含まれます。 フルートは倍音が豊かで、柔らかくも鋭くも表現できるのが魅力です。
8. まとめ
音楽は、空気の震えを感じ、操ることで生まれます。 フルートの美しい音色の背後には、物理学的な波と振動の法則が隠れています。 この仕組みを知れば、音楽を聴く耳も、演奏する楽しみもさらに深まります。
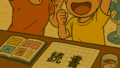

コメント