
tekowaです。
第71回(2025年度)青少年読書感想文全国コンクールの課題図書18冊を、部門別に一気に把握できるまとめです。この記事は、公式の課題図書一覧に基づき、低学年・中学年・高学年・中学生・高校生までを正確に整理。あわせて、本の選び方・学年別の書き方テンプレ・3日で仕上げる進め方・よくあるNGをまとめました。教材としてそのまま使えるよう、見出しと段落構成を整えてあります。保護者・先生のサポートポイントも載せました。
課題図書18冊|学年別の完全一覧
小学校低学年の部(1・2年)
- ライオンのくにのネズミ(さかとく み雪/中央公論新社)
- ぼくのねこポー(岩瀬成子 作・松成真理子 絵/PHP研究所)
- ともだち(リンダ・サラ 作・ベンジー・デイヴィス 絵・しらいすみこ 訳/ひさかたチャイルド)
- ワレワレはアマガエル(松橋利光 文・写真/アリス館)
小学校中学年の部(3・4年)
- ふみきりペンギン(おくはら ゆめ/あかね書房)
- バラクラバ・ボーイ(ジェニー・ロブソン 作・もりうち すみこ 訳・黒須高嶺 絵/文研出版)
- たった2℃で…:地球の気温上昇がもたらす環境災害(キム・ファン 文・チョン・ジンギョン 絵/童心社)
- ねえねえ、なに見てる?(ビクター・ベルモント 絵と文・金原瑞人 訳/河出書房新社)
小学校高学年の部(5・6年)
- ぼくの色、見つけた!(志津栄子 作・末山りん 絵/講談社)
- 森に帰らなかったカラス(ジーン・ウィリス 作・山﨑美紀 訳/徳間書店)
- マナティーがいた夏(エヴァン・グリフィス 作・多賀谷正子 訳/ほるぷ出版)
- とびたて!みんなのドラゴン:難病ALSの先生と日明小合唱部の冒険(オザワ部長 著/岩崎書店)
中学校の部
- わたしは食べるのが下手(天川栄人/小峰書店)
- スラムに水は流れない(ヴァルシャ・バジャージ 著・村上利佳 訳/あすなろ書房)
- 鳥居きみ子:家族とフィールドワークを進めた人類学者(竹内紘子 著/くもん出版)
高等学校の部
- 銀河の図書室(名取佐和子/実業之日本社)
- 夜の日記(ヴィーラ・ヒラナンダニ 著・山田 文 訳・金原瑞人 選/作品社)
- 「コーダ」のぼくが見る世界 ― 聴こえない親のもとに生まれて(五十嵐 大/紀伊國屋書店)
※上記は全国学校図書館協議会(SLA)掲載の公式一覧に準拠しています。出典は記事末に記載。
本の選び方|最短で「書ける本」を決めるチェック
- 気持ちが動くテーマか:主人公に共感できる/怒りや驚きが湧く本は書き出しが速い。
- 事実と感想のバランス:物語型は「心の変化」、ノンフィクションは「発見→自分事化」が軸にしやすい。
- 分量と締切:文字数目安に対し、章の区切りや見出しが取りやすい本を選ぶ。
- 資料の有無:巻末解説・年表・写真があると引用・根拠が作りやすい。
- 読みやすさ:ふりがな/漢字の難度、文のリズムを現学年に合わせる。
3日で仕上げるスケジュール
- 1日目:通読→付箋で「心が動いた3場面」をマーキング。ひと言メモを残す。
- 2日目:テンプレに当てはめて下書き。序論150〜200字/本論600〜800字/結論150〜200字を目安に。
- 3日目:推敲。主語・述語の対応、同語反復、言い切り(〜と思いましたの多用回避)を整える。
学年別・書き方テンプレ
低学年(短め・体験重視)
導入:「この本でいちばんおどろいたのは〜です。」/本論:好き・こわい・かなしい等、はっきり一語感情→理由→自分の体験一つ。/結び:「つぎは〜してみたい。」
中学年(理由づけ・比較を導入)
導入:出会いのきっかけ+簡単な概要。/本論:心が動いた場面を三段で、①場面 ②気づき ③自分の経験・別の本との比較。/結び:「自分はどう行動を変えるか」を一文で。
高学年(問い立て・引用を活用)
導入:本の一文やデータを短く引用して問題提起。/本論:作者の意図推測→根拠(描写・事実)→自分の考え(反論・別解)。/結び:社会や地域への接続(家・学校でできる一歩)。
中学生(構成と論拠を明確に)
導入:テーマの定義(例:貧困、差別、食と身体)。/本論:①事実(作中の具体)②分析(因果・背景)③自分の立場(賛否と代替案)を各段落で。/結び:関連書や資料へ広げる。
高校生(批評的読解・比較考察)
導入:作品の位置づけ(著者背景・時代)。/本論:テーマを二つに分け、複数引用で比較検討。
例:「夜の日記」のアイデンティティ表現と、「銀河の図書室」の図書空間メタファーを対照。/結び:作品の射程を現代社会へ接続し、自分の学びに落とす。
文字数の目安と段落設計
| 部門 | 目安 | 段落構成例 |
|---|---|---|
| 小学生 | 800〜1200字 | 導入150/本論600〜800(2〜3段)/結び150 |
| 中学生 | 1200〜1600字 | 導入200/本論1000(3段)/結び200 |
| 高校生 | 1600〜2000字 | 導入250/本論1300(3〜4段)/結び250 |
仕上げのチェックリスト
- あらすじは全体の3割以内(結末のネタバレは避け、焦点化)。
- 「〜と思いました」の多用を避け、原因・理由・根拠を一文で示す。
- 引用は「二重カギカッコ」と出典頁(可能なら)を明記。
- 段落頭は一字下げ。主語と述語、時制の食い違いを点検。
- 最後にタイトルを付け直す(主張が伝わる具体語を入れる)。
保護者・先生のサポートのコツ
- 読みの前後に3つだけ質問(気になった登場人物/驚いた事実/自分ならどうする)。
- 「言い換え辞典」や付箋を用意し、語彙の幅を広げる支援を。
- 書きはじめは音声入力や箇条書きOK。後で文に整える。
- 清書前に声に出して読む。リズムが悪い箇所が分かる。
まとめ
2025年の課題図書は、フィクションとノンフィクションのバランスがよく、「自分ごととして語れる」題材が揃っています。選書の段階で心が動いた本を選び、テンプレで素早く骨格を作り、3日スケジュールで仕上げれば、締切前でも十分間に合います。この記事が、家庭・教室・図書室での実践の土台になれば幸いです。
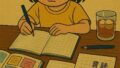

コメント