
tekowaです。
「聴こえない」と「聴こえる」のあいだで育つ子どもたちがいる。彼らはCODA(コーダ)——聴覚に障がいのある親(ろう者)を持つ、聴者の子どもである。
『「コーダ」のぼくが見る世界 ― 聴こえない親のもとに生まれて』は、著者・五十嵐大が、自身の経験を土台に“二つの世界”を行き来しながら見えた社会の景色を、率直な言葉で綴ったノンフィクションだ。十代の読者にとっては、多様性・家族・言語・コミュニケーション・権利といったテーマが一冊に凝縮された学びの入口になる。
本の情報(課題図書・基本データ)
- タイトル:「コーダ」のぼくが見る世界 ― 聴こえない親のもとに生まれて
- 著者:五十嵐 大
- 出版社:紀伊國屋書店
- 対象:高等学校の部(2025年 課題図書)
あらすじ(ネタバレなし・要点だけ)
著者は、ろうの母と、後に聴力を失った父のもとで育った。家庭の第一言語は手話。幼いころから病院や役所で「通訳」を担い、ときに大人の社会の“段差”に直面する。学校に行けば、音声日本語の世界。家では手話が自然体。
二つの言語・文化を行き来する日々で、彼は次第に気づく——困るのは「聴こえないこと」そのものではなく、社会側が整っていないことだ、と。
本書は、身近な出来事(手話での親子のやりとり、病院での場面、映画やメディアの表現、学校でのまなざし)を通し、コーダとしての揺れ・誇り・違和感を丁寧に見つめ直す。読後には、“聞こえる/聞こえない”の二分法を越える視点が手に入る。
テーマ深掘り|この本が“刺さる”理由
1)家族は最初の「言語共同体」——手話が教えてくれること
手話は単なる身振りではない。文法・語彙・比喩・リズムを持つ言語だ。著者の家庭では、表情・視線・身体の動きが豊かなニュアンスを伝える。音声言語では取りこぼしがちな情感や、間(ま)の意味がくっきり立ち上がる。
この視点に立つと、「手話がわからない多数派の社会」こそバリアであり、当事者の「努力不足」ではないことが見えてくる。
2)“ヤングケアラー”のグラデーション——支え/担わされる の線引き
子どもが親の通訳をする——それは温かい家族の協力にも、過剰な負担にもなりうる。著者は、その曖昧な境界を体験として語る。読者が自分事に引き寄せる入口はここだ。
☑︎ 家庭で「自分だけが担っている役割」はないか。
☑︎ それを軽くできる制度や周囲の助けはあるか。
“頑張りで穴埋めする”のではなく、社会の側の設計に視線を向ける態度が身につく。
3)「感動ポルノ」への違和感——表象の問題
障がい者やコーダの物語が、しばしば「頑張っていて感動した」で終わってしまう。著者は、そこに潜む消費のまなざしを指摘する。求められているのは涙ではない。対等な関係とアクセシビリティだ。
読者は“いい人ぶる”読書から卒業し、構造を変える想像力へ踏み出せる。
4)二つの世界を行き来する知性——翻訳者としてのコーダ
コーダは「通訳」を担うことで、自然とメタ認知(メタ視点)を鍛える。他者の立場に立ち、文脈を整え、感情を害さぬよう言い換える。これは将来どの進路でも武器になる。
本書は、弱さや困難を「スキル」に変換するプロセスの手本でもある。
キーワード&モチーフ(感想文の“芯”にできる)
- ☑︎ CODA(コーダ):ろう親を持つ聴者の子ども。文化と言語の二重性。
- ☑︎ 手話は言語:表情・空間・手指の位置が文法的意味を持つ。
- ☑︎ アクセシビリティ:字幕・要約筆記・手話通訳・制度設計。
- ☑︎ ヤングケアラー:支援が必要な「家庭内の通訳・介助」の線引き。
- ☑︎ 表象(メディア):感動の消費ではなく、対等な関係へ。
用語ミニ解説(本文理解を助けるショートノート)
- ろう文化:“聞こえない”ことを障がいでなく文化的アイデンティティとして肯定する考え方。
- 手話言語と音声日本語:言語構造が異なるため、逐語の「直訳」ではなく、文脈を読み替える翻訳が必要。
- コミュニケーション権:情報へアクセスし、意思を伝える権利。教育・医療・行政での保障が鍵。
読後に考える——「聞こえる私/聞こえない私」を超えて
本書が問いかけるのは、当事者だけの問題ではない。
社会の多数派(聴者)が“努力を分配する番”なのだ。字幕を付ける、口元を見せる、手話を学ぶ、筆談を用意する、黙って相手の手を待つ。ささやかな配慮はコストではなく共生の技術だ。
読後、生活のどこを直せるか——学校・アルバイト先・家族の中で、今日から変えられる習慣を一つ書き出したい。
授業・探究・進路にどう効く?(実用の視点)
探究・プロジェクト学習
- ☑︎ 校内の「情報保障」調査(掲示・放送・行事)。改善案を提案。
- ☑︎ 手話サークル×放送委員の合同企画(行事の手話・字幕化)。
- ☑︎ 小学校との連携授業:簡単な手話+コミュニケーション権のワーク。
面接・小論文
「自分の当たり前を問い直した経験」として語りやすい。引用→体験→行動→成果の流れで組み立てると説得力が増す。
感想文の作り方|5ステップで迷わない
- 導入:本との出会い(誰の推薦/帯・書影/映画『CODA』からの興味など)。
- 要約:著者の家庭(手話の家)と「二つの世界」を3〜5文で。
- 核:心に残った一場面・一文を1つ選び、自分の体験・価値観で掘る。
- 展開:学校・家・地域での行動宣言(字幕ONで視聴/掲示の点検/会議の要約共有など)。
- 結び:読む前と後で変わった視線+次に学ぶこと(手話・情報保障)。
段落の型:抽象(気づき)→具体(本と自分の場面)→再抽象(社会への視点)でまとめる。
テンプレ例文(写して“自分語”に置換できる雛形)
テンプレA:推薦文400字級
『「コーダ」のぼくが見る世界』は、手話の家で育った著者が、二つの世界を行き来しながら見えた社会の段差を描いた本です。私は「困るのは聴こえないことではなく、社会が整っていないことだ」という指摘に、はっとしました。
読後、私は動画を必ず字幕ONにし、委員会の議事メモを簡潔に共有するようにしました。配慮は“特別”ではなく“技術”だと気づいたからです。多様性を感動で消費せず、関係を変える一歩を踏み出したい人にすすめます。
テンプレB:感想文800〜1200字級
家の第一言語が手話、学校の言語が音声日本語。著者はその間で育った。
印象に残ったのは、役所で子どもの著者が親の通訳をする場面だ。私はこれまで、家の手伝いは善いことだと思ってきた。でも本書は、協力と過剰な負担の境界が曖昧なまま放置されている現実を見せる。
読後、私は学校での放送・掲示を見直した。大切な連絡ほど文字化されていない。そこで学級委員として、放送内容の要点をクラスルームに即日掲載する取り組みを始めた。小さな工夫でも、情報の段差は減らせる。
「聴こえない人の努力」を称えるより、社会が努力を分配する。これが本書から受け取った最大のメッセージだ。二つの世界の橋渡しをするコーダの視線は、私に“自分の当たり前”を疑う方法を教えてくれた。
テンプレC:小論文骨子(問題提起型)
- 主張:アクセシビリティは“善意”ではなく“設計”。
- 根拠1:手話は言語=情報保障の対象。感情の翻訳が必要。
- 根拠2:ヤングケアラー問題——役割の過重化は制度で軽くできる。
- 提案:校内情報の字幕化・要約共有の運用。行事の手話・字幕。
- 結論:「多数派が努力を分配する」文化の醸成へ。
失敗回避チェックリスト
- ☑︎ あらすじは400字以内。場面の羅列はしない。
- ☑︎ 引用は短く(10〜20字)。必ず「自分の理由」を添える。
- ☑︎ 「感動した」で終わらせない。行動か提案で締める。
- ☑︎ “かわいそう”の語を安易に使わない(表象の問題に自覚的である)。
保護者・先生向けメモ(伴走のコツ)
- ☑︎ 「どこに線を引いた?」と尋ねる。要約より理由を聞く。
- ☑︎ 行動宣言を一つ決める(字幕ON習慣/掲示の点検/手話の基本語)。
- ☑︎ 本人の経験と社会制度をつなぐ視点を促す。
まとめ|“聴こえる/聴こえない”を越えて、生きやすい社会へ
本書は、当事者の物語でありながら、読者一人ひとりの生活を変えるヒントに満ちている。
配慮は特別ではない。技術であり、設計であり、文化である。
感想文は「いい話だった」では終わらない。あなたの学校・家庭・街を少し良くする実践に結ぶとき、読書は力になる。ページを閉じたあと、まずは字幕をONに——そして、次の誰かの声に耳を澄ませよう。

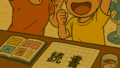
コメント