
tekowaです。
学校や家庭で当たり前だと思っていたことが、実は社会の仕組みによって大きく左右されているとしたら——?
『子どもたちの階級闘争』は、フランスの社会学者が実際の教育現場を通して描いたノンフィクション。
学びのチャンス、進路の選択、家庭環境の違いが、子どもたちにどう影響するかを丁寧に追いかけ、“教育と社会の不平等”を明らかにする。
難解に思えるテーマだが、高校生にこそ必要な「社会の見方」を与えてくれる。
ここでは、感想文に使えるポイントやテンプレまでをまとめた。
本の情報(課題図書・概要)
- タイトル:子どもたちの階級闘争
- 著者:クリスティアン・ボルタンスキー(翻訳:日本版)
- 出版社:みすず書房
- 対象:高校生(2025年課題図書)
- テーマ:教育格差/社会不平等/家庭環境/進路と将来/社会学の視点
あらすじ(要点のみ・ネタバレなし)
フランスの学校で、異なる家庭環境の子どもたちを追った調査から見えてきたのは、「家庭の経済力や文化資本が進学・将来に大きく影響する現実」だった。
裕福な家庭の子は塾や習い事、文化的な体験に恵まれやすい。一方、労働階級の家庭では進学が難しく、早くから働きに出る選択肢を迫られることもある。
この構造は偶然ではなく、社会の仕組みがつくりだした“見えない壁”なのだ。
著者は子どもたちの声を丁寧に拾い、教育制度と社会の不平等を浮き彫りにしていく。
感想文で書きやすいポイント
1)教育のチャンスは平等か?
「がんばれば報われる」と言われるが、スタート地点が違えば努力の意味も変わる。
この点を自分の学校生活と比較すると書きやすい。
2)日本社会との比較
フランスの事例だが、日本でも塾・習い事・受験制度に「格差」が見える。
身近なニュース(教育費・少子化・進学率)と結びつけると内容が深まる。
3)“努力”の意味を考える
努力は個人の問題ではなく、社会の仕組みと関係している。
「努力すればいい」という言葉の裏にある構造を問うのが本書の核心。
キーワード(感想文の軸にできる)
- ☑︎ 階級・格差
- ☑︎ 教育の不平等
- ☑︎ 家庭環境と進路
- ☑︎ 努力と構造
- ☑︎ 社会の仕組み
感想文の書き方(5ステップ)
- ① 本を選んだ理由(教育に関心/ニュースとのつながり)
- ② 要約(子どもたちの現状と階級差の問題)
- ③ 印象に残った点(努力と格差の関係など)
- ④ 自分の生活や学校での実感と比較
- ⑤ 結論(どんな社会が望ましいか/自分ができること)
推薦文・感想文テンプレ(例文)
例文(400字級・推薦文向け)
『子どもたちの階級闘争』は、家庭の違いが子どもたちの進路にどのように影響するかを描いた本です。
私は「努力すれば報われる」という言葉の裏にある現実を知り、はっとしました。
塾に通えるか、家でどんな会話が交わされるか、そうした違いが大きな差を生むのです。
この本を読んで、自分の努力だけでなく、社会全体の仕組みを考えることが大切だと感じました。
教育や社会に関心を持つ人におすすめしたい一冊です。
例文(800〜1200字級・感想文向け)
「努力すれば報われる」という言葉を、私は今まで信じてきました。
しかし、『子どもたちの階級闘争』を読んで、努力だけでは越えられない壁があることを知りました。
本の中では、家庭環境によって進学できる子とできない子の差が描かれていました。塾に通えるかどうか、家に本があるかどうか、そんな小さなことが積み重なり、将来の選択肢に大きな影響を与えるのです。
私はこれを日本の教育と重ねました。周りでも、塾や習い事に通えるかどうかで成績に差が出ています。家庭の経済力が、子どもの「努力の成果」にまで関わっているのだと思いました。
この本を読んでから、私は「努力がすべてではない」ということを理解しました。社会の仕組みを変えていく視点を持つことが、次の世代の未来を守ることにつながるのだと思います。
読後、私はニュースを見る目も変わりました。教育費や格差について報じられるとき、自分もその社会の一部だという自覚を持ちました。
努力と社会の関係を考えるきっかけになる一冊です。
まとめ|「努力」と「社会」をつなぐ視点を持つ
『子どもたちの階級闘争』は、高校生に「努力だけでは説明できない社会の現実」を教えてくれる本だ。
感想文では「自分の生活との比較」「ニュースや社会問題との関連」を組み込むと内容が深まりやすい。
努力を軽視するのではなく、努力を正しく生かせる社会とは何かを考えること。
それが、この本を読む意味であり、高校生の読書感想文にふさわしいテーマになる。
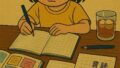

コメント