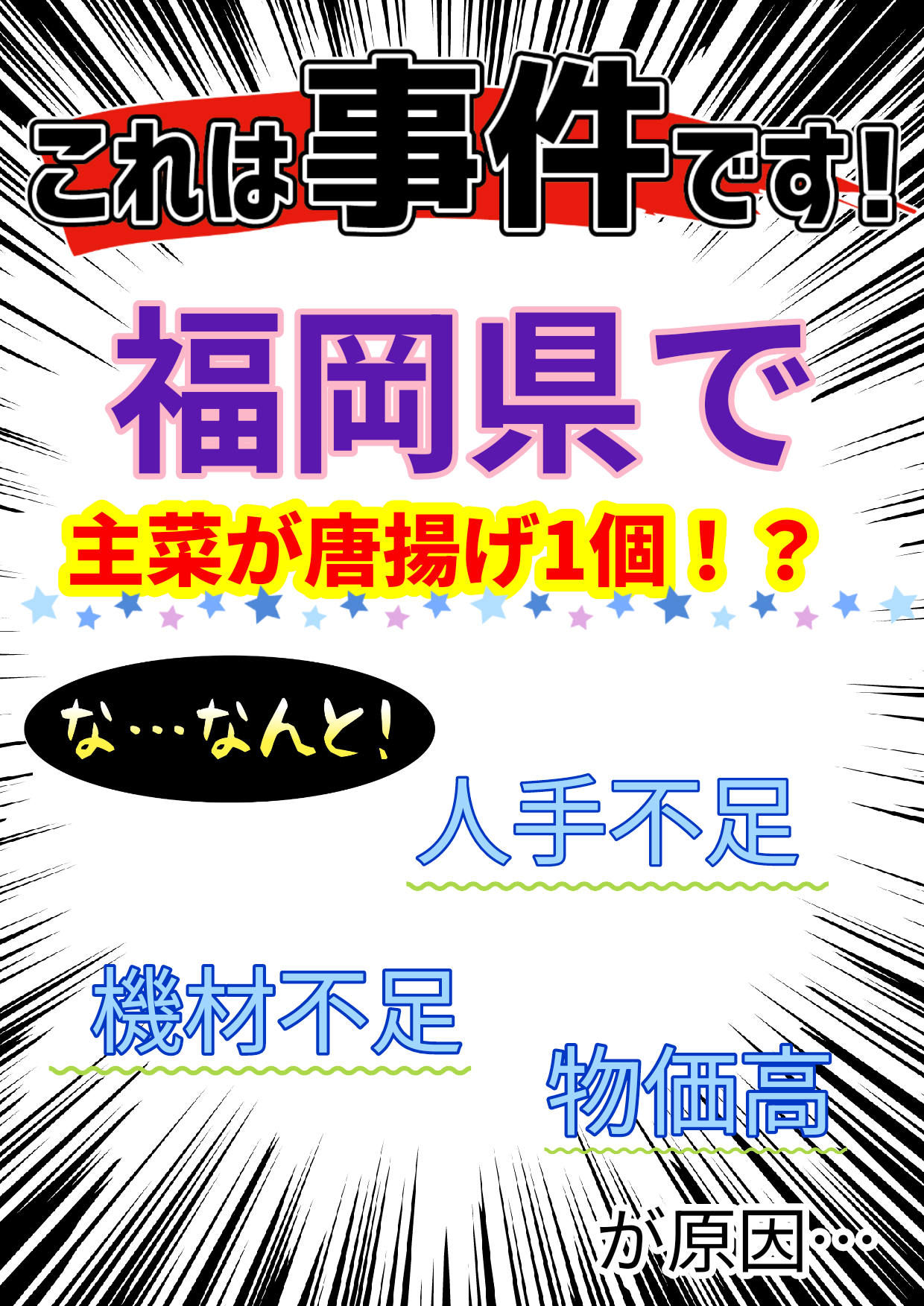
tekowaです。
小学校の給食で主菜が“唐揚げ1個”の写真が拡散し、SNSで大きな議論に。「子どもがかわいそう」「栄養は?」という不安の一方で、現場の声からは人手不足・設備制約・物価高騰が重なった厳しい状況が見えてきます。この記事では炎上の要点となぜ起きたのかをコンパクトに整理します。目次
炎上の要点:何が問題視された?
- 見た目のインパクト:主菜がひと口サイズでボリューム感に欠ける。
- 栄養バランスの不安:たんぱく質や鉄が足りないのでは?という声。
- 運用判断への疑問:なぜその献立で提供されたのか、説明が不足。
「手抜きでは?」という感情的反応が起点。しかし、現場のオペレーションの限界も無視できません。
なぜ“唐揚げ1個”になったのか(3つの背景)
1)人手不足:大量調理は“人力”の積み重ね
下処理・加熱・急冷・配缶・洗浄…どの工程も人手が必要。採用難や高齢化、季節の繁忙で品数やサイズの縮小が起こり得ます。
2)設備・衛生の制約:作れるもの・数に限界
釜やスチコンの台数・能力、衛生基準の厳格化は献立選択に直結。安全最優先で工程を減らす判断が発生します。
3)物価高騰:単価の中で“厚み”が削られる
油・肉・魚・調味料までコスト増。品目・量・回数のどこかを削る必要が生じ、結果として主菜が小さくなるケースも。
重要:これは「誰かの怠慢」ではなく、構造的な制約の表面化。短期のしのぎと中長期の再設計が同時に必要です。
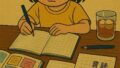
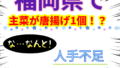
コメント