
tekowaです。
ふわりと揺れるやさしい光。 夏祭りの夜、道を照らす提灯の灯りは、どこか懐かしくて、あたたかく感じます。
でもこの「提灯」、どうやってできてるの? 中の灯りは昔と今でどう違う? 今回は、日本の伝統的な照明器具である「提灯」にスポットを当て、構造・灯り・進化の3視点からひもときます。
提灯の基本構造|和紙×骨組みのチームワーク
提灯はおおまかにいうと、以下のようなパーツから成り立っています。
- 骨組み:竹や針金でできた円筒状のフレーム
- 貼り紙:薄くて透ける和紙、もしくはビニール素材
- 火袋(ひぶくろ):火を入れる空間
- 持ち手・吊り下げ具:手持ち型・吊るし型がある
たたむことができる「蛇腹式」の提灯は、携帯性に優れ、祭りや神事で広く使われています。
昔の灯り:ろうそく・油・火種の工夫
昔の提灯の光源は、ろうそくや菜種油などを使った火の灯りでした。
火が風で消えないように、骨組みと紙で囲んで風よけ+拡散効果を実現していたのです。
和紙は適度に光を透過し、光をやわらかく広げてくれるため、照明器具としても非常に優秀。暗がりの中でも目が疲れにくいとされています。
今の灯り:LEDとろうそく、どう違う?
現代の提灯は安全性を考慮して、LEDタイプが主流になっています。
▼ 比較:LED vs. ろうそく
| 項目 | LED | ろうそく |
|---|---|---|
| 明るさ | 安定して明るい | ゆらぎがある |
| 安全性 | 高い(熱を持たない) | 火事のリスクあり |
| 雰囲気 | クール・現代的 | あたたかみ・風情 |
イベントではLEDが安心、家庭用や茶室ではあえてろうそくを使うことで“揺らぎの美”を感じる演出もあります。
提灯の種類と使い分け
実は「提灯」とひとくちに言っても、いろいろな種類があります。
- ・祭礼用:神輿や山車に取り付ける大型タイプ
- ・家紋入り:お盆や葬儀で使用する家族用提灯
- ・装飾用:イベント・飲食店などで使うカラー提灯
- ・小型携帯型:手持ち式の蛇腹タイプ
地域によって形や模様も異なり、提灯を見れば「どこの祭りか」わかることもあります。
ちょこっと観察ヒント💡
・紙製提灯とビニール製で、光の広がり方にどんな違いがあるか? ・LEDの色(白/電球色/キャンドル型)で雰囲気がどう変わるか? ・手作りミニ提灯キットで構造を実際に組んでみるのもおすすめ!
まとめ|提灯は“和の照明デザイン”の結晶
提灯は単なる明かりではなく、「風よけ」「光の拡散」「文化的装飾」という多層的な意味を持った、日本独自の照明器具です。
その光は、人の目にやさしく、心にやわらかい印象を残します。 どんなに時代が変わっても、あのやさしい灯りを見たときに感じる“懐かしさ”は、ずっと変わらないのかもしれません。
次回はついに最終回!【昔の子ども遊びを体験して記録】 竹とんぼ、けん玉、紙ふうせん──日本の原風景へGO!
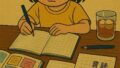

コメント