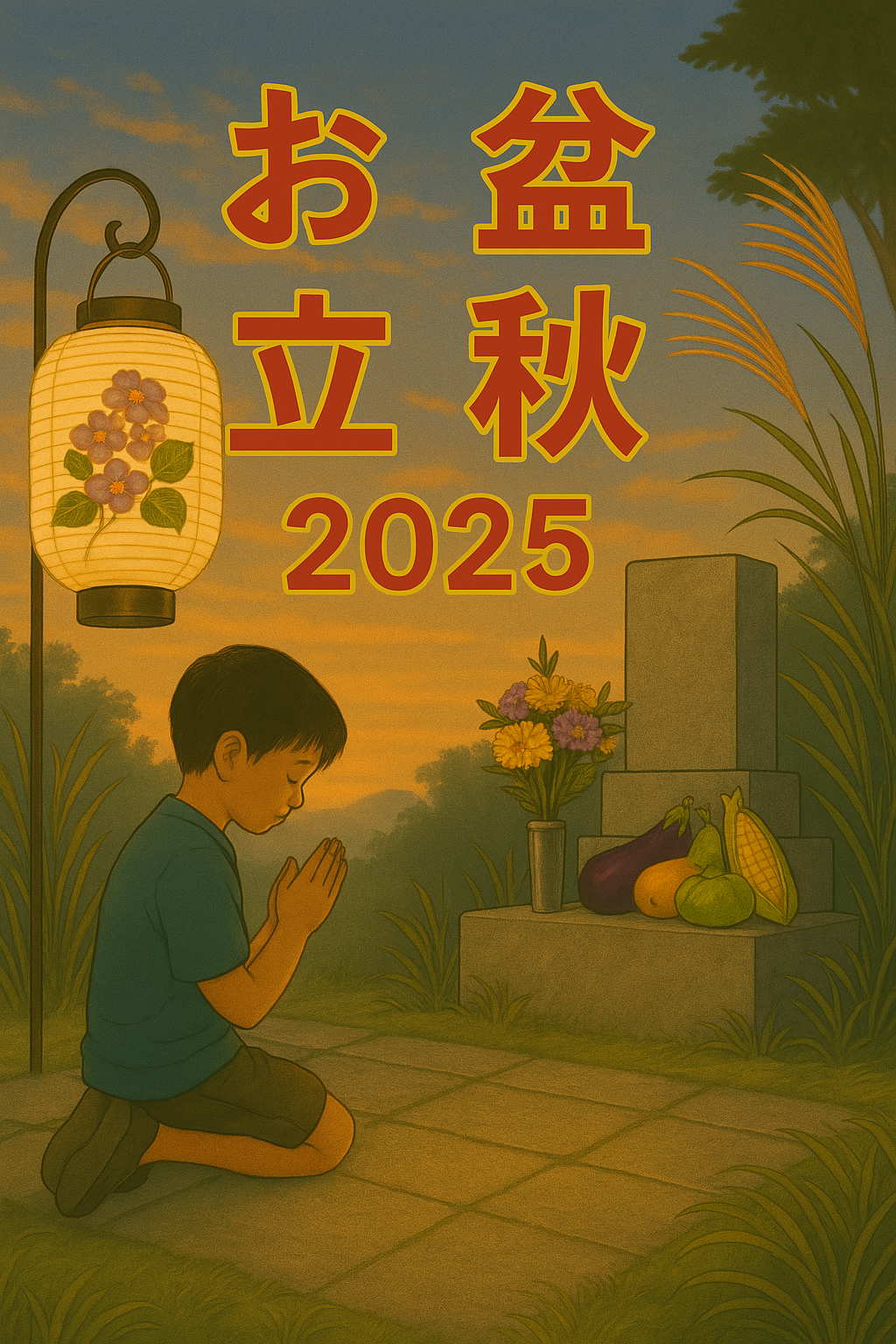
tekowaです。
立秋を過ぎるころ、ふと耳に届く「リーン、リーン」という涼やかな虫の声。昼はまだ暑いのに、音だけ秋が先にやって来たような、不思議な気持ちになりますよね。
この記事では、虫の声と立秋の関係、どんな虫が鳴いているのか、なぜ日本人にとって“秋の音”なのか、その理由をやさしくひも解いていきます。
立秋とは?季節の“節目”
立秋(りっしゅう)は、二十四節気のひとつで「秋の始まり」を意味する日。毎年8月7日頃にあたります。
とはいえ、実際にはまだ猛暑真っ只中。そんな中でも、「音」だけがひと足早く“秋らしさ”を連れてくるのです。
なぜ立秋のころに虫が鳴き始めるの?
理由はシンプルです。秋に鳴く虫の羽化が始まるのが、ちょうどこの時期だからです。
- 夏の終わりに土の中から出てきて、羽化・成熟
- オスがメスを呼ぶために鳴き始める(求愛)
- 夕方~夜に鳴く種類が多く、涼感を与える
コオロギ、鈴虫、キリギリスなど、「秋の虫」と呼ばれる虫たちが、ちょうど立秋を過ぎたころから活動を始めます。
どんな虫が鳴いているの?“秋の虫”たち
1. エンマコオロギ
「リーン リーン」と鳴く、秋の代表格。名前の由来は「閻魔さまのように大きな顔」から。
2. スズムシ(鈴虫)
「リーーーン」という、まるで鈴のような音。涼感の代表的な虫です。
3. マツムシ
「チンチロリン♪」という、軽快で高音の鳴き声が特徴。
4. キリギリス
「ギーッチョン ギーッチョン」とリズミカルに鳴く、おなじみの昆虫。
これらは成虫のオスが羽を震わせて音を出しているもので、それぞれの“声”が自然の秋を彩ります。
日本人と「虫の音」の文化
実は、虫の声を“音楽”や“言葉のようなもの”として捉える感性は、日本人に特有のものとされています。
- ヨーロッパやアメリカでは、虫の音は「ノイズ」扱い
- 日本では、古くから和歌・俳句・童謡に登場
- 平安時代には、虫の声を聞く「虫聴(むしきき)」という風習も
これは、日本語が“高低アクセント”を持つため、虫の声も言語のように感じやすいからとされます(脳科学的にも実証あり)
五感の中で「聴覚」だけが先に秋を感じる
立秋の時期、視覚ではまだ真夏。汗も止まらない。
でも、耳だけが先に秋を受け取ってくれる――それが“虫の音”です。
人間の感覚の中でも、聴覚は季節の変化に最も敏感とされ、「音」から季節を意識する文化はとても豊かな体験です。
虫の声を自由研究にしてみよう!
- 録音して比べてみる:日ごと・場所ごとに違う鳴き方
- 鳴いている時間帯・気温・湿度を記録
- 種類別に観察ノートを作る
- 風鈴や鈴との“音の違い”を比べてみる
身近な場所(公園・庭・畑など)でできる自由研究として、虫の声の観察はとてもおすすめです。
まとめ|“音から始まる秋”を感じよう
立秋が過ぎて、最初にやってくるのは涼しい風ではなく「虫の声」。
その音は、季節の移ろいを静かに教えてくれる“自然からの手紙”のような存在です。
エアコンの音や車の音ばかりではなく、ちょっと耳を澄ませて、虫たちの小さな声に気づいてみてください。
そこには、暦より早く、秋を届けてくれる優しい世界が広がっています。


コメント