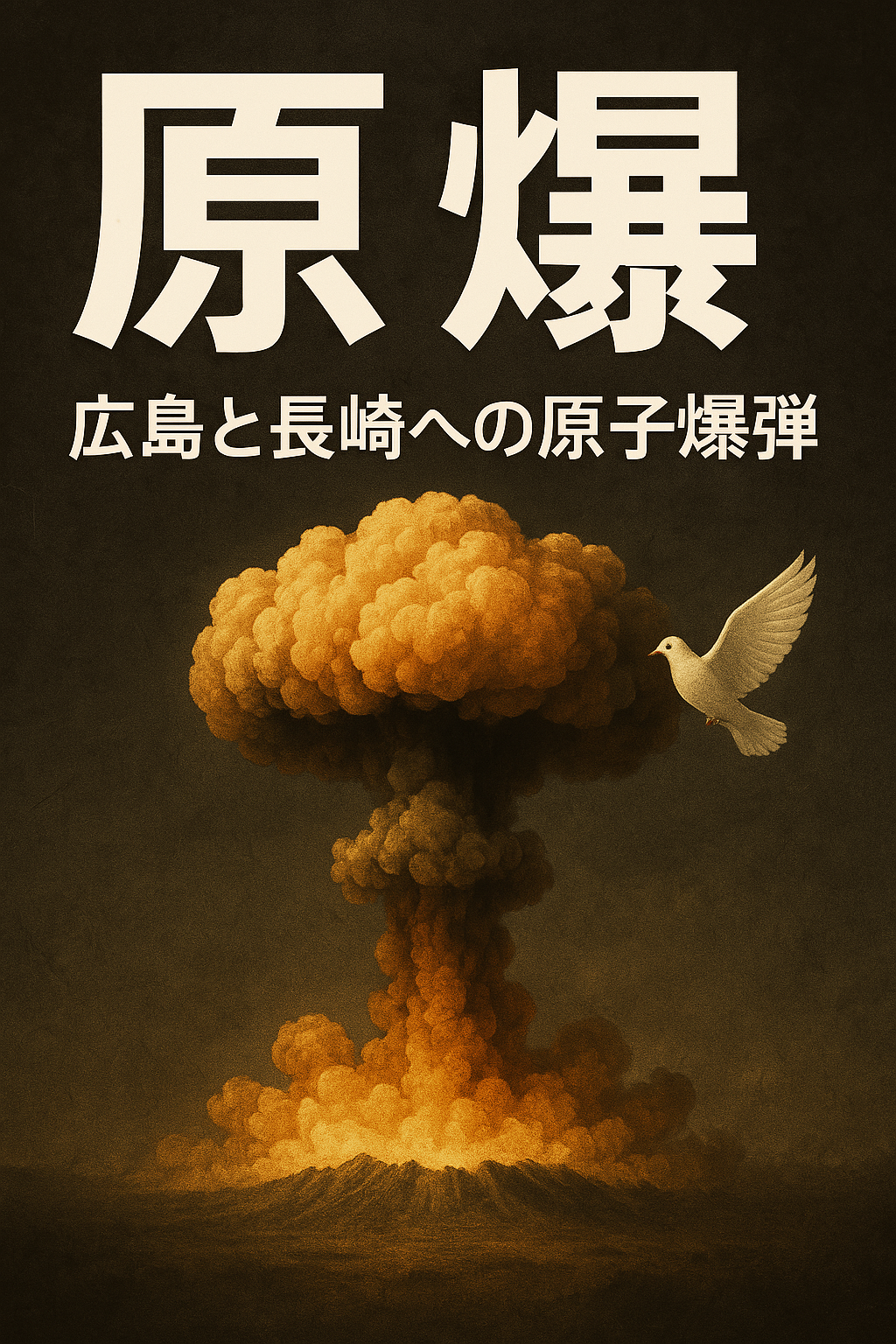
tekowaです。
戦争中、日本のまちには「空襲(くうしゅう)」と呼ばれる爆弾の攻撃がありました。そんなとき、人々は命を守るためにさまざまな工夫をしていたのです。
今回は、防空頭巾(ぼうくうずきん)や灯火管制(とうかかんせい)など、空襲へのそなえについてやさしく紹介します。
1. 防空頭巾ってなに?
防空頭巾とは、空襲のときに頭をまもるための布やわたで作られたカバーです。
爆風やガラスの破片から頭をまもる役割があり、子どもからおとなまで学校や家でかぶっていました。
ふとんのわたをぬって手作りする家庭も多かったそうです。
2. どうやって使っていたの?
・ふだんはかばんに入れて持ち歩く
・空襲警報が鳴ったら、すぐにかぶる
・頭と首のうしろをしっかりおおう形が多い
学校では毎日のように訓練が行われ、すぐに防空頭巾をかぶる練習をしていました。
3. 灯火管制ってなに?
夜になると、町のあかりが「敵に見つかる目印」になってしまうことがありました。
そこで、夜間にはすべての電気や火をけして、まちを暗くする「灯火管制(とうかかんせい)」が行われました。
・家の中のあかりは黒い布でおおう
・街灯も消される
・まっ暗な中を歩くのがあたりまえ
今では考えられないくらいのくらやみの中、人々は静かに生活していたのです。
4. 空襲のときはどうしたの?
空襲警報が鳴ると、人々はすぐに防空壕(ぼうくうごう)と呼ばれる地下の避難所に逃げました。
家の庭に手作りで掘ったり、公園や学校に共同の防空壕が作られたりしていました。
とてもこわくて、暗くて、長い時間じっとしている必要があったのです。
5. 子どもたちの不安と強さ
空襲の音や警報にびくびくしながらも、子どもたちは毎日をがんばって生きていました。
防空頭巾を自分でかぶり、弟や妹の手を引いて逃げる姿もあったそうです。
6. まとめ|身を守る知恵と工夫があった
防空頭巾や灯火管制は、命をまもるために考え出された工夫でした。
戦争がもたらす恐ろしさを知ることで、今の平和な毎日がどれほど大切かがわかります。
これからも「戦争のない社会」を目指して、知ること・考えることを続けていきましょう。
🕊 このシリーズの他の記事も読んでみよう!
→ 第22弾「戦争が残した心の傷~子どもたちのその後~」へつづく

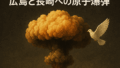
コメント