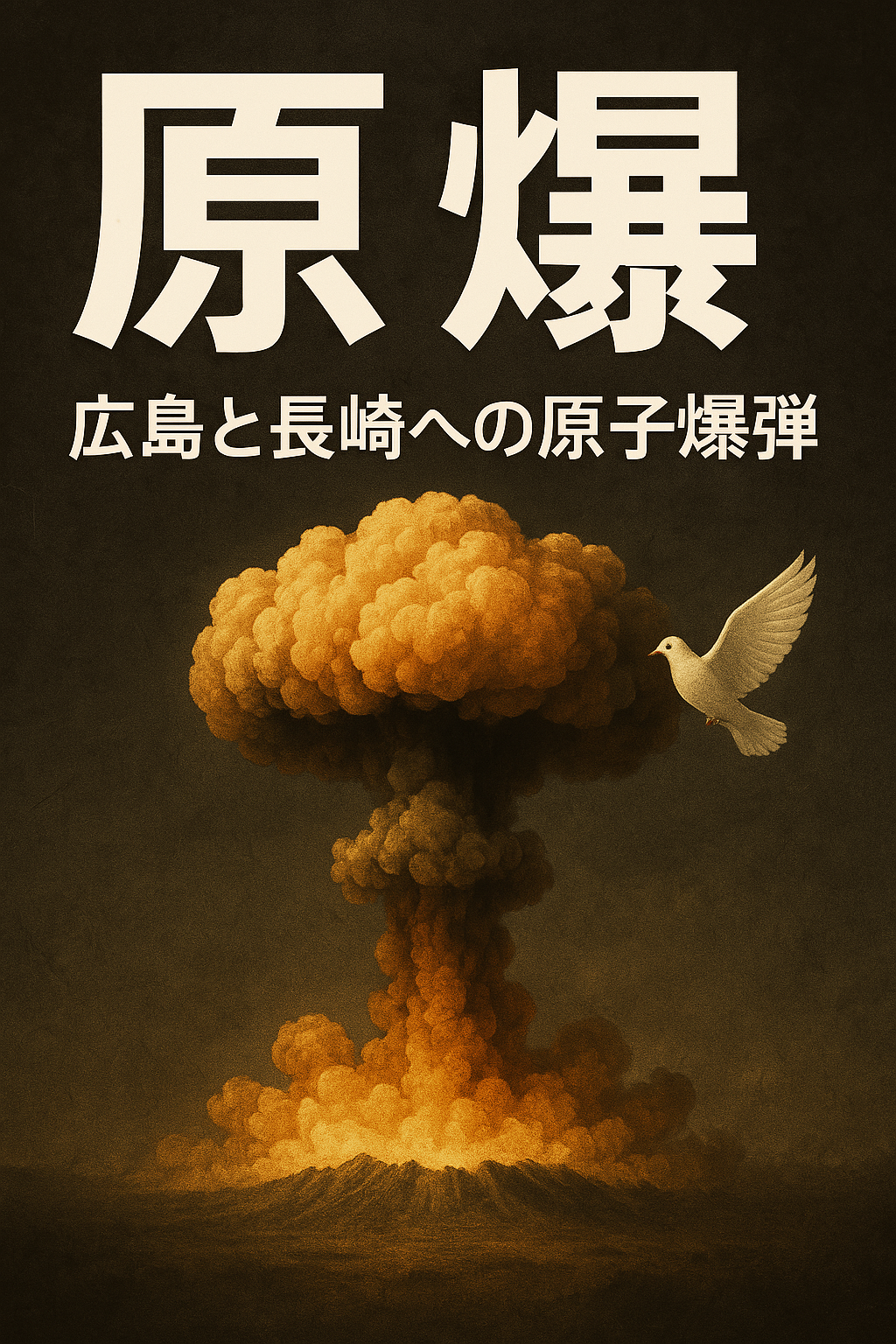
tekowaです。
戦争の時代、大人だけでなく子どもたちも大きな影響を受けていました。なかでも「学童疎開(がくどうそかい)」と呼ばれる、子どもたちだけの避難(ひなん)生活は、とても特別な体験でした。
今回は、戦時中の子どもたちの暮らしや学校生活について、やさしく紹介します。
1. 学童疎開ってなに?
学童疎開とは、戦争で爆弾が落ちる危険があった都会(とし)から、子どもたちを安全な田舎に避難させることです。
とくに小学生の高学年は、先生やクラスの友だちといっしょに団体で地方へ引っ越して、しばらくのあいだ家族と離れて生活しました。
2. どんな生活をしていたの?
疎開先では、地元の人のお家やお寺、学校などに泊まりながら生活をしました。
ごはんを作ったり、薪(まき)を拾ったり、畑しごとを手伝ったりと、今では考えられないようなことも子どもたちの役目でした。
3. 家族と離れるさみしさ
子どもたちはまだ小さくても、家族と離れてくらすことになりました。「お母さんに会いたい」「弟は元気かな」そんな気持ちをかかえながら、毎日をがんばっていたのです。
中には、手紙を書くことだけがたのしみという子も多くいました。
4. 戦時中の学校って?
戦争中の学校では、ふつうの勉強のほかに、「軍事教育(ぐんじきょういく)」と呼ばれる授業もありました。
体をきたえるための運動や、戦争に関する内容を学ぶ時間もあり、今の学校とはかなり違っていました。
5. 空襲で学校に行けない日もあった
爆撃(ばくげき)の危険がある日は、学校がお休みになることもありました。
また、教室が壊れてしまったり、先生が戦争に行ってしまって、授業ができない日もあったのです。
6. 子どもたちのがんばり
つらい中でも、子どもたちは毎日を一生けんめいに生きていました。おとなたちの手伝いをしたり、友だちと支えあったりしながら、希望を失わずにがんばっていたのです。
7. まとめ|子どもたちも「戦争」と向き合っていた
戦争の時代には、子どもも「ただ守られる存在」ではありませんでした。家族や友だちと協力して、たくましく生きる力を身につけていたのです。
私たちは、そんな子どもたちの体験を知ることで、平和の大切さをより深く学ぶことができます。
🕊 このシリーズの他の記事も読んでみよう!
→ 第18弾「戦争とメディア~新聞・ラジオで伝えられた時代~」へつづく
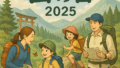
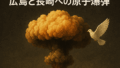
コメント