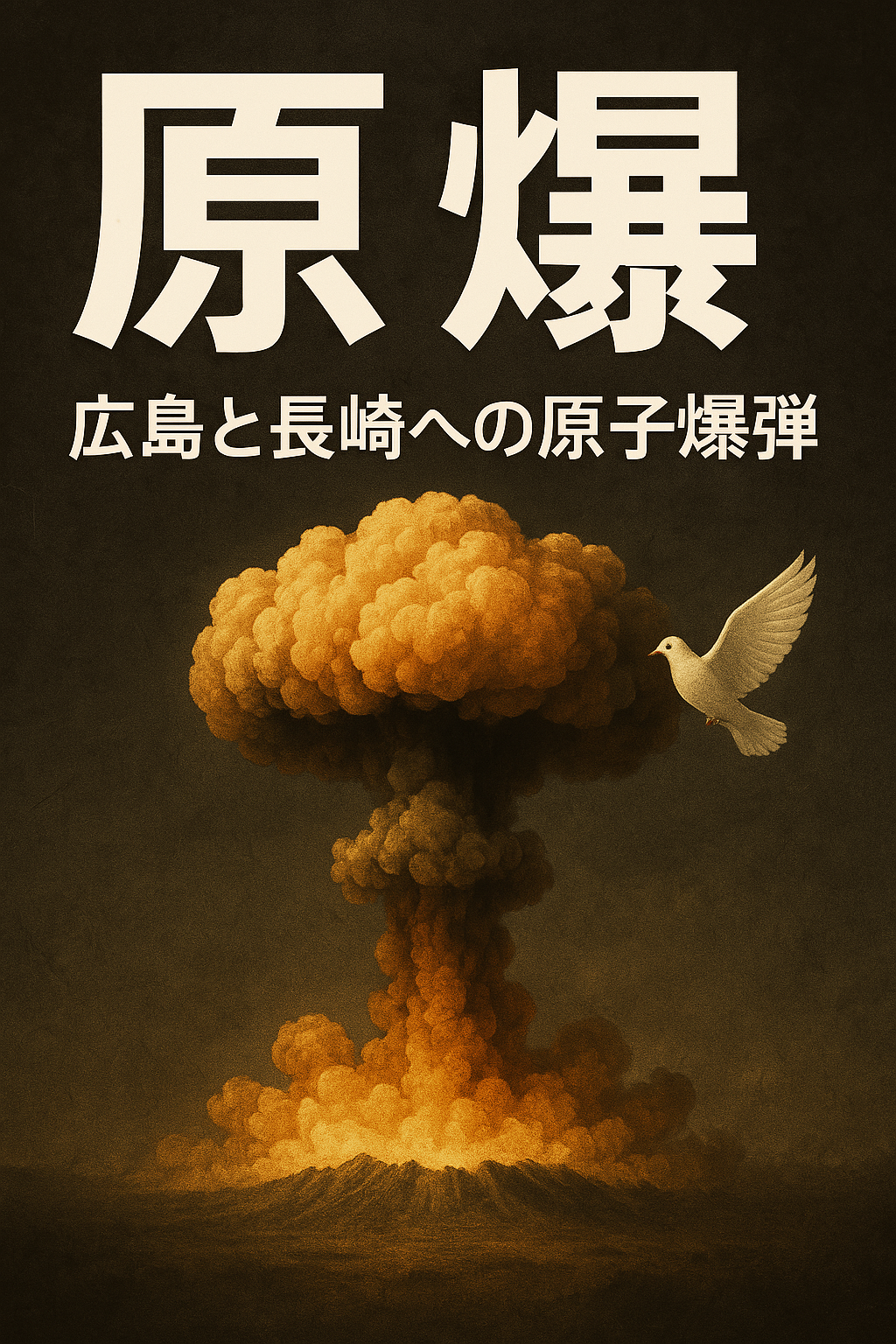
tekowaです。
疎開とは?戦時中の子どもたちの生活と体験をわかりやすく解説
「疎開(そかい)」という言葉を聞いたことがありますか?戦争中、日本では都市部のこどもたちが安全な場所にうつされることがありました。それが「疎開」です。今回は、疎開とはなにか、どんな生活だったのかを、子どもにもわかりやすく紹介します。
1. 疎開ってなに?
疎開とは、戦争中に空襲(くうしゅう)などの危険からにげるために、都市から地方へ人びとが移動することをいいます。
とくに、東京や大阪のような大きな町にすむ子どもたちは、地方の親せきの家や、農村の学校に移されました。これは「学童疎開(がくどうそかい)」と呼ばれ、政府が行ったものです。
2. どうして疎開が必要だったの?
戦争がすすむと、都市部は敵の飛行機による空襲のターゲットになりました。家や学校が爆弾でこわされる危険があったため、子どもたちを安全な場所に移そうという目的で始まりました。
しかし、慣れない場所での生活や、家族と離れることへの不安はとても大きなものでした。
3. どこへ疎開したの?
疎開先は、田舎(いなか)の村や山の中など、空襲が少ないと考えられる場所でした。親せきの家に行く「縁故疎開(えんこそかい)」と、学校ごと地方に移る「集団疎開(しゅうだんそかい)」がありました。
見知らぬ土地に行くことも多く、子どもたちはとまどうこともたくさんありました。
4. 疎開先での生活は?
疎開先での生活は、今とちがってとてもたいへんでした。
- 食べ物がじゅうぶんにない
- 水道や電気がないところもあった
- 農作業を手伝うこともあった
- 学校がなくなり、勉強ができない日々も
それでも、地元の人たちに助けられながら、がんばって生活していたのです。
5. 家族と離れるつらさ
多くの子どもたちは、家族と別れて生活することになりました。お母さんやお父さんに会えないさびしさ、不安、なれない生活。泣きながら夜をすごした子もたくさんいました。
手紙でやりとりしたり、お守りを持って行ったりして、心を落ち着ける工夫もしていたそうです。
6. いい思い出もあった?
すべてがつらかったわけではありません。田んぼや山で遊んだことや、自然の中でのびのびできたこと、地元の友達と仲よくなったことなど、よい思い出も残っている子もいます。
ただし、戦争がもたらした「命を守るための疎開」であったことを忘れてはいけません。
7. まとめ|疎開から学べること
疎開は、戦争が子どもたちの生活にも大きな影響をあたえていたことを教えてくれます。
ふつうに学校に通い、家族とすごすことができるのは、当たり前ではありません。だからこそ、平和のありがたさを考えるきっかけにしたいですね。
🕊 このシリーズの他の記事も読んでみよう!
→ 第7弾「戦時中の食事って?代用食や配給制度の話」へつづく
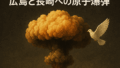

コメント