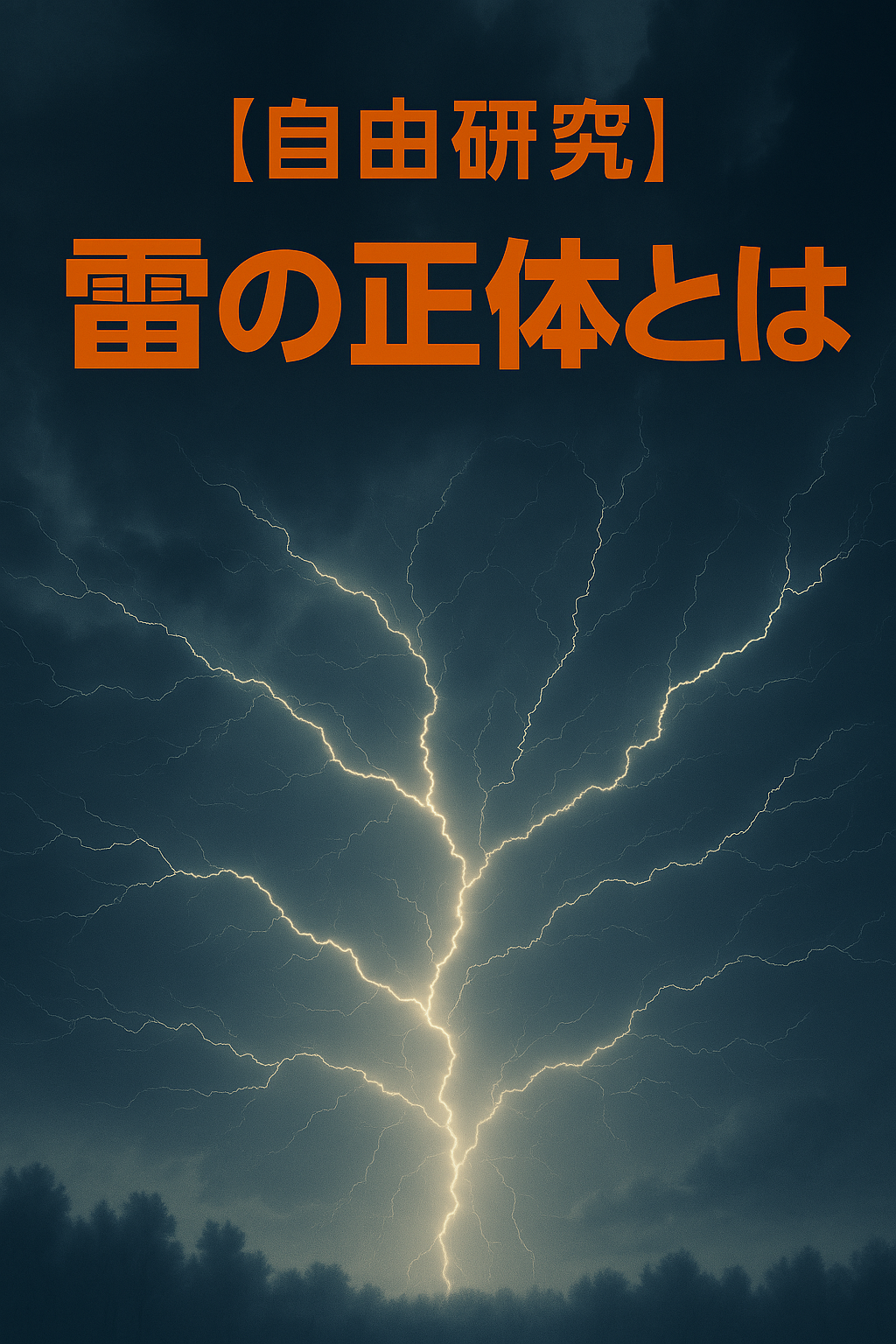
tekowaです。
雷のひみつ(後編)〜自然のふしぎと安全なつきあい方〜
こんにちは!「雷のひみつ(前編)」では、雷がどうして光ったり音を出したりするのか、基本のしくみを学びましたね。
今回はその続きを学んでいきます。雷の電気はどこから来るの? 静電気と関係ある? 落雷から身を守るにはどうすればいいの?など、もっと深く知って、雷と自然のつながりを学びましょう!
雷の正体は「自然の静電気」?
雷の元になる電気――これは私たちの身のまわりでも起きている「静電気(せいでんき)」とよく似ています。
たとえば、冬にセーターをぬいだとき「パチッ」と音がしてびっくりすることがありますよね? あれも空気が乾燥しているときに体にたまった電気が一気に放電(ほうでん)されたものです。
雷も、ものすごく大きな静電気!?
雷は、雲の中で氷のつぶがぶつかり合うことで電気がたまり、限界までたまると「放電(ほうでん)」して雷になるという点で、まさに巨大な静電気!
ふだんの「パチッ」は電気の量が少ないけど、雷はとてつもなく大きなエネルギーを持っていて、ときには数万アンペア(A)もの電流が流れます。
どうして金属に落ちやすいの?
雷は電気が通りやすいもの(=電導性が高いもの)を好みます。
- 金属(かね)
- 水をふくんだ木
- 人の体(約70%が水分)
そのため、高い木や電柱、アンテナ、さらには人間にも落ちる可能性があります。
雷が鳴りはじめたら、金属製の傘やゴルフクラブ、自転車などは近くに置かず、すぐに安全な場所に避難しましょう。
雷から身を守るには?
雷が近づいたとき、どうやって安全を守ればよいかを知っておくことは、とても大切です。
安全な場所
- 家の中(特に木造より鉄筋コンクリートの建物)
- 自動車の中(金属で囲まれているので安全)
- 学校の教室や公共施設の中
危険な場所
- ひらけた広場(自分の体が一番高くなってしまう)
- 水辺・プール(水は電気を通しやすい)
- 高い木の近く
耳をすまして「ゴロゴロ」と聞こえたら、すぐに屋内に避難しましょう。雷は思っているよりも遠くからでも落ちることがあります。
雷のときの合言葉「くもがにがて」って?
雷から身を守るために、小学生に向けた安全な行動の目安「くもがにがて」があります。
く:くも行きがあやしいときは早めに行動!
も:もりや林に近づかない!
が:学校では先生の指示にしたがう!
に:にわか雨に気をつけて!
が:がけや川辺には近づかない!
て:てんきの変化をチェックしよう!
ちょっと楽しく覚えられて、役にも立つ言葉ですね♪
実験してみよう!静電気ミニ実験
おうちでも安全にできる「雷のミニ実験」があります。
●ふわふわティッシュで静電気
- 風船をふくろから出してふくらませます。
- ウールやセーターなどに風船をこすります(約10回以上)。
- 軽くちぎったティッシュに近づけてみましょう。
風船にティッシュがくっつけば、電気がたまった証拠! これが静電気です。
●スプーンと髪の毛でパチパチ実験
- プラスチック製のスプーンを、ドライヤーで乾かした髪の毛にこすります。
- アルミホイルの小さなボールを近づけます。
うまくいくと、アルミが吸い寄せられたり、ポンと跳ねたりしますよ。
このように、雷と同じ「電気の力」が、身近なところでも体験できるんです。
雷と文化のおはなし
雷は、昔からこわい自然現象であると同時に、神さまのしるしとしても考えられてきました。
●ことわざや言い伝え
- 「雷が鳴るとへそを取られる」…子どもにおなかを冷やさないよう注意するための言い伝え。
- 「雷と火事と親父」…昔の三大こわいものとして有名な表現。
●雷神さまの存在
雷の音や光は、雷神(らいじん)さまや風神(ふうじん)さまが太鼓を鳴らしているのだと考えられていたこともあります。雷はただの自然現象ではなく、神話の中にも登場するパワフルな存在だったのです。
自由研究にするときのヒント
「雷のひみつ」は、自由研究のテーマとしてもおすすめです。
●おすすめ構成
- 雷とはなにか?
- 雷のしくみ(前編内容)
- 静電気との関係(後編)
- 安全対策
- 観察日記や天気図との比較
- 身近な実験と結果
- まとめ・感想
「雷がこわくなくなった」「自然ってすごい!」など、自分の気づきを言葉にすると、読む人にも伝わりやすくなります。
まとめ
- 雷は「巨大な静電気」と同じしくみで起こる
- 金属や水は電気を通しやすく、雷が落ちやすい
- 安全な場所に避難するのがとても大事
- 静電気のミニ実験で、雷のしくみを体感できる
- 昔の人も、雷にいろいろな意味を見つけてきた
空の上でひびく「ゴロゴロ」の音には、自然からのメッセージがかくれているのかもしれません。
こわがらずに、正しく知って、安全に向き合っていきましょう♪
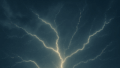
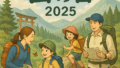
コメント