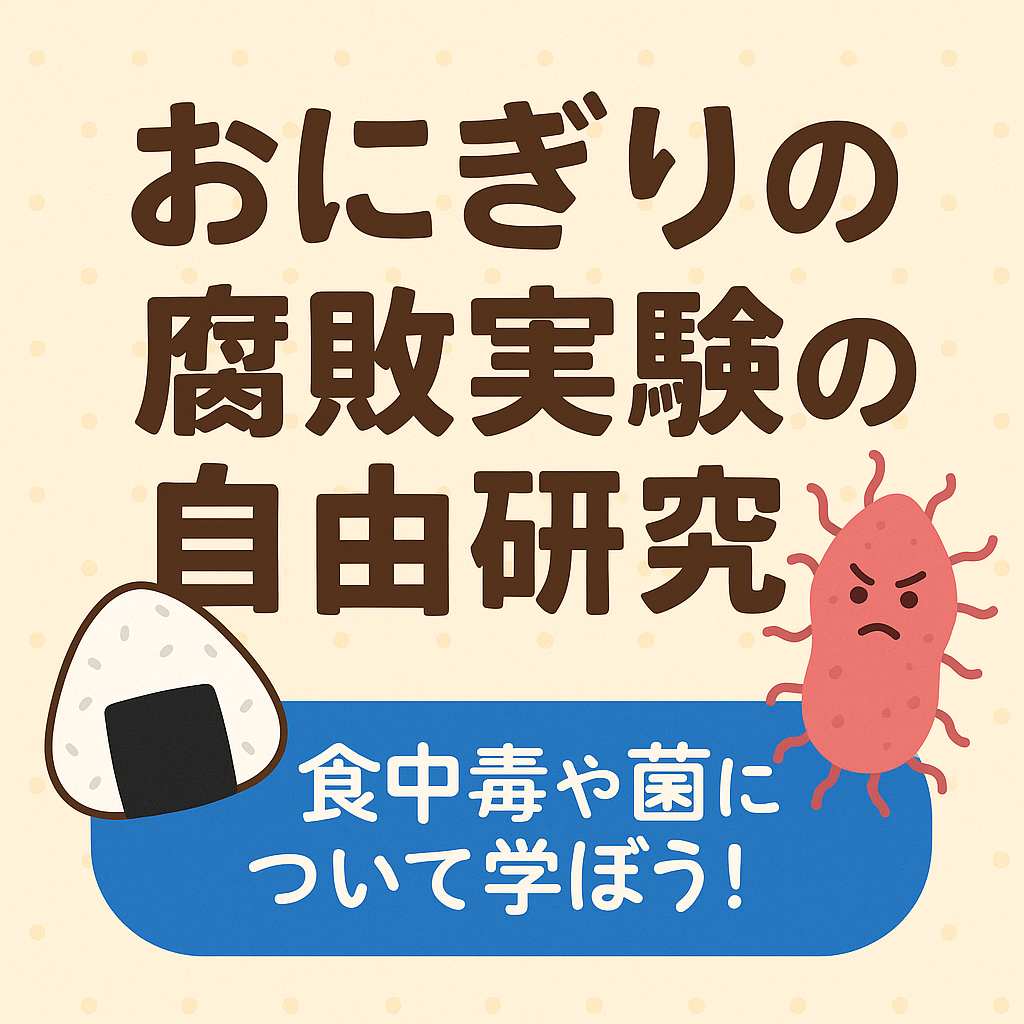
tekowaです。
夏になると、お弁当のおにぎりが腐ってしまった…という話を聞いたことはありませんか?
見た目は同じようなおにぎりでも、「手で握ったもの」「ラップを使って握ったもの」「市販のおにぎり」では、腐る速さやにおいの出かたがちがうかもしれません。
この自由研究では、身近なおにぎりを使って「腐敗の進み方」や「菌のはたらき」について観察・記録していきます。
どうして食べ物は腐るの?
食べ物は空気中の菌(細菌やカビなど)がつくことで、時間がたつと腐っていきます。これを「腐敗」といいます。
とくに夏場は気温や湿度が高く、菌が活発に増える季節です。30℃近くあると、菌の増殖スピードはぐんと速くなります。
私たちの手にもたくさんの菌がいるため、「手で握ること」がおにぎりの腐敗に影響するのかどうかも調べてみましょう。
今回のテーマと実験の目的
テーマ:おにぎりの握り方・保存方法で、腐り方は変わるのか?
目的:食べ物が腐るしくみを学び、どうすれば安全に保存できるかを考える
準備するもの
- 炊きたてのごはん(すべて同じ条件で)
- ラップ
- 市販のおにぎり(コンビニなど)
- ビニール手袋・マスク
- 密閉できる保存容器(観察用)3つ以上
- 温度・湿度を記録できる温度計や観察ノート
- 観察表(自作してもOK)
実験方法
1日目に、以下の3種類のおにぎりを用意します。
- A:素手で握ったおにぎり(手を石けんで洗ってから握る)
- B:ラップで握ったおにぎり(ラップを使って手が触れないように成形)
- C:市販のおにぎり(包装はそのまま、表面の変化だけ観察)
大きさや材料(中身なし)をそろえることで、公平な実験になります。
保存はすべて常温(室温25〜28℃前後)で行い、1日1回観察して記録します。
観察するポイント
観察は1日目から毎日同じ時間に行いましょう。できれば5日間観察します。
注目するポイントはこちら:
- 見た目の変化(色・表面のぬめり・カビ)
- におい(酸っぱい/くさい/なし)
- ごはんのかたさやベタつき
においの強さは、「においスケール」をつけてもおもしろいです(1=においなし〜5=すごくくさい)。
記録のしかた
以下のような表を作って、日ごとに観察内容を記入していきます。
| 日付 | A:手で握る | B:ラップ握り | C:市販おにぎり |
|---|---|---|---|
| 1日目 | 変化なし | 変化なし | 変化なし |
| 2日目 | 表面にぬめりあり、におい少し | 変化なし | 変化なし |
写真を撮っておくと、見た目の変化がわかりやすくなります。
菌について知っておこう
食べ物を腐らせるのは「腐敗菌」や「カビ菌」などの微生物です。
とくに手についている菌は、目に見えないけれど、握っただけでごはんに移ります。
菌は栄養・水分・温度がそろうと一気に増えるため、夏はとても腐りやすい季節なのです。
ごはんには水分もあり、栄養も豊富なので、保存に気をつけないとすぐに菌が増えてしまいます。
保存方法のちがいも注目!
今回の実験は常温保存ですが、冷蔵庫や冷凍庫に入れていた場合はどうなるか?を考えるのも自由研究のヒントになります。
- 冷蔵保存:腐敗スピードはゆるやかになるが、ごはんが固くなりやすい
- 冷凍保存:腐敗しにくいが、解凍時に水っぽくなることがある
ラップや包装材が、菌の付着や空気との接触をふせぐ役割をしている点にも注目してみよう!
安全に実験するために
- においをかぐときは、近づけすぎない
- ぬめりやカビが出たら容器ごと密封して処分
- ぜったいに食べない!
- 手洗いと片づけはていねいに
家族にも協力してもらい、安全に実験しましょう。
前編のまとめと後編への予告
この実験では、ふだん何気なく食べている「おにぎり」が、どのように腐っていくかを毎日観察します。
においやぬめり、カビの出かたなど、変化の様子をしっかり記録していくことで、菌のはたらきや衛生の大切さが見えてきます。
後編では、観察した結果をもとに「どのおにぎりが一番くさりやすかったか?」「どうすれば長もちするのか?」を考えます。
さらに、菌についての知識や、夏のお弁当で気をつけたいポイントもまとめていきましょう。
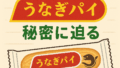
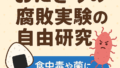
コメント