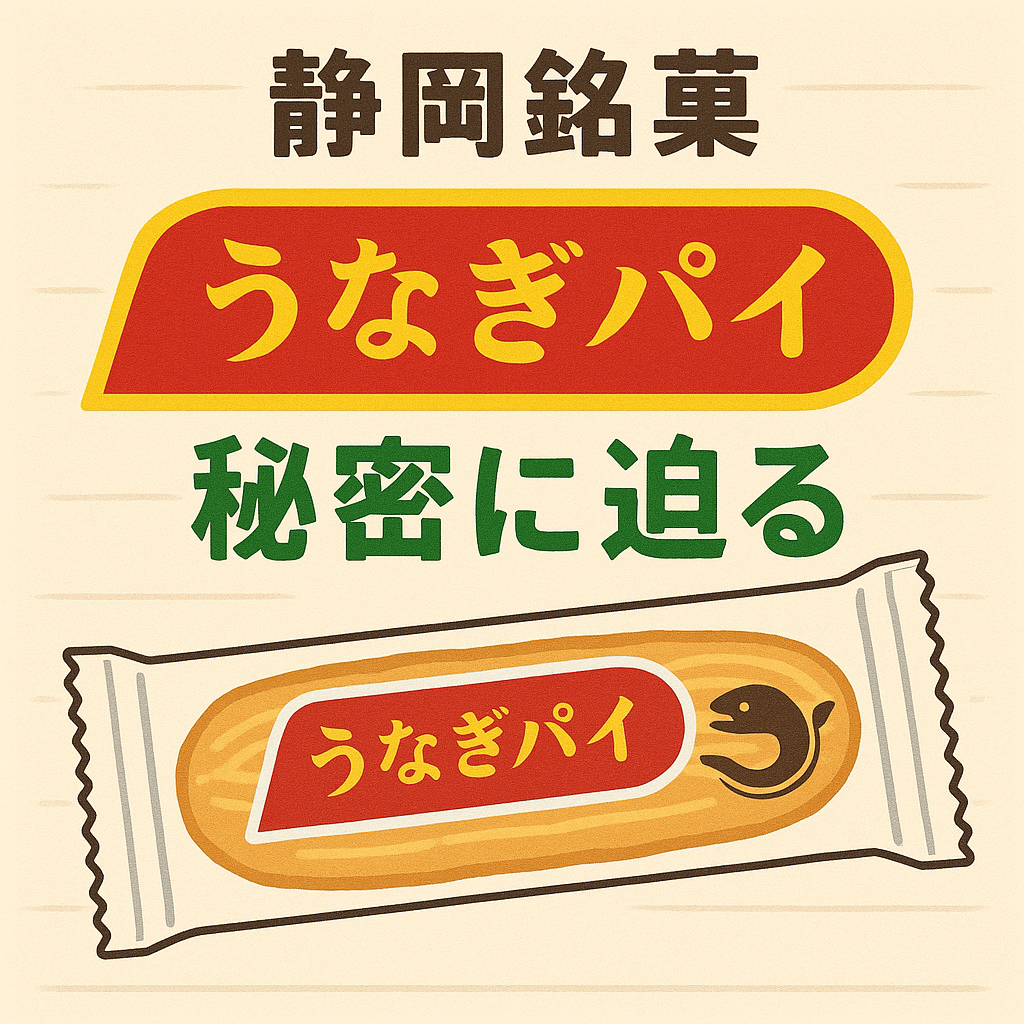
tekowaです。
静岡のお土産といえば、多くの人が思い浮かべる「うなぎパイ」。 「夜のお菓子」としても知られ、長年にわたり幅広い世代に愛されています。 でも、この名前を初めて聞いた人からはよくこんな質問が飛び出します。
「うなぎパイって……うなぎ入ってるの?」
この記事では、その素朴な疑問をヒントに、うなぎパイの正体・歴史・意味、そしてそこから広がる食や文化の視点まで、一緒に見ていきましょう。
うなぎパイには本当にうなぎが入っている?
結論から言えば、うなぎパイには“うなぎ”がほんの少し入っています。
製造元である静岡・浜松の老舗和菓子店「春華堂」によれば、うなぎパイには「うなぎの粉末」が使われています。ただし、量としてはごく微量で、食べたときに「うなぎの味がする!」と感じることはほとんどありません。
このように“うなぎが入っている”ことは事実ですが、実際にはバターや砂糖の香ばしい風味が中心で、パイ生地にほのかに加えられた“うなぎエッセンス”のようなものだと考えるのが正しいでしょう。
「夜のお菓子」の意味は?
うなぎパイのパッケージに書かれた有名なキャッチコピー、「夜のお菓子」。 初めて見る人は、なんだか意味深な印象を受けるかもしれません。
実はこれ、「家族団らんのひとときに、お茶と一緒に楽しんでほしい」という想いを込めてつけられた言葉なんです。
開発当時(1960年代)、まだ娯楽の少なかった時代に「夜に家族が集まってお茶を飲む時間を大切にしてほしい」という願いが込められたとのこと。 つまり、決して怪しい意味ではないのでご安心を。
うなぎパイはどうやって作られる?
うなぎパイは、パイ生地を何層にも折り重ね、バター・砂糖・はちみつなどを加えながら香ばしく焼き上げます。 そこに、ごくわずかな「うなぎの粉末」と、春華堂独自の隠し味が加わることで、あのサクサクで香り高い味わいが生まれます。
この製造工程は、浜松市にある「うなぎパイファクトリー」で実際に見学することができます。 ガラス越しに職人の手作業や機械による工程を見られ、子どもから大人まで楽しめる施設として人気です。
自由研究や地域学習にもおすすめ
うなぎパイは、ただのお菓子にとどまりません。 地域の名産であるうなぎを活かした商品開発、昭和の時代背景を反映したネーミング、観光資源としての工場見学……。
たとえばこんな自由研究テーマに展開できます:
- ・うなぎパイにうなぎが入っている理由を調べてみよう
- ・「夜のお菓子」の意味を考察しよう
- ・工場見学をして、お菓子ができるまでを記録しよう
- ・おみやげってなに?どうして地域限定のお菓子があるの?
また、「自由研究」としてだけでなく、「地域学習」「食育」「伝統文化の発展」という切り口でも十分深められる内容です。
うなぎパイを食べたことがない子へ
「パイにうなぎなんて無理!」と思うかもしれません。 でも、実際に食べてみると「えっ、うなぎどこ?」「めっちゃ美味しい…!」となるのがうなぎパイのすごいところ。
香ばしく焼き上げられたバターと砂糖の風味、絶妙なパリパリ感は大人から子どもまでハマる味です。 お菓子としての完成度が高く、個包装で配りやすいのも人気の理由です。
まとめ|うなぎパイは味もストーリーも奥深い!
うなぎパイには本当にうなぎが入っています。ただしその量はわずかで、風味に大きな影響はありません。 名前の由来や「夜のお菓子」の意味を知ると、単なるスイーツではなく、静岡の文化や家族の時間を大切にする心が詰まったお菓子であることが分かります。
もし静岡に行く機会があれば、ぜひ「うなぎパイファクトリー」を訪れて、自分の目で見て、香りを感じて、お菓子の奥深さを味わってみてください。
おみやげとしても、自由研究のヒントとしても、うなぎパイはたくさんのことを教えてくれる“知るほどおいしい”名菓です。

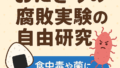
コメント