
tekowaです。
土用の丑の日といえば「うなぎ」。でも、そのうなぎがどこから来て、どんな旅をしてきたかを知っている人は、実はあまり多くありません。
今回は、「うなぎの一生=一大冒険」について掘り下げてみます。どこで生まれ、どこで育ち、なぜ川にいるのに海で生まれるのか。理科や地理、そして環境の学びにもつながる内容で、大人も子どもも一緒に楽しめるテーマです。
うなぎの生まれ故郷は、海の“ど真ん中”だった!
日本でよく食べられている「ニホンウナギ」は、実は太平洋の真ん中にある「マリアナ諸島付近」で生まれます。場所でいうと、フィリピンの東、グアムの近く。そこは水深がとても深く、調査も難航する神秘的な場所です。
ここで産まれたうなぎの赤ちゃんは、「レプトケファルス」という透明で葉っぱのような姿をしています。成長しながら黒潮に乗って日本近海へやってきます。
川にいるのに海で生まれる?うなぎは“両側回遊魚”
うなぎは「両側回遊魚(りょうそくかいゆうぎょ)」に分類されます。これは、海で生まれて川で育ち、また海に戻って産卵する魚のこと。
似たような性質を持つ魚には、サケ(逆に川で生まれて海で育つ)などがいます。うなぎはその反対で、いわば“海生まれの川育ち”。
この両側回遊の仕組みは、私たちの身近な川や田んぼと、遠くの海とが実はつながっていることを教えてくれます。
シラスウナギってなに?
春先のニュースなどでよく聞く「シラスウナギ」は、海から日本の河口にたどり着いた若いうなぎのことです。
体長はわずか5cm前後。体は半透明で、まるで細長いガラス細工のような見た目。食卓で見る蒲焼きの姿とは全く違います。
このシラスウナギは、川や養殖場に取り込まれて成長していきます。つまり、私たちが食べているうなぎのほとんどは、天然で獲れたシラスウナギを育てた“養殖うなぎ”なのです。
どんな川でも育てるわけじゃない?
うなぎは、水質のよい川や湖、または泥の多い場所を好んで暮らします。夜行性で、昼間は岩の隙間や泥の中に潜んでいて、夜になると活動します。
エサはミミズ、小魚、水生昆虫など。見た目はちょっと怖いけれど、意外と雑食です。
養殖うなぎも自然に近い環境で育てられており、水温やエサの管理が非常に重要です。1年半から2年ほどで出荷されます。
成魚になったうなぎはどうするの?
川や湖で数年を過ごしたうなぎは、成熟すると再び「生まれ故郷=マリアナ海域」へ向かって旅立ちます。これが「降海(こうかい)」と呼ばれる行動です。
このとき、うなぎの体は大きく変化します。体色は銀色に変わり、目が大きくなります。いわゆる“銀うなぎ”と呼ばれるこの姿は、長旅に備えて変身した証拠。
しかし、旅立ったうなぎは、その後どうなるか詳しくわかっていません。産卵後に力尽きて死ぬという説もありますが、実際の産卵シーンを見た人はいないのです。
謎が多いからこそ、研究が進む
うなぎの産卵場所や繁殖行動は、いまだに「完全な謎」です。日本や世界の研究者が長年にわたって調査をしていますが、決定的な証拠はごくわずか。
2023年には深海カメラを使った調査で産卵の痕跡らしきものが確認されたものの、映像での確認には至っていません。まるで「深海に消えるミステリーフィッシュ」と言われるほど。
その神秘性ゆえ、うなぎの研究は地理・生物・環境の学問を超えて、多くの専門分野にまたがるロマンのあるテーマとされています。
絶滅の危機と未来
現在、ニホンウナギは「絶滅危惧種(レッドリスト)」に指定されており、資源の枯渇が懸念されています。違法なシラスウナギの捕獲や、環境破壊、気候変動による生育環境の変化など、要因は複雑。
そのため、日本では「完全養殖」技術の研究も進んでいます。これは、人工的に卵から成魚まで育てる技術。現在はコストが高く、一般流通には至っていませんが、未来のうなぎ食文化を守るために重要なステップです。
まとめ:うなぎは“旅する魚”だった
うなぎの一生は、実にスケールの大きな旅の連続です。海で生まれ、川で育ち、また海に帰る。その間、透明な赤ちゃんから銀色の成魚まで、姿も暮らしも大きく変わっていきます。
土用の丑の日にうなぎを食べるとき、ぜひその壮大な物語にも思いを馳せてみてください。知ることは、食べることをより深く豊かにしてくれるはずです。
「知る」ことが「守る」ことにつながる。うなぎの未来を考えるきっかけになりますように。
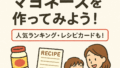

コメント