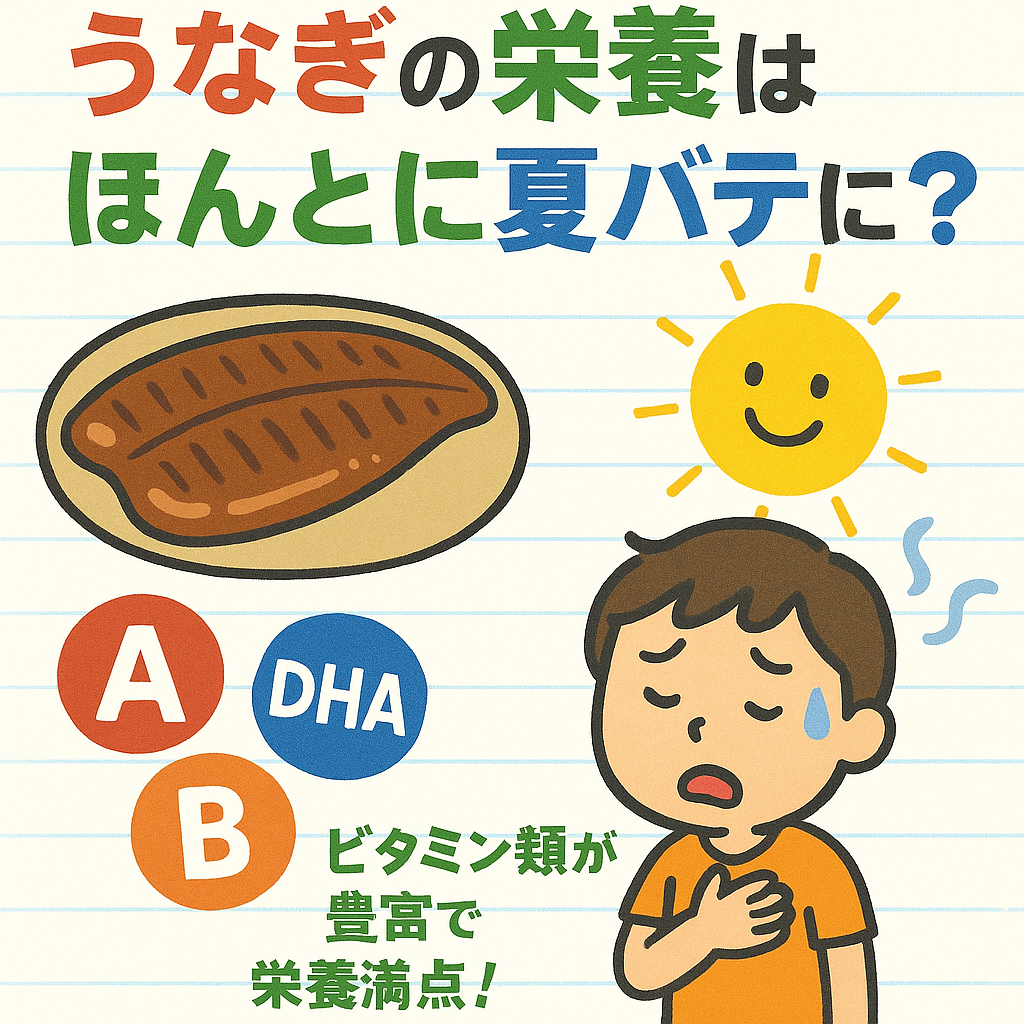
tekowaです。
土用の丑の日といえば「うなぎ」——。暑い夏を乗り切るために食べるスタミナ食として、日本では長年親しまれてきました。でも本当に、うなぎって夏バテ対策に効くのでしょうか?
今回は「栄養士」の視点で、うなぎの栄養素とその働きを分かりやすく解説。さらに、食べる際の注意点や向いている人・向かない人など、“うなぎの本当のチカラ”に迫ります。
うなぎの栄養成分をチェック!
まずは、うなぎの蒲焼き100gあたりの代表的な栄養成分を見てみましょう。
- エネルギー:約290kcal
- たんぱく質:約23.0g
- 脂質:約20.0g
- ビタミンA:約1,500μg
- ビタミンB1:約0.75mg
- ビタミンB2:約0.74mg
- ビタミンD:約19μg
- DHA:約1,300mg
- EPA:約900mg
栄養価は全体的に非常に高く、特に注目されるのがビタミンA・D、そしてDHAやEPAなどの不飽和脂肪酸です。
夏バテに効く理由は「脂溶性ビタミン」と「たんぱく質」
夏バテの原因には、食欲低下、脱水、ミネラル不足、睡眠の質の低下などがあり、それに対抗するためには「代謝を上げる栄養」「胃腸に負担をかけすぎない食材」が理想です。
うなぎに豊富な栄養素のうち、特に夏バテに効果的とされるのが以下の3点です。
- ビタミンB1:糖質をエネルギーに変える働きを助け、疲労回復に貢献
- ビタミンA:粘膜を強くし、夏風邪予防や免疫アップに役立つ
- 高たんぱく質:筋肉維持や代謝促進に必要不可欠
つまり、うなぎは「疲れやすい夏の体」にうれしい要素をしっかり持っている、まさに“栄養のかたまり”ともいえる食材です。
ただし、脂質とカロリーは高め。注意が必要な人も?
うなぎの脂質は100gあたり約20gと、かなり高めです。蒲焼きは甘辛いタレもかかっているため、ご飯との相性がよく、ついつい食べすぎてしまいがち。
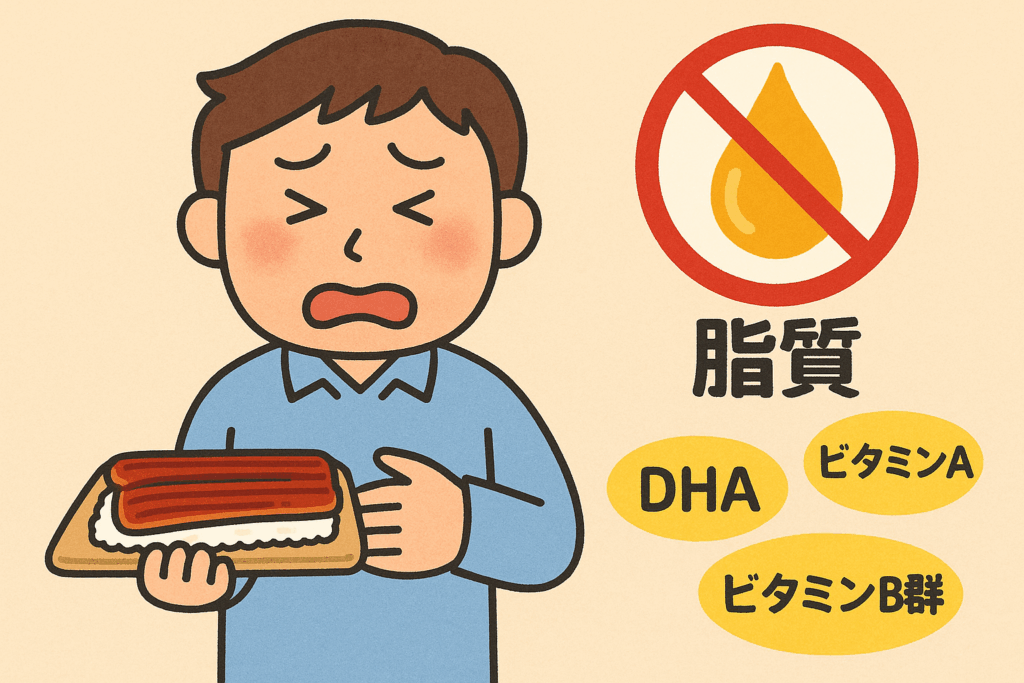
注意したいのは以下のような方々です。
- 脂質制限をしている人(例:高脂血症・脂肪肝の方など)
- 妊娠中の女性(ビタミンAの過剰摂取リスクがある)
- 小さなお子さん(栄養過多やタレの塩分に注意)
栄養満点な一方で「とりすぎはNG」な栄養素も含むため、食べる量や頻度には注意したいところです。
土用の丑の日にうなぎを食べるのは“理にかなっている”?
土用の丑の日にうなぎを食べるようになったのは江戸時代の話。学者・平賀源内のアイデアで始まったといわれていますが、当時も「うなぎは滋養強壮に良い」と考えられていたようです。
実際、江戸時代の食生活では動物性たんぱく質が乏しく、うなぎのように栄養豊富な魚は貴重でした。そう考えると、猛暑に耐える日本の夏に、体力回復を目的に食べるという流れは、現代にも通じる面があります。
夏バテ対策に向いている人・向いていない人
では、どんな人にうなぎが向いているのでしょうか?
◎向いている人
- 食が細くなりがちな人
- 夏でも肉体労働や運動量が多い人
- 高齢者で筋力維持を意識したい人
△控えめにしたい人
- 脂質やカロリー制限が必要な人
- ビタミンAの摂取量に注意が必要な妊娠初期の方
体質や健康状態によっては、「夏バテ対策だからといって必ずしも最適とは限らない」という視点を持つことが大切です。
結論:うなぎは栄養満点!でも“適量”が鍵
うなぎは、たんぱく質や脂溶性ビタミン、DHA・EPAなど非常に栄養価の高い食材であることは間違いありません。「夏バテに効く」と言われるのは科学的にも根拠があります。
ただし、脂質・カロリーが高く、食べすぎによる影響もあるため、家族でシェアする、週に1回のごちそうにするなど、量と頻度を調整しながら取り入れていくのが理想です。

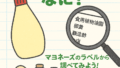
コメント