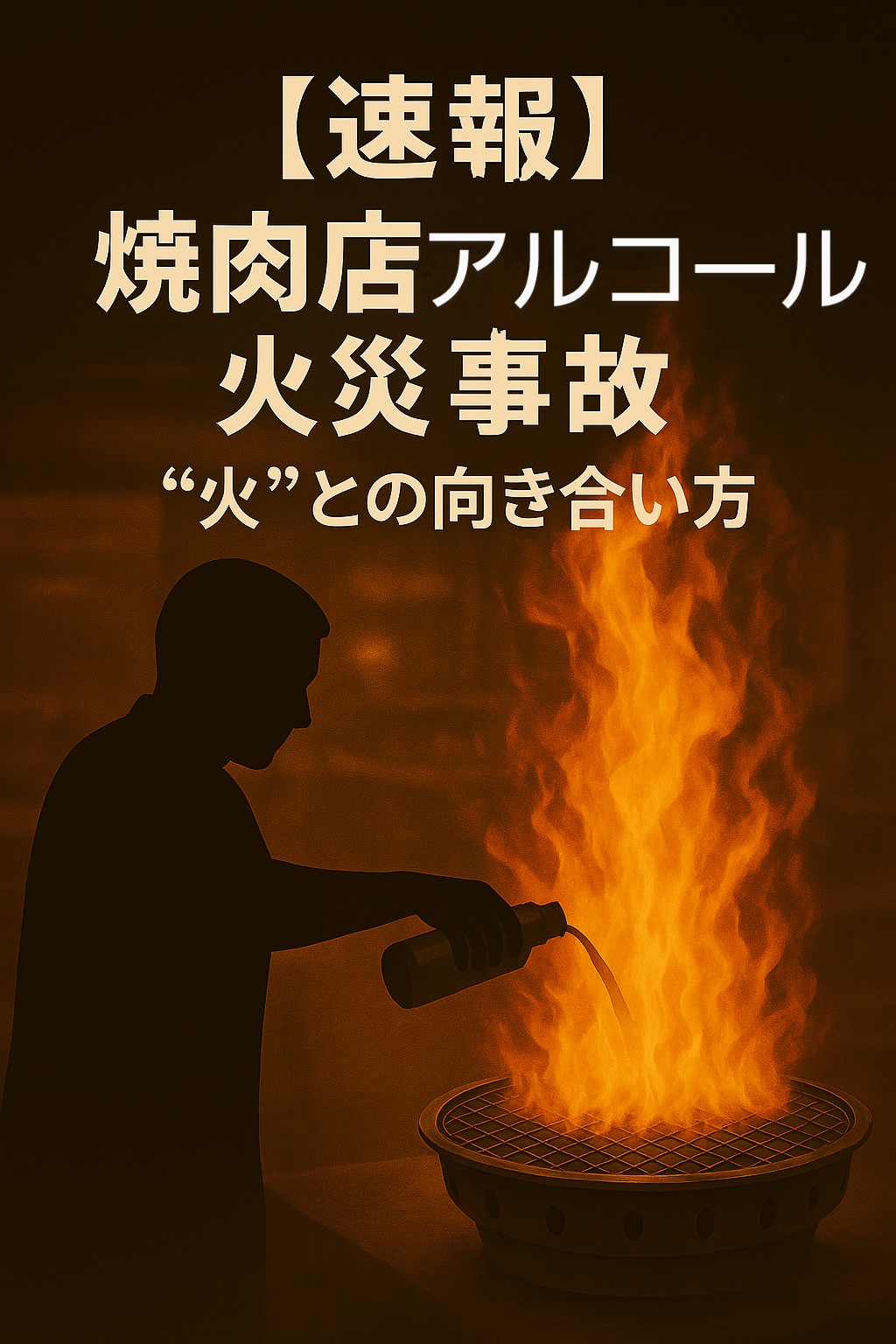
tekowaです。
2025年7月下旬、ある焼肉店で火災事故が発生し、女性客が重いやけどを負ったという報道が入ってきました。事故の原因は、グリルに使用されていた消毒用アルコールの継ぎ足し中に引火したことによるものとされています。
アルコールバーナーは、調理や演出の場面で「見た目に派手で手軽」とされる反面、取扱いには高度な注意が求められるものです。
今回の事故を受けて、日頃から“火”に関わる立場である栄養士・保育士補助・介護福祉士の視点から、火の取り扱いと事故防止について考察してみましょう。
事故の概要:見えない炎が“危険”を隠していた
報道によれば、焼肉店のスタッフが調理用グリルに消毒用アルコールを継ぎ足した際に火が上がり、その場にいた女性客に火が燃え移ったとされています。
アルコールは蒸発しやすく、空気中に拡散した蒸気に引火する性質を持ちます。特に炎が目に見えにくい状態でも燃焼が続いていることがあり、油断すると一気に火が上がる可能性があります。
一部では「燃えていないと思った」との証言もあり、見た目だけで判断するリスクの大きさが浮き彫りになりました。
栄養士の視点:火気使用責任者としての自覚
保育園や介護施設などでは、厨房でガスやIH、時にはアルコールランプを使用する機会もあります。
消防法や自治体の指導に基づき、施設では防火管理者や火気使用責任者が定められており、栄養士や調理員がその役割を担うケースが少なくありません。
火気を扱う場面では、以下のような事故が実際に報告されています:
- ガスの消し忘れによる引火事故
- アルコールバーナーの誤使用によるやけど
- 紙製メニューや布巾など可燃物の接触による発火
これらの事故は「慣れ」「忙しさ」「確認不足」に起因することが多く、定期的な点検と研修の重要性を改めて感じさせます。
また、子どもと一緒に行うクッキング保育や食育イベントでは、火を扱うときに「火の状態を目で見て確かめられないリスク」にどう対応するかが問われます。
保育補助の視点:子どもと火の“適切な距離感”を考える
子どもにとって“火”は身近ではない存在です。多くの家庭ではIHが主流になり、マッチやライターの使い方を知らない子も増えています。
保育現場では:
- 日常的な避難訓練や防災週間で火災の危険を伝える
- 火を使う活動(キャンドル作り、焼き芋、キャンプ)を通して正しい扱い方を学ぶ
- 遊びや紙芝居を活用した間接的な教育で印象付ける
「火=危ない」だけではなく、「火=便利であたたかい。でも扱い方にはルールがある」という理解を伝えることが大切です。
事故を防ぐためには、保育補助の立場であっても、火の性質や扱いに関する基本的な知識を持ち、子どもの行動を予測する視点が求められます。
介護福祉士の視点:高齢者施設の火災リスク
介護現場では、調理レクリエーションやバーベキューイベントなどで火を使用する場面がある一方、高齢者の安全確保という重要な任務も伴います。
特に注意したいのは:
- アルコールランプや携帯コンロの使用時における器具の配置と管理
- 認知症のある高齢者の行動予測と避難導線の確保
- 一人で作業させない、必ず複数名で監視体制を整える
火を使うイベントには、日頃の訓練だけでなくヒヤリハット報告を共有し、過去の失敗や気づきを活かす取り組みが欠かせません。
提供者・ホールスタッフへの教育とマニュアル
今回の事故は、厨房ではなくホールスタッフ側で起きたという点も見逃せません。つまり、“火に慣れていない立場”の人が、日常的に火気を扱っていた可能性があるのです。
その場合、以下のようなマニュアル整備と教育が必要です:
- アルコールバーナーの継ぎ足しは絶対に「火が消えてから」と明示
- 引火性燃料の取扱マニュアルを作成・全員に周知
- 新規アルバイトやパートへの実技含む研修の実施
現場の「慣れ」や「忙しさ」で安全確認が疎かにならないよう、仕組みそのものを設計することが求められます。
まとめ:火は“日常の中にある危険”である
火災事故は、日常のほんの一瞬の油断が引き金になります。
とくに今回のように目に見えにくい火を扱う場合、そのリスクは一層高まります。
保育・福祉・栄養の現場では、「火気使用責任者」という立場であれ、そうでない立場であれ、火に対して“責任ある距離感”を持つことが求められます。
事故は誰にでも起こり得る――だからこそ、私たち一人ひとりが、“明日は我が身”と考えて行動したいものです。


コメント