
tekowaです。
もうすぐ夏休み。自由研究どうする?
もうすぐ夏休み。夏休みといえば自由研究…
「何をテーマにすればいいの?」「どうまとめたらいい?」と悩むお子さんや親御さんも多いのではないでしょうか?
そこで今回は、小学校の低学年・中学年・高学年・中学生それぞれに合わせて、自由研究のテーマの決め方・まとめ方のポイントを紹介します。
「どんなふうに書けばいいの?」「うちの子、まだ文字が書けるか心配…」という方も大丈夫。
学年別のテンプレートと実例をもとに、“自分で考える力”を育てる自由研究を一緒に作っていきましょう。
各学年別テンプレートはこちら
- ▶ 小学3・4年生向けテンプレート
- ▶ 小学5・6年生向けテンプレート
- ▶ 中学生向けテンプレート
- ▶ 自由研究ってなんのためにあるの?親も知っておきたい目的とは
まだ小学校に入って間もない1・2年生。
文章を書くことや、まとめることがむずかしく感じる子も多いかもしれません。でも、自由研究は「自分で調べて、自分で感じたことを言葉にする」ことが一番大切。
この時期は、大人が手伝いすぎないように、子どもの「なぜ?」「どうして?」を大切にしながら、簡単な形で楽しくまとめてみましょう。
■おすすめの研究テーマ例
- 身のまわりにある不思議(野菜や果物、天気、虫、水など)
- 食べものや飲みものの違い(冷たい/あたたかい、甘い/すっぱい)
- 植物の観察(朝顔やきゅうりなど、育てている植物)
- 「やってみた!」実験(氷がとける速さ比べ、ぬるぬるせっけん実験など)
- おうちの手伝い体験記(お皿洗い、洗濯たたみなどを自分でやってみた記録)
■自由研究テンプレート
1. しらべたこと(テーマ)
どんなことを調べたのか、タイトルのように書きます。
例:すいかのたねは なんこある?
2. きっかけ(どうしてこれを調べようと思ったのか)
「○○を食べていて、ふと気になった」「テレビで見てやってみたくなった」など、子どもがどう思ったかを短く素直に書きましょう。
3. よそう(こうなるんじゃないかな?と思ったこと)
自分なりの予想を書きます。まだ難しい子には「~だとおもう」と一言だけでもOKです。
4. しらべたこと・やったこと
自分でやってみたこと、見たことを絵や言葉でまとめます。写真や絵を貼ってもよいです。
5. わかったこと・おどろいたこと
「思ったより多かった」「ぜんぜんなかった」「すごく変わった」など、子どもなりに感じたことをまとめましょう。
6. かんそう
「たのしかった」「またやってみたい」「ちょっとたいへんだった」など、自由に書きましょう。
■まとめ方の工夫
- 大きな紙1枚に見やすくまとめる
- 写真や絵をたくさん貼って、文字は少なめに
- マス目のノートや自由帳を使って絵日記のようにまとめてもOK
■親御さんへのヒント
1・2年生の自由研究は、調べる内容より「自分でやってみてどうだったか」を言葉にする練習の場と捉えるのが良いです。
まだ自分ひとりでは文章にするのが難しい子も多いので、親御さんが「こんなこと思った?」と声をかけながら、子どもが話した言葉をそのまま書き留めてあげるとスムーズです。
また、「正しい答え」よりも、「自分なりの発見や驚き」を大切にしましょう。
たとえば「氷がすぐにとけた!」だけでも立派な観察です。「じゃあなんでとけたのかな?」と一歩踏み出すきっかけを作ってあげるのが、親の役目です。
■この学年で伝えたいこと
- 自由研究は、「自分で気づいて、自分でまとめること」が楽しいものだと感じてもらう
- 答えを見つけることより、「やってみた」ことを大切にする
- 観察や記録の習慣を持つきっかけになる
■このテンプレートを使って自由研究を書くと…
- 先生にも伝わりやすい、まとまりのある研究ができる
- 子どもが主体的に取り組みやすい
- 親子で楽しみながら進められる
■参考:他の学年向けテンプレート
企画・構成:tekowa
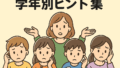

コメント