
tekowaです。
土用の丑の日が近づくと、スーパーやコンビニにずらりと並ぶうなぎの蒲焼き。しかし、年々その価格が上がっていると感じたことはありませんか?「気軽に食べられない」「うなぎって高級品だよね」と思う方も多いはず。
この記事では、うなぎの価格がなぜここまで高騰しているのか、背景を分かりやすく解説します。
うなぎが高い3つの主な理由
① シラスウナギの漁獲量減少
うなぎは天然の稚魚「シラスウナギ」を養殖して育てますが、そのシラスの漁獲量が年々減少しています。
温暖化による海流の変化、環境破壊、違法漁業などの影響により、資源としての供給が非常に不安定になっているのです。
その結果、シラスの取引価格は高騰し、1kgあたり数十万円にもなることも。
② 養殖コストの増加
うなぎの養殖はとても手間がかかります。
水温管理や病気予防の徹底、育成期間中の品質保持など、他の魚に比べて管理コストが高くつきます。
さらにエサ代・燃料代・人件費の高騰が追い打ちをかけており、養殖業者の負担は年々増加しています。
③ 輸入うなぎへの依存と為替の影響
日本で流通するうなぎの約6割は、中国や台湾などからの輸入品。
特に最近は円安傾向が続いており、輸入コストが上がっています。
これにより、比較的安かった中国産うなぎも価格が上昇し、消費者が「うなぎ高っ!」と感じる状況になっているのです。
かつては庶民の味だったうなぎ
昭和の時代には、土用の丑の日にうなぎを家族で楽しむのが一般的でした。
うな重をテイクアウトする家庭や、実家で蒲焼きを焼く香りに包まれて育った人も多いでしょう。
しかし現在は、一尾3,000円以上の商品も珍しくなく、特に子育て世帯や高齢世帯には「贅沢品」として敬遠されがちです。
それでも食べたくなる“特別感”
それでも、暑さで体力が落ちる夏の時期にこそ、栄養満点なうなぎは魅力的。
ビタミンAやB群、DHA・EPAなどの健康成分も豊富で、夏バテ対策やスタミナ補給にぴったりです。
価格を見極めて、上手に選ぶ
最近では、コンビニやスーパーでも手頃なハーフサイズ、真空パックの冷凍うなぎなど選択肢が増えています。
「どこで買うか」「どんな加工か」「産地や加工方法」などを意識して、納得できる一尾を選びたいところです。
次回予告|話題の「イオンのメスうなぎ」、その魅力とは?
うなぎの価格高騰にはさまざまな理由がありますが、それでも「買いたい!」と思わせてくれる特別なうなぎがあります。
次回は、いま注目の「イオンのメスうなぎ」にスポットを当て、メスならではの味わいや企業努力による育成管理などを詳しくご紹介します。
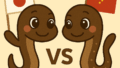
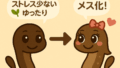
コメント